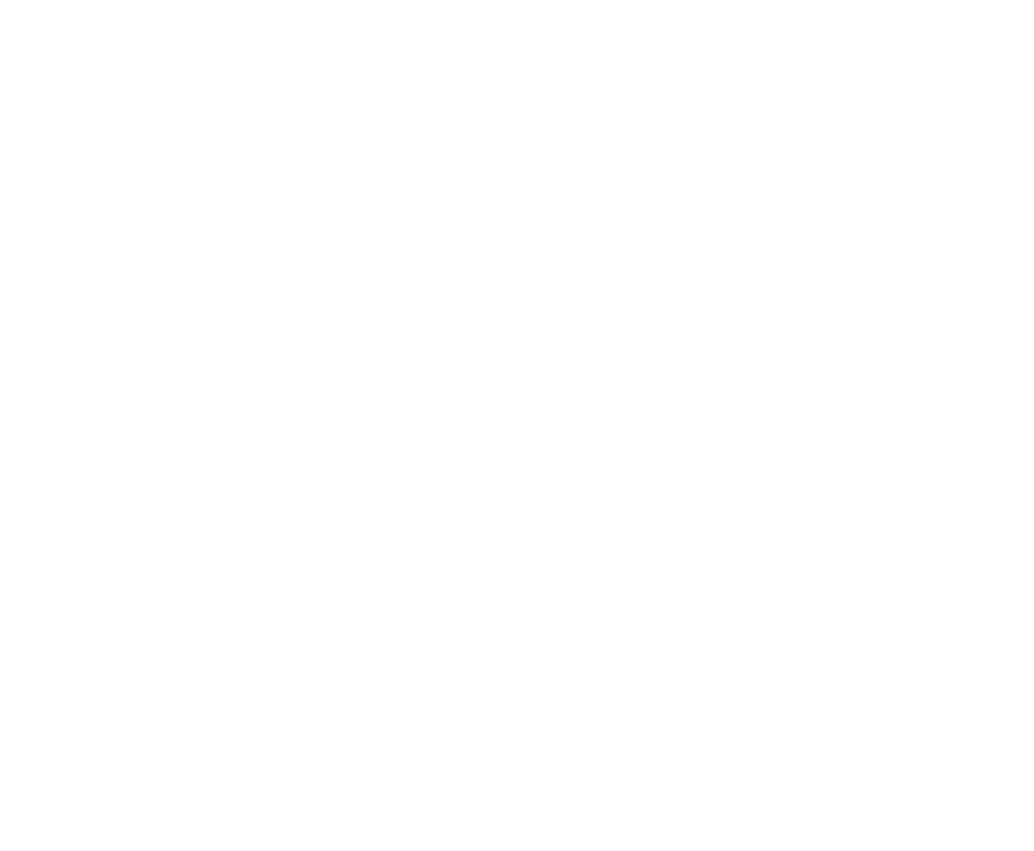今朝も嫌な夢で目が覚めた。
右を向けど左を向けど、目に入る全ての人が皆同じおじさんになっている夢だ。
母と思わしきおじさんが台所で鼻歌交じりに料理の味見をしている。エプロン姿にオタマを持つ手の小指を立てている様子はいただけない。妹と思わしきおじさんは制服を纏い、髭跡の目立つ顔に真剣な表情でメイクしていた。こちらもまた、強烈な絵面だ。しかし、二人は何事もないかのようにいつものルーティンを進めていく。父はもう仕事へ向かったのだろうか、姿を見かけない。外へ出ても奇妙な光景が広がっていた。お洒落なOLと思わしきおじさん、幼稚園への送り途中の母子と思わしきおじさんペア、学校へ行くと思わしき制服のおじさん… 私の頭はおじさんだらけでパンクしてしまいそうだ。女子校通いの私が学校へ着いてもおじさんしか存在しない。仲のいい亜弥と美寿々、真面目な花恵、クラス一可愛い奈美陽、担任の景子先生、全員が同じ顔のおじさんとなっている。
こんなのおかしい!
そう叫ぶと同時に目を覚ましたのは今日で何回目だろう。憂鬱な気分に飲まれながらも私は登校の身支度を済ませ、玄関を出た。勿論、通学途中にすれ違う人々はそれぞれ異なる姿をしている。学校に着いてからもいつもの光景が待っている。
変わり映えのしない日常がどれだけありがたいものなのだろうか。そんなことを思っていながら時間は過ぎてゆき、あっという間に放課後を迎える。
「裕美子もカラオケ行く?」
「ごめん、亜弥。私、今日も寄っていかなきゃいけないとこがあってさ」
「え〜、また? 最近付き合い悪くない? 雰囲気も変わった気がするし、もしかして彼氏ができたとか!?」
「違うよー、近くのおじさんが怪我しちゃってさ、今日は私が手伝いに行かなきゃいけないの。明日ならいけると思う、ってか行きたい!」
「そっかぁ、じゃあ明日遊ぼうよ。お手伝い、頑張ってねー」
友だちの誘いを断り、自宅からほど近いマンションの一室へと急ぐ。この近辺でひときわ目立つ高層マンションは家賃も相当な額であると有名だ。エントランスへ到着、エレベーター内で髪を整え、私の髪ってサラサラしていて綺麗だよね。36階到着の合図を受け、自惚れも程々にし、おじさんに住む3601号室へと向かう。インターホンを押すとすぐに玄関が解錠された。中に入るといつものようにおじさんが私を責め立てるように告げる。
「今日こそアタシの身体を返してよね!」
やれやれと思いながらも、私は冷静に言葉を返す。
「来るなり毎回その話をしてもしょうがないじゃない。それよりも、はい。今日もやるんでしょ? いつもの」
「当たり前じゃない! アタシが佐倉裕美子なんだから。早く脱ぎなさいよ」
「はいはい…」
おじさんに促され、私は素直に服を脱ぐ。おじさんの前で女の子が裸になるのだ。一般的に考えれば、いかがわしい場面に間違いない。私たちにおいても、それ自体は否定できないのだが、普通とは少し異なる。おじさんは私の脱いだ制服を手に取ると、すぐに着用し始めるのだ。
「あぁ、アタシの制服… アタシの匂い…」
今さっきまで私が着ていた制服を着込んで、おじさんが感情に浸っている。はっきり言って気持ち悪い。女の子の香りに反応したのか、スカートの真ん中辺りが持ち上げられている。色々な趣味嗜好の人がいるとはいえ、誰の目にもしんどい絵面だと映るだろう。
「その格好、正直見ててキツいんだよね」
「アタシだってわかってるわよ! だから、早く身体を返してって言ってるの!」
「私だって可哀想だとは思うけど、おじさん見てると… まぁ、ね…」
「な、何よ?! アタシが自分の制服にこだわって問題あるわけ? それから、アタシのことをおじさんって呼ばないで!」
「百歩譲ってそこは目を瞑ったとしても、ほら、おちんちんが…」
「し、仕方ないでしょ! アタシの匂いのせい、じゃなくて、この身体が勝手に反応しちゃってるんだから… そうよ、おじさんのせいなの!」
「私にそういう趣味はなかったよ? でも、たしかに私の着ていた制服のニオイで興奮しちゃってるんだから、今の私のせいか、フフ♡ じゃあ、早速今日もやっちゃおっか、女装大好きおじさん?」
「フ〜ッ、フ〜ッ… なんか癪だけど、もう我慢の限界だし、早くしてェ!」
おじさんのスカートを捲し上げると、今どきあまり見ないようなブリーフを突き破りそうなほど真っ直ぐ反り立つ肉棒の主張が目に入る。左右どちらかにずらせば多少は楽だろうものの、これでは先端がずっと布にあたって刺激が与え続けられ、放っておいたらしばらく勃起したままではないか。ビジュアル的に耐え難いが、それもそれで滑稽だ。私はブリーフの窓から硬くなっている肉棒を摘み出すと指先に力を入れて握った。
「アッ、アァ…ンッ… いきなりやるのは卑怯よォ…ウァンッ」
おじさんが何か言っているが、これで手を止めたら止めたで文句を言うのは見えている。私はさっさと終わらせようと先端を強めに刺激しながら上下運動を続ける。
「ハァ、ハァ… 気持ちィイわ…アタシ、女の子なのにィ… ウッ…… もう出ちゃった…」
小さな右手へ放出された白濁液をティッシュに拭って、おじさんを白い目で見ながらおじさんへ笑み混じりに問う。
「今日も随分と気持ち良さそうだったけど、まだ自分のことを女の子だなんて言うわけ?」
「フゥ… 当たり前でしょ! 大体、こんなことをしてもらわなくちゃいけないのもアタシの身体を返してくれないからだし!」
「そんなこと言っても元に戻る方法がわからないんだから、私だけ責めても仕方なくない? あとさ、あんまり言わないほうがいいかもだけど、私がその身体だったときよりも頻繁にヌいてるのは“おじさん”の意思だと思うよ?」
「おじさんって呼ぶなって何度も言ってるでしょ! アタシが裕美子なんだから!」
「わかった、わかった。じゃあさ、“裕美子ちゃん”は自分の制服を着ただけでおちんちんを大きくしちゃう、髪は薄くなりつつあるのに、口の周りが髭跡で青い“女の子”ってことなんだね?」
「い、今は身体を盗られてるからなだけで、アタシはこう見えてもピュアだったの!」
「身体を盗られたのはお互い様だよね。私だって愛しのムスコが股になくなって寂しいときもあるもの。で、どうする? 明日は来てあげられないけど、もう一本くらいイっとかなくて大丈夫?」
「なんで明日は来れないのよ?! 毎日情報共有に来るって話だったわよね?」
「たまには亜弥たちと遊ばないと友だち関係にも響くからさぁ。元に戻れたとき、オトモダチがいなかったら可哀想だと思って。亜弥も仲良くしてくれてるから安心してね。私も亜弥のこと、大好きなの」
「亜弥ッ! 亜弥に変なことしてないでしょうね!?」
「失礼しちゃうなぁ。今は私が“佐倉裕美子”っていう、れっきとした女の子なんだよ! 女友だち同士でやっておかしくないことしかやってないに決まってるじゃない。あれ? 裕美子おじさんったら、またアソコが大きくなっちゃってるけど、亜弥のことでも想像しちゃったのかしら? 」
「クッ… ち、違うわよ…」
「ダメだよ。オトモダチのこと考えて勃たせちゃったら。まさか、亜弥のこともオンナとして見ちゃってるとか?」
「違うって言ってるでしょ! いいから早くヌきなさいよ!」
「怖っ! 女の子にそんな言い方するなんて、喋り方以外はすっかりオジサンね…」
「ごちゃごちゃうるさいぃ! アンタはいいわよ。アタシみたいな若くてかわいい女の子になれたんだから。口調も女子っぽくしてるくらいだし、楽しんでるんでしょ。それに比べてアタシは何も悪いことなんてしてないのに、いきなり男に、しかもおじさんになっちゃったのよ? なんだから、ヌくくらいしてくれたっていいじゃない!」
「そっかぁ… やっぱり私、いや僕みたいなおじさんになるのはイヤだよね… 辛いよね… でも、僕は40年ちょっとの間、その身体で生きてきたんだよ… まだ何週間かしかその身体で過ごしてない“裕美子ちゃん”にそこまで嫌がられちゃうと僕も哀しくなっちゃうな…」
「ご、ごめんって……」
「いや、いいんだよ。正直な気持ちだろうし、わかるから。今の僕、いや私は毎日がすごく楽しいもん。だからこそ悪いとも思ってるの。ただ、戻れるまでは私に佐倉裕美子でいさせてほしい。できる限り寄り添うからさ」
「おじさん… アタシも悪かったわ、ごめん。でも、イヤになっちゃうわね。切ない場面でもアタシのちんちんはおっ立ったままだなんて」
「もう一回私がヌいてあげるから大丈夫。今日は特別、クチでヤってあげる」
「本当に?! 聞いたことはあるけど実際にやってもらえるなんて初めてよ。はやく、早くゥ!」
私だって口でしてもらったことなんてない。フィクションのなかで観たことはあるが、手でヤるのとは勝手が違う。あくまで想像をもとにおじさんのおちんちんを咥える。強烈な臭いや喉のほうまで先っぽが届く度にオエッとなりそうになるが、今そんな素振りを見せたら、せっかく裕美子ちゃんを上手く言いくるめた雰囲気を壊しかねない。今後も僕が“私”でいるためには、目の前のおじさんとどうにか上手く付き合い続け、穏便な生活を守る必要があるのだ。
「ハァ、ハァン、アァ… あっ、痛っ! 出るゥ…」
肉棒が歯にあたった際に思わず噛んでしまったらしい。その弾みに勢い余って出てしまったドロドロの臭い液体が私の口を不快感で満たす。痛いと言いながら、それさえも快感とした“彼”にはM男としての適性があるのかもしれない。私が精液を吐き出そうとするとおじさんは切なそうな上目遣いで私を見つめてくる。
「吐かないで…飲んでよ、アタシのなんだから…」
キツめな口調のどこかに弱々しさを感じた私は嫌々ながら飲み込んであげた。喉越しの不快感だけでなく、屈辱的な気持ちが同時に私を襲う。だが、私が私でいることを邪魔されないためであればお安いものだ。おじさんに貸していた制服を着て、私は今の自宅ーー佐倉家ーーへ帰る支度を始める。一、二時間ほどという短い時間でも中年男性が着ていた服に頭を通すと加齢臭だろうか、嫌な臭いが鼻に刺さる。少し前までは自分からこの臭いが漂っていたなどと思いたくもない。
「それじゃあ、また明後日来るから。私が来なくてもやり方はわかるよね。もう何度も自分でヤってるんだし」
「ね、ねぇ… 何でもいいからアタシの服を置いていってくれない?」
「裕美子ちゃんは元自分の着衣が大好きなんだね。尖った趣味だこと。だけど制服は無理だから… もしかして、女の子にノーパンで帰れっていうの?!」
「中身は女の子じゃないでしょ! 第一、アタシのパンツを履いていけばいいじゃん」
パンツをとりかえっこして履かされるという、これまた裕美子おじさんの癖に付き合わされることに唖然としながらも、早く帰りたいと思った私は言う事を大人しく受け入れてマンションをあとにする。
やっぱり男モノの下着ではサイズも合わずスースーするが、外に出てしまった今さら何を言っても仕方ない。今日もなんとか私は今の生活を守ることができた。明日はおじさんに会わないので少なくとも明後日までは私が“佐倉裕美子”として生きられる。お金に不自由のなかった以前と比べて、限られたお小遣いでやりくりするのは大変だ。いつでも好きなときに食べたいものをデリバリーして貰えるようなこともなくなった。しかし、今の私には周りの全てがキラキラして映る。むしろ眩し過ぎるくらいで、私には勿体ないくらいであるとともに、失うことをこれほど恐ろしく思うのは初めてだ。友だちにも恵まれ、家族の待つ温かい家庭がある。私、佐倉裕美子は幸せな女の子だ。こんな日々がいつまでも続けばいいのに。いや、絶対に手放してなるものか。あんな身体に戻るなんて冗談じゃない。受験、就職、結婚、出産… なかには辛いことだってあるかもしれない。それでも私が私であり続ければ、多くの未来が待っているのだ。
「もしもし、お母さん? うん、もうすぐウチに着くよ。夕飯なに〜?」
他愛のない電話ひとつすら楽しい。私は“いつもの”帰り道を足取り軽く駆け出した。
私事ですが、昨年は締切前日にエントリー、即日入稿というギリギリのスケジュールだったことを教訓に、今年は多少の余裕を持って準備させていただきました。
本作ではおじさんの女子の入れ替わりを扱い、空気感を意識して書いてみました。冒頭から「入れ替わりじゃないじゃん!」とのお叱りをいただきそうですが、れっきとした入れ替わりモノなので遊びとして見ていただければと。
個人的に普段はあまりおじさんと若い女子の入れ替わりを扱っていないため、新鮮な気持ちで書き進められましたが、如何でしたでしょうか。少しでも楽しんでいただけていましたら幸いです。
末筆となりましたが、この度は素敵な企画ありがとうございました。
TSFesの今後にも大いに期待しております。