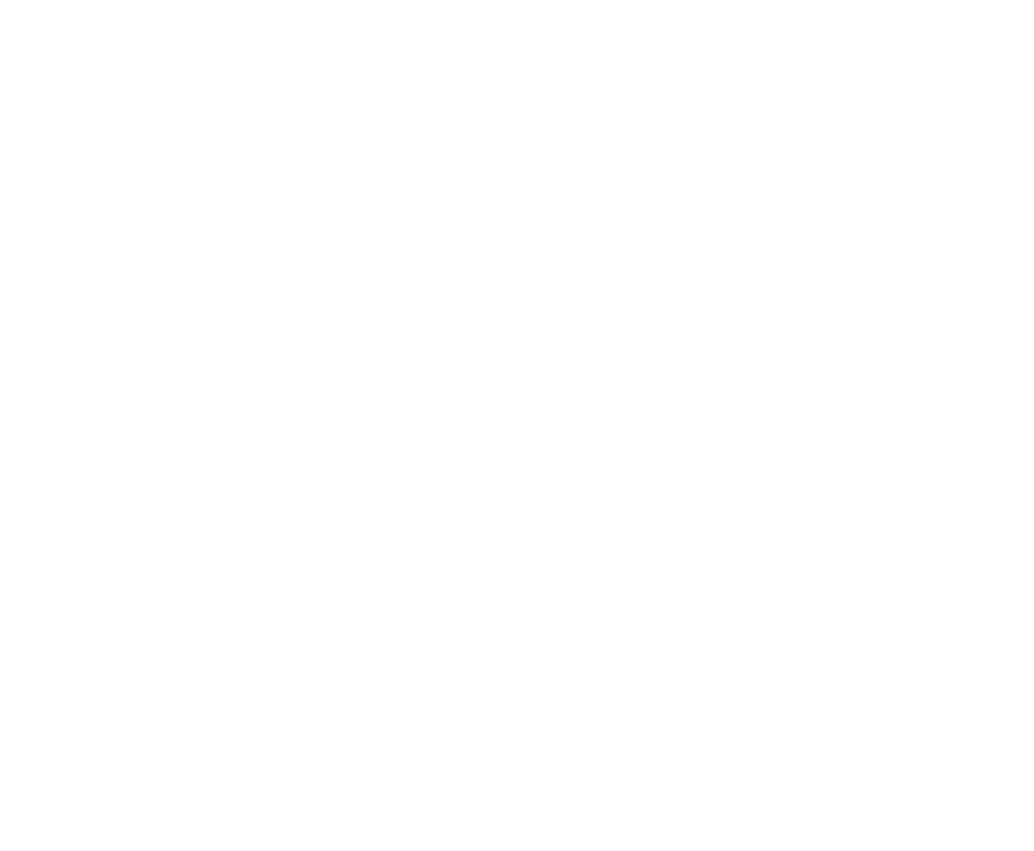青春なんてあっという間。
よく聞くフレーズだが、高3の私にはまだよくわからなかった。
そう、あの日までは…
◇
「シンゴ、一緒に帰ろっ?」
昼休みもそろそろ終わる頃、いつものように私はシンゴへ話しかける。
杉本シンゴ、私の同級生で彼氏。マジメで色白だが、運動神経も抜群と、文武両道を体現したような男子だ。
「水原さん、放課後ちょっと残ってくれないかしら…」
他人行儀な呼び方に、どこか女性らしい仕草をとるシンゴに違和感を覚える。彼なりの冗談だろうか。
「どうしたの? いつもユッコって呼ぶのに」
シンゴはより驚く発言を続ける。
「実はアタシ、杉本くんじゃないのよ」
「何それ? あっ、わかった!入れ替わっちゃった〜ってやつ観たんでしょ?」
私は様々な感情を隠すために、シンゴの言葉にノッたつもりだったが、彼がトーンを変えることはなかった。
「とにかく、放課後お願いよ」
午後の始業を告げるチャイムが鳴り、私は自分の席へ戻る。
◇
女性口調で自分はシンゴではないというシンゴの意図はなんなのだろう。
そんなことを考えているうちに午後の授業は終わり、呼ばれていた理科準備室へ向かう。
「失礼しまーす」
扉を開けると既にシンゴの姿があった。横には園田先生が座っている。
「ユッコ、俺だよ!わかるよな?」
「えっ、園田先生?」
園田ミホ、36歳。美人ではあるものの、さぞや自分に自信があるのか、高飛車な雰囲気が否めない。一部の男子生徒からは絶大な人気を持つ国語教師だ。
そんな園田先生が自分のことを俺と言い、私をユッコと呼んでいる。
「今朝、園田先生と入れ替わっちゃったんだよ。ユッコなら信じてくれるよな?」
「バカなこと言って、二人で私をドッキリにはめようとしてるの?」
「いや、本当なんだって!なんでも聞いてくれよ」
「そうね。アナタたち、付き合ってるんでしょ。二人しか知らないこともあるでしょうし、それが早いわ」
大股を開きながら机へ前のめりになる園田先生と、短い髪の襟足をいじりながら、どこかのギャルのように語るシンゴ。
私の質問へスラスラと回答する前者と、机に肘をつきながら脚を組み『ふ〜ん』と聞いている後者。
私は二人が入れ替わっていることを信じざるをえなかった。
「まさか本当に…」
「ユッコなら信じてくれると思ってた」
そう言って抱きついてきた園田先生の大きなバストが、私に圧迫感を与える。
「コホン… 人前で、ましてや先生の前ですることじゃないと思うけど」
二人は入れ替わった理由に思い当たる節が全くないのだが、入れ替わってしまった以上、元に戻るまでお互い生活を取り替えて過ごす必要がある。
そこで、どちらのことも知っている身近な人物として私へカミングアウトし、手助けしてもらおうということだ。
たしかに突然大人の女性になってしまったシンゴは右も左も分からない状態、かたや園田先生は男になったとはいえ、2回目の学生生活なので、シンゴほど苦労はしない。とはいえ交友関係などで困ることもあるだろう。
私は二人に同意し、手を差し伸べることにした。
日も落ち、外も暗くなってきたこともあって私たちは各々の家へ帰る。
シンゴは園田先生の家へ、園田先生はシンゴの家へ、私は私の家へ。
園田先生は一人暮らしのため、シンゴとしては身体の変化に対応できれば大丈夫だが、シンゴの家は両親と姉が同居しており、園田先生は家族にボロが出ないようにしなければならない。
二人の健闘を祈りつつ、私は二人をそれぞれの自宅へと送ってから帰路についた。
翌朝、早い時間に学校へ着くと、シンゴと園田先生は既にお互いの身だしなみチェックを始めていた。
男子高校生が女教師に化粧を施している姿に、私は昨日の出来事が夢ではなかったと現実に引き戻される。メイクを終え、元自分の髪をコテで巻いている園田先生が私に話しかける。
「水原さん、悪いんだけどピン持ってたら、貸してくれない?」
普段は前髪を下ろしている園田先生だが、視界に入って邪魔だと文句を垂れるシンゴの意見を汲んで、前髪をピンで止めてあげるという。
キッチリと斜めに分けられた前髪にふんわりとした長い髪、顔にはいつもの化粧がノり、喋らない限りどこからどう見ても園田ミホにしか思えない、美女が出来上がった。
「俺ってもしかしてかわいい…?」
「当たり前でしょ、アタシなんだから」
「そっかぁ、そうですよね。今は俺が園田先生なんだし、俺とか言っちゃいけませんよね」
「そのとおりよ。アナタは今、『アタシ』って言わなきゃいけないの。言葉遣いには気をつけてちょうだいね」
「わ、わかったワ。あ、あたしは園田ミホなのヨ。どう、可怪しくないカシラ?」
「もう少し自然にやってごらんなさい」
「あたしは園田ミホ、現代文を教えてるノ。うーん、なかなか上手くできる自信がないワ…」
「今のはなかなか良かったわよ。もう少し練習してみましょうか。じゃあ園田先生、彼氏はいるのかしらね?」
「彼女ならいるワヨ。あたし男子だモノ」
「ちょっとぉ!喋り方はいいけど、今度はアタシになってるってことを忘れてるじゃない!」
「あっ、ごめんなさいネ。あたし、彼氏はいないワヨ」
「そうそう、やればできるじゃない」
「園田先生、じゃなくて、杉本くんもできれば男の子っぽくしてくれないカシラ。なんだか自分がクネクネしてるのが見慣れなくって恥ずかしいワ…」
「たしかにアタシも変な目でみられないようにしないとマズいわよね。わかったわ、えっーと。オレ、杉本シンゴ。ユッコと付き合ってるけど、なんだか園田先生のことが気になってしょうがないんだ。こんな感じでどう?」
「す、すごいワ。でも、あたし園田先生にはあんまり興味ないワヨ?」
「このくらい当然よ。つーか、せっかくアタシみたいな美人になってるんだから、ちょっとは興味持ちなさいよね〜」
シンゴと園田先生が奇妙なやり取りを繰り広げている。
私は蚊帳の外だ。お手洗へと向かう私に二人は気づくこともなく、ちぐはぐなキャッチボールを続けていた。
◇
奇妙な出来事から1年。
私たちは卒業を迎え、それぞれの道を進んでいる。
あの後、シンゴと園田先生はときどきおかしな素振りを見せながらも、お互いのフリをこなしていった。
シンゴと別れた私も日常生活を取り戻す。
私にはシンゴがわからなくなってしまった。
お互いのフリを続ける二人の姿をみて、シンゴの姿をしているのが園田先生なのはわかる。しかし、園田先生に見えるのが本当にシンゴなのか自信がなくなったのだ。
自分で化粧をするようになり、オンナを強調しているかのような素振りをナチュラルにみせるなど、日に日に女性らしさを増す“園田ミホ”の姿に私は困惑し、憔悴していた。
私と別れた後、ほどなくして、園田先生、シンゴの両者とも付き合っている人ができたと耳にする。
相手が男子なのか、女子なのか、それすらも私は知らなかった。
興味がなかったわけではなく、知りたくなかっただけだ。
だが、色恋沙汰の噂は足が速い。
受験シーズンを終えた頃には、シンゴが園田先生の家に入り浸っているという話が私の耳にも届いた。
入れ替わっていることもあり、二人が密接な関係を築いているのは既知であったため、驚きも薄かったが、周囲からは園田先生が妊娠したという話も聞こえる。
たしかにお互いかけがえのない関係性になったのだ。その点だけをみれば二人が近づいていくのもわからなくはないかもしれない。
とはいえ、自分の顔に欲情などできるものなのだろうか。
私には理解し難かったが、火のないところに煙は立たない。
吹っ切れていたつもりの私は、モヤモヤとしたものを胸に抱いたまま、学び舎を後にした。
◇
大学からの帰り道、背後から私を呼ぶ声がする。
振り向くとベビーカーを押す夫婦の姿があった。
夫よりだいぶ年上であろう妻が、私のカバンから落ちたポーチを手渡してくれる。
「ありがとうございます」
御礼を言って、再び歩き出した私の背中に夫婦は言葉を続ける。
「この子の名前、ユウコにしたの」
涙と笑みが私の顔を崩す。
身体を、若さを奪われた彼が一番可哀想だと思っていた。
でも、それは違った。
独りだけ取り残されたのは私だ。
青春を奪われた私が一番不幸になっていたのだ。
今すぐに気持ちを切り替えなければいけないような気がする。
そのためにも、この場から一刻も早く離れたいという想いで走り出した私だったが、足取りはとても重い。
あの日終焉を告げた私の青春は既に呪いとなっていた。
家に着き、玄関を強く閉めた私の頭に良からぬ考えが過った。
17年後、私も36歳のときに若い子と入れ替わることで青春を取り戻してやればいい。
杉本シンゴよりイケメンな男子と入れ替わって、私自身を年上女房に迎える。
入れ替わる男子の彼女には悪いけど、私と同じ思いをしてもらう。
でも彼女も将来、私と同じことをすればいいだけ。延々と続く負のループは時代を超えて引き継がれていくの。
それしか私を浄化させる方法はない。
私のなかに巡る何かによって、次々と私の心は灰色へと染められていったーー
■終■
締切前日に思い立ってエントリーさせていただきました。
今回は、大人の女性教員と男子の入れ替わりを彼女目線を通した間接的な描写のみで書いてみましたが如何でしたでしょうか。性描写を一切入れていないうえ、独特な雰囲気で書いたこともあり、本企画にそぐっているか不安だったりもしますが、一人でも楽しんでいただける方がいましたら幸いです。
末筆となりましたが、この度は素敵な企画ありがとうございました。
TSFesの今後にも大いに期待しております。