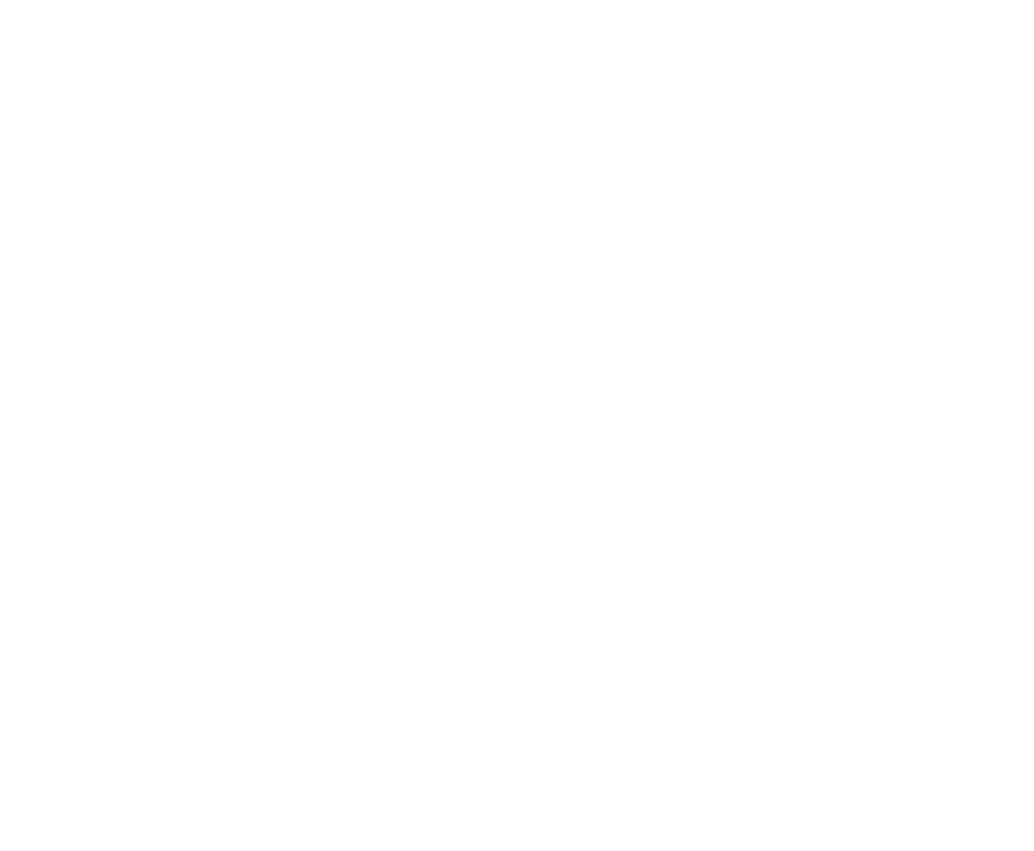今回は欲求不満な(元)人妻と性欲旺盛な男子高校生が入れ替わるお話です。久しぶりにイチャラブハッピーエンドを書いたらなかなか楽しかったです……!
燦々とした日差しが降り注ぐ初夏のとある土曜日。小綺麗なアパートの一室で取り込んだ洗濯物を丁寧に折りたたんでいる女性がいた。
「ふうっ・・・」
彼女は今里アケミ。今年で三十七歳になるはずの女性だが、その美貌には衰えというものを全く感じさせない。
元々やや童顔気味で昔からよく実年齢より若く見られる事に加え、くりくりとした大きな瞳やふっくらとした唇、綺麗な桜色をした頬とそれぞれが少女のそれを思わせるせいで余計に幼く見える。しかし目元にある一点の黒子が大人の女性らしい妖艶な魅力を放っており、それらが混じり合って独特の雰囲気を漂わせていた。
だがそれとは対照的に身体の方はしっかりと年齢を反映している。小ぶりなスイカと見紛うほどの大きさを誇る胸は重ねた時のせいでややハリを失って垂れ、お腹周りやお尻、太ももなどはむっちりとした柔らかな脂肪が必要以上に付いてしまっている。今はまだギリギリぽっちゃりとも言えない程度の体形ではあるものの、この調子だと近いうちに服装では誤魔化しきれないほどムチムチの肉が全身に付いてしまう事は容易に想像出来た。しかしこのだらしないとも言える身体は美しい顔と合わせると思わず生唾を飲み込んでしまうほどの極上の魅力を放っており、普段彼女が好んで着ているシルエットの見えづらいゆったりとした服越しであっても同じアパートですれ違った男性はほぼ全員アケミの淫らな姿を思い浮かべずにはいられないほどだった。
腰まで伸ばされた明るい茶色の髪は緩くウェーブがかかっており、その艶めきは一目見るだけで丁寧に手入れをされているのだと分かる。普段は家事の邪魔にならないよう首元で一つにまとめる事が多いが、どんなヘアアレンジでも似合うだろう。
性格はやや内気な面があるものの穏やかそのもので、滅多に怒る事もなく人当たりも良い。実際、近所の住人とはトラブルなど一切起こした事が無いどころかとても良好な関係を築いていた。
今はこのアパートで一人暮らしをしているが、綺麗に着飾って婚活なり何なりをすればあっという間に相手が見つかるほどの美貌と内面を携えている。だがそうしないのはアケミに一つのトラウマがあるからだった。
(ブラ、またキツくなってきちゃったわね・・・やっぱり毎日シているせいなのかしら?我慢しないといけないのは分かってるけど、『あの人』のせいで・・・)
わざわざ海外から取り寄せなければならないほど巨大な黒のセクシーなデザインのブラジャーを見ながらため息をつく。
実は、アケミは既に離婚を経験している。元々結婚に興味はなかったが、結婚適齢期の二十代半ばに友人の勧めもあり、婚活を始めた。
その魅力的な容姿と包容力のある性格であっという間に相手が見つかり、めでたくゴールイン。しばらくは順風満帆な結婚生活を送っていたものの、三十歳を過ぎた辺りで度々夫から暴力を振るわれるようになってしまったのだ。加えて性欲の強い彼は毎日のようにアケミに夜の供を強引にさせ、彼女の身体を徹底的に開発した。
勇気を振り絞って夫のDVを告発し、多額の慰謝料を貰って離婚した今でもそれは元に戻るはずがなく、毎夜のように自分を慰めてしまう日々が続いている。そのせいで身体はムチムチとどんどん女性らしさを増していき、胸やお尻などは特に大きく育ってしまった。さらにその成長は留まる事を知らず、最近でも度々下着を買い替えなければならないほどだ。気に入ったデザインも身体に合うサイズもなく、肩にずっしりと負担をかけてくる胸を何度も忌々しく思ったが、自分の身体なのでこの先一生付き合っていかなければならないのだともはや諦めている。だが、苦い過去と共に重苦しいため息をついてしまうのは仕方のない事だった。
「っ、こんな暗い気持ちじゃいけないわね。どんよりしてても仕方ないわ!」
胸の内を覆う雨雲のように鈍重な気持ちを吹き飛ばすように勢いよく立ち上がる。だが、常日頃から運動不足を自覚するほどに動かしていない身体を急激に動かしてしまっては節々が悲鳴を上げないはずもなく。
「いたっ、いたたたた・・・そうだったわ、最近は腰も痛いのよね・・・」
ズキズキと鈍い痛みを返してくる腰を優しくさすりながら顔を歪める。元夫から貰った慰謝料はかなりの高額に上るが、それだけでは当然生きていけないのでパートで生活費のやり繰りをしている。だが数か月前に重い段ボール箱を無理に持ったせいか腰を痛めてしまい、以来些細なきっかけで痛むようになってしまった。肩こりや増え続ける体重に加え、腰痛まで感じるようになってしまっては否が応でも年齢を自覚させられてしまう。振り払ったはずの暗い気持ちに再び覆われてため息をつきながら夕飯の材料の買い出しに行くべく冷蔵庫の中身を確かめ始めた。
***
買い物メモを手に自室のカギを閉める。財布もエコバッグの中に入れ、準備は万端だ。
アケミの部屋はアパートの五階にあるのでいつもはエレベーターを使って上り下りしているのだが、ふと階段が目に入る。
「・・・うん、たまには階段で行こうかしら」
脳裏をよぎるのは先ほどの苦い思い。健康のためにも日々の運動はすべきかもしれないと思い、ついエレベーターのボタンに伸びていた手を止めて階段の方へと足を向ける。
「うーん・・・そうだわ!せっかくだし少し走っていきましょう」
どうせなら、と階段を駆け下りる事に決める。ただ日頃の運動不足に加えて今は白いトップスに茶色のロングスカートとお世辞にも運動に適した恰好とは言えないのであまり全力は出さずに小走りにはなるが。
ゆっくりと深呼吸をして息を整え、踏み外しても大丈夫なように手すりに手を添えて一気に階段を駆け下りる。くるくると勢いよく回る景色に振り回されながらも何とか一階まで辿り着くとそれだけで息が上がってしまった。
「はぁ、はぁ、はぁっ・・・こ、こんなに体力が落ちてたのね・・・」
全力では無かったとはいえ階段を駆け下りるだけで膝に手を付いてしまうほどに衰えている自分の体力に驚く。それどころか全身からは汗が吹き出し、じっとりとした不快感が纏わりついてくる。元々汗っかきな体質ではあったものの、年齢を重ねる毎にそれがさらに酷くなっているような気がしてならない。ここまで体力が低下していた事に加え、たったこれだけの運動で汗だくになってしまった事に恥じ入ってしばらくその場で立ち尽くしていると風に乗って威勢の良い掛け声が聞こえてきた。
「あら?この声は・・・」
よくよく耳を澄ませてみるとどうやら学校の野球部の声らしい。アケミの住むアパートの近くには高校があり、時折そこから声が聞こえてくる事がある。そういえばその高校の野球部が今年念願の甲子園出場を果たしたとどこかで耳にした事を思い出し、それならばこの気合の入った声も頷ける、と顔をほころばせた。
「ふふ、若い子たちって良いわね・・・」
ざあっ、と身体中を心地よく駆け抜ける風と野球部の声に元気を貰い、エコバッグを肩にかけるとしっかりとした足取りで近所のスーパーへと歩き出した。
***
アケミのアパートから程近い場所にある高校のグラウンド。威勢の良い掛け声で満たされていた基礎練習の時間とは違い、今やピリピリと張り詰めた空気が漂っていた。
「うわ、すっごい緊張感・・・!ね、ねぇ、これただの練習試合なんだよね?」
「しっ!あんまり大きな声出しちゃ駄目だよ!甲子園に向けて本気のレギュラー争いしてるんだから・・・!」
グラウンドの金網の外では女子生徒二人がひそひそと声を抑えて試合を見学している。向かい合っているバッターとピッチャーの間にはもはや殺気とも言うべき異様な雰囲気が漂っており、思わず生唾を飲み込んで魅入ってしまうほどだ。
ゆるり、と緩慢な動作でピッチャーが振りかぶり、居合のように白球を握りしめた右腕が閃き――スパァン!という轟音がグラウンドへと響き渡った。
「ットライィーク!バッターアウッ!ゲェェームセッ!」
バッターは全く反応出来なかったのか、はたまたそんな自分に恥じ入っているのかバットを構えたまま動かない。審判を務める監督もその球速と圧倒的な光景に興奮しているのか試合終了を告げる声に力が籠っていた。
まもなくしてそれぞれのチームが一列に並んで向かい合い、帽子を取って礼を言う。そのまま二つのチームの間、先頭より前に立っていた監督の方を向くと彼が口を開いた。
「よし、みんなよくやったな。これまでの練習と今日の試合結果を踏まえて、甲子園のレギュラーを決定する。ただし勝敗だけで決めるつもりはないから、勝った奴も油断しないように。以上!」
「「「ありがとうございました!!」」」
再びの礼。そこでようやく二つのチームは『試合相手』から『同じチームの仲間』になり、各自適当な相手を見つけて個別に反省会を開く。自分はああ動くべきだった、お前のあれは良かったなど、互いに反省点や良いところを指摘し合って今日の試合を確実に己の経験値として身に付けていった。
そんな彼らのうち、先ほど剛速球で試合の幕を引いたピッチャーへと監督自ら声をかけにいく。
「北島!今日も良いピッチングだったぞ!流石はうちのエース。甲子園に向かって気合が入っているな!」
「ありがとうございます!」
晴れやかな笑顔で監督に頭を下げるのは北島タクミ。野球部部長にしてエースピッチャーであり、万年地方大会準優勝に甘んじてきたこの学校を悲願の甲子園にまで引き上げた立役者だった。
野球部と言えば髪型は五厘刈りをイメージしがちだが、近年ではその慣習から脱却しようという流れもある。彼もその例に倣い、五厘刈りでこそないものの黒い髪をさっぱりとしたスポーツマンらしい短髪に仕上げている。顔立ちはイケメンと形容するのがピッタリなほど整っており、普段の柔和な顔立ちからは想像出来ないほど鋭くなる試合中の眼光に心を奪われる女子が大勢いるような状況だった。
パッと見でこそ身体は細く見えるもののユニフォームの下には日々の練習で驚くほど鍛え上げられた筋肉をまとっており、同じ男子が憧れて時折触りに来るほど。最大の武器である剛速球を生み出す腕はもとより、下半身もしっかりと強化していて余念がない。
性格も部長とエースという立場を笠に着る事は一切なく、誰にでも気さくに話してすぐに打ち解けられるおかげでクラス内でも部内でも慕われている、まさに理想的な人物だ。
小学校から野球を続けており、タクミ自身が真面目に練習に打ち込む事に加えて才覚もあったおかげで高校に入って以降も一年生からレギュラー入りしているほどの実力者だ。しかし甲子園への壁は厚く、一昨年、去年とあと一歩のところで逃していた。しかし今年が最後という事で獅子奮迅の活躍をし、見事夢の舞台の切符を手に入れたのだった。それを思えば、声をかけてきた監督の上機嫌さも分かるというものだ。
「地方大会万年二位だったこの学校が甲子園まで漕ぎ着けたのは間違いなくお前の実力のおかげだ。全部が全部お前にかかってるなんて情けない事を言うつもりはないが・・・期待してるぞ」
「はい!頑張ります!」
監督の期待の強さを表すように肩を力強く掴まれ、それに応えるようにはっきりと目を見据えて答えを返す。それに満足したかのように監督は離れると部員一人一人にアドバイスと激励をかけていった。
***
練習後の反省会とストレッチも終わり、着替えを終えて更衣室を出るタクミ。そこには先ほど練習試合を見学していた女子生徒二人が待ち構えていた。
と、その片方――髪を肩の辺りまで伸ばしたセミロングの大人しそうな女子生徒が顔を赤らめてタクミに声をかける。
「あ、あのっ、北島先輩!練習お疲れ様です!わ、私っ、二年の花崎っていいます!」
「あぁ、ありがとう。それで、俺に何か用かな?」
「ええと、そのっ、ここ、これを渡したくて!どうぞっ!い、いらなかったら捨てて貰って全然大丈夫なので!」
バッ、と腰を九十度折り曲げて差し出してきたのは綺麗にラッピングされた包み。それを受け取り、許可を貰って開けてみると中から出てきたのは吸水性と肌触りが良いと評判のスポーツタオルだった。
「うわっ、これ結構良いところのタオルじゃん!いいの?貰っちゃって」
「はいっ!私、先輩が練習とか試合とかずっと頑張ってる姿に勝手に元気貰ってて・・・少しでもお礼がしたいなって思ってたんです。その・・・迷惑、でしたか?」
「全然!むしろめちゃくちゃ嬉しいよ。今使ってるヤツがそろそろダメになってきたからちょうど買い換えようかと思ってたんだ。こんないいもの貰えるなんて・・・マジで嬉しいよ」
「あ、ありがとうございま・・・うっ、うえぇぇぇ~ん・・・」
お礼を言いながら女子生徒の目にはじわりと涙が浮かび、間もなくして泣き出してしまった。何か失礼な事をしたのか、とタクミが困惑していると成り行きを見守っていたもう一人の女子生徒が泣き出した彼女を抱きしめて代わりにタクミに謝罪する。
「すみません先輩。この子、先輩に受け取って貰えた事がよっぽど嬉しかったみたいで・・・ちょっと話せそうもないし、これで失礼しますね」
「わ、分かった。・・・花崎さん、本当にありがとう。これ、甲子園で使わせて貰うね。」
「あ゛、あ゛りがどうございまずぅ・・・」
「あーよしよし。ほら、行くよ?」
最後にもう一度礼を言うタクミにまた感涙したのか抱きしめてくれている女子生徒の胸元に顔を埋めながらも再びお礼を言う花崎。あやすように頭を撫でられながら、二人はゆっくりとタクミのもとを去って行った。
「ふぅ・・・俺も帰るか」
手にしたタオルを丁寧に畳んでカバンに入れるとタクミも家に向かって歩き出す。その途中で頭を巡るのはやはり先ほどの出来事だった。
(しっかし、さっきのはドキドキしたな・・・告白かと思った)
表面上では平静を装っていたものの、内心ではかなりドキドキとしていた。甲子園を控える野球部のエースである前にタクミも立派な一人の男子高校生なのだ。恋をしたり彼女を作ったりとそういう甘酸っぱい青春に憧れが全く無いと言えば嘘になる。なるのだが。
(甲子園前に彼女作るとか、やっぱりそういうの駄目だよなぁ・・・万が一それでメンタルやられたら皆にも申し訳ないし・・・)
タクミにとって今最も大事なのは野球だ。なればこそ、それを揺るがすような行動は極力取りたくない。それでも憧れだけは止められなかった。
「あー・・・彼女欲しい・・・」
誰にともなく呟いた声は昼下がりの空に吸い込まれて消えていった。
***
甲子園へ向けての調整のためか軽めに終わった練習のおかげで体力が有り余り、帰ってからも何かトレーニングをしようか、と考えながらタクミは帰り道をぼんやりと歩く。
と、道の正面から一人の女性が息を切らせながら歩いてきていた。一目で美人だ、と分かるほどに整った顔は疲労で歪み、白いトップスは既に汗でビショビショに濡れている。おまけに熱中症というほどではないにせよ足取りもどこかフラフラとしており、手にしている満載のエコバッグを今にも落としそうだ。
そんな彼女にタクミは迷う事なく声をかける。
「こんにちは!」
「ふぅ、はぁ・・・こ、こんにちは。何かご用かしら?」
返事をするのもやっと、という体で何とか挨拶を返したのはアケミだった。唐突に話しかけてきた男性――タクミにやや困惑したものの、明らかに善意と分かる笑顔にぎこちないながらも笑顔を返す。
「すみません、急に話しかけて・・・こんな暑い日にフラフラしてたのでちょっと心配になっちゃって。もし良かったら荷物持ちましょうか?」
「だっ、大丈夫よ。セールだからって調子に乗って買い込みすぎた私が悪いんだし、こんな重い荷物を押し付けるわけにもいかないわ」
「でもここから一番近い住宅街まででも結構距離ありますし、万が一倒れたら大変ですって。熱中症って本当に怖いんですよ?」
「で、でも・・・」
アケミの本音としては、この申し出はとてもありがたい。しかしやはり見ず知らずの、しかも若い男の子にこんな事を任せるのは申し訳ない。だが、心の底からアケミを心配しているタクミの真剣そのものの視線にとうとう折れてしまった。
「・・・わ、分かったわ。申し訳ないけど、お願いしちゃおうかしら」
「任せてください!じゃあ、それをこっちに」
「えぇ。あっ、重いから気を付けて・・・!」
「大丈夫です!俺、野球部で鍛えてますから!」
アケミから受け取ったエコバッグを軽々と持ち上げるばかりか、ウェイトトレーニングのように軽く上下させるタクミ。そんな彼の様子にアケミは一瞬見惚れてしまう。
(やっぱり若いって良いわね・・・ちょっと羨ましくなっちゃうわ)
自分があれほど苦労して持ち運んでいたエコバッグをいとも簡単に持ち上げた姿にほんの少し憧れてしまう。無論自分があの年代であってもここまで楽に持ち上げてはいないだろうが、それでもあの力強さに惹かれてしまうのも無理はない。最初こそタクミに申し訳なさがあったものの、軽々と持ち上げる様子に安心したのかそのまま任せて彼と一緒に自宅へと歩き出した。
***
「へぇー!あの高校の野球部さんだったのね・・・!しかもエースだなんて・・・本当にすごいわ」
「いやぁ、それほどでも・・・へへへ」
十分後、疲労したアケミのペースに合わせてゆっくり歩きながら会話していく中であっさりと打ち解け、軽くお互いの事を話すまでになっていた。アケミが高校近くのアパートに住んでいる事、タクミがそこの野球部である事、今年悲願の甲子園出場を果たした事などなど、テンポよく会話が弾む。そうこうしているうちにあっという間にアケミのアパートへと辿り着いた。
「ありがとう、すっごく助かったわ。あとは一人でも大丈夫そう」
「いえいえ、せっかくなら最後まで運びますよ!階段も大変でしょうし」
「そう?じゃあ・・・お願いしようかしら」
アケミは少しだけ逡巡したものの、この短い時間の会話だけでもタクミがとても優しい人柄だという事はよく分かっていたのでそのまま言葉に甘える事にする。
だが、アケミの部屋へ向かう階段を昇っている時の事だった。
「きゃっ・・・?!」
炎天下に普段あまり動かさない脚を酷使してしまった影響だろうか。力が上手く入らず、ぐらりと階段を踏み外してしまった。
バランスが崩れ、真っ逆さまに落ちていく景色。いや、落ちているのは自分か、と加速している思考の中で呑気さにも似た諦めの境地で見送っているとそれを許そうとしない意思が込められた腕が伸びてきた。
「アケミさんっっ!!」
必死の形相でこちらに手を伸ばして抗うタクミ。その願いが通じ、アケミの手を取った――までは良かったが、お互いあまりに不自然な体勢だったせいで支える事など当然出来ず、二人でもつれ合うようにして階段を転がり落ちてしまった。
***
「いてて・・・」
ずきずきと全身に響く痛みの不快感で目を覚ます。額が特に痛みと熱を持っており、どうやら強くぶつけたせいで気を失っていたらしい。と、そこまで思い至ったところで直前の光景を思い出した。
アケミが階段から転落した事。
それを受け止めようとした事。
だが失敗してしまい自分ごと落ちてしまった事。
せめてアケミに怪我がないよう自分がクッションになろうとした事――
「そうだっ、アケミさんは・・・!」
自分の方は痛みこそあるものの特に異常はない。ならばアケミの方はどうなったのだろうか、と『綺麗なソプラノ声で』叫びながら身体を起こした。
「へ・・・?」
その瞬間、目に入った光景に凍り付く。
野球の邪魔にならないよう短く整えた黒髪。
整っている方ではあるがもう少し男らしい迫力が欲しいと思っていた顔つき。
雑に扱うせいで少しシワのある高校の制服。
目の前にいるのは間違いなく北島タクミだった。
「こっ、これ、どうなって・・・!」
しかも自分の方も様子がおかしい。喉から漏れる声は「困惑している」というだけでは説明が付かないほど細く高くなっているし、視界の端で揺れている明るい茶色の束は間違いなく髪の毛だ。何より胸元にはまるで重いボールを詰め込んだかのようにずっしりとした球体が二つも揺れている。
信じたくはないが、この状況を説明できる現象が一つだけ存在する。
「うっ、うぅ、ん・・・?」
と、目の前のタクミも目を覚ます。ぼんやりとした視界が徐々に鮮明になってきたのか、はっきりと目が合い――まるで信じられないものを見たかのような表情になった。
「う、嘘・・・なんで『私』がそこに・・・?」
まるで女性のように口元に手を当てて、女性のような口調で呟く。その仕草と言葉でアケミは――『タクミ』は自分の突飛な想像が間違っていなかった事を突き付けられた。
「俺たち、入れ替わってる・・・!!」
***
一先ずアパートの階段では落ち着いて話も出来ないだろう、という事で散らばってしまった荷物を二人で拾い集め、アケミの部屋へ行く事に。少し動いただけだというのに身体中に強烈な違和感が走り、改めて他人の身体になってしまったのだと自覚させられた。
アケミの部屋に入り、慣れた手つきでタクミが冷えた麦茶を用意するとお互いに一息つく。どう話を切り出していいものかとタクミが思案しているとアケミの方が恐る恐るといった様子で口を開いた。
「その、改めて確認なんですけど・・・俺の身体になってるのって、アケミさん・・・ですよね?」
「え、えぇ。逆に私の身体になってるのはタクミくんね・・・?」
「やっぱり、俺たちの身体が入れ替わっちゃってますね・・・」
はぁ、と二人で重苦しいため息を吐く。入れ替わりという非現実的な事が起こったのみならず、まさか自分たちが経験するとは思ってもみなかった。今もそうだが、この先の事を考えると暗い気持ちになってしまうのは当然の話だ。
「そうだっ、もう一回同じ事をやってみれば元に戻るんじゃないですか?そうすればきっと・・・!」
「良い案だと思うけれど・・・駄目だと思うわ。あの時は奇跡的に二人とも軽い怪我で済んだけれど、あんな危険な落ち方をもう一回すれば無事でいられる保証も無いのよ?・・・そ、それに・・・私は、その・・・ちょっと、太ってる、し・・・きっと元に戻れてもタクミくんに大怪我させちゃうわ」
「す、すみません・・・」
自覚はあれども流石に恥ずかしいのか、『太っている』の部分が極端に小さくなりながらもタクミはアケミの提案を却下する。自身の無謀な提案と恥ずかしい事を言わせてしまった申し訳なさでアケミはバツが悪そうに謝罪した。
その後もどうやって元に戻るか、医者にかかるべきじゃないか、そもそもこんな話を信じて貰えるのか――などの議論が続き、最終的には元に戻れる方法が見つかるまでしばらくお互いのフリをして生活する事になった。
「私は一人暮らしだからあんまり人と関わる事はないし、そんなに心配しなくても大丈夫だと思うけれど・・・タクミくんはご家族さんと暮らしてるのよね?それに学校のお友達とか、部活の子とか・・・バレないためにも色々教えてくれると助かるわ」
「・・・・・・」
「タクミくん?」
「へっ?!あっ、あぁ、人間関係ですね!?その、俺ちょっと友達多いんで大変かもしれないんですけど・・・」
「だ、大丈夫。頑張るわ」
話し合いの最中だというのにアケミはどこか上の空といった様子でタクミの話をやや聞き流してしまったらしい。その理由は『アケミ』本人には何となく察しがついていた。
(や、やっぱり汗臭いって思われてるわよね・・・最近自分でも気になる時があるし・・・うぅ~・・・・!あんなオバサンの身体にさせちゃって・・・本当に申し訳ないわ)
交友関係の話を聞きながらも内心でタクミは恥ずかしさと申し訳なさに必死に耐える。
事実、『タクミ』の身体になってからというもの正直アケミの体臭が気になる瞬間が時折ある。恐らくそれが気になって話に集中出来ていないのだろうと思っていた。
だがその予想は全くの的外れで。
(うぅ・・・!む、胸が・・・胸が気になって集中出来ない・・・!)
アケミの感心は『男として』当然というか、胸元の巨大な二つの塊に向いていた。
ほんの少し身じろぎするだけでもゆさっ♡と敏感に反応を返すほどに柔らかく、まるで限界近くまで投球をした後のようにずっしりとした重量が常に肩にかかり続けている。「ただそこにあるだけ」というにも関わらずその存在を声高に主張してくる魅惑の果実に心を揺さぶられっぱなしだった。加えて、谷間にもたっぷりと汗を掻いていて不快感こそあるものの、そこから立ち上ってくる臭いはむしろずっと嗅いでいたくなるほどの不可思議な魅力を放っている。練習後の野球部の更衣室では常に部員たちの汗臭さが充満していて顔をしかめる事も多かったが、それとはもはや別種の臭いだ。
微妙にぎこちない空気が漂う中でも何とか情報の交換を終えて最後に連絡先だけ交換し、一先ずはそれぞれの家へ『帰る』事にしたのだった。
***
「ふぅっ・・・」
タクミを見送り、自宅になってしまった部屋で一人ため息をつくアケミ。色々手ほどきを受けたとはいえ唐突な一人暮らし、しかも他人の――年上の異性の身体で過ごさなければならないという事がさらに不安に拍車をかけていた。
「っ、あぁもう!じっとしてたらもっとモヤモヤする!とりあえず、部屋を見て回ろ・・・」
じわ、と胸中に忍び寄ってくる不安を誤魔化すように与えられた部屋を色々と散策してみる。そのどれもが丁寧に掃除されており、それだけでも『アケミ』の人柄が伺い知れるというものだ。
とはいえさほど部屋数があるわけでもなく、あっという間に最後の部屋まで辿り着く。
「ここが寝室、か・・・うわ、なんかすごい罪悪感・・・」
寝室とはいわば私室であり、その人の内面が最も出やすい部屋でもある。その例に漏れずここもアケミの考えがどこよりも強く出ていた。
落ち着いたモカブラウンの家具を基調にハーバリウムや可愛らしい雑貨の類が配置され、シンプルながらも落ち着ける空間になっている。小物も目を引くとはいえ多すぎず少なすぎずバランスよく置かれている辺り『アケミ』のセンスの良さが伺い知れた。
これからしばらくはここを使う事になるとはいえ、女性のプライベートな空間に立ち入っているという事実でドキドキと鼓動が加速していく。
と、突然部屋の主である『アケミ』の姿が視界に飛び込んできた。
「うわっ?!すす、すみません無遠慮に見ちゃって!・・・ってなんだ、鏡か・・・」
アケミが反射的に謝ってしまったのは部屋に置いてあった姿見に映った鏡像。ひとまず本人で無かった事に安堵したものの、鏡に映るのが見慣れた自分の顔ではない事に奇妙な感覚になり、まじまじと覗き込む。
「やっぱり・・・俺が女の人に・・・『アケミさん』になってるんだよな」
ぷにっ、と無意識で触れた頬が柔らかい感触を返し、口から出た声も自分のものとは似ても似つかない高く丸みを帯びた声。何より鏡に映る女性の顔に改めて別人になってしまった事を突き付けられた。
少し視線を落とせば胸や腰回り、太ももが脂肪に覆われたむちむちの熟れた身体があり、部活の厳しい練習で鍛え上げた筋肉の鎧など一欠片も残っていない。これでは自慢だった剛速球を発揮できないばかりか腕立て伏せの一回も出来るか怪しく、正直落胆の色を隠せない。事実、入れ替わる前は軽々と持ち上げられていたアケミのエコバッグも重くて持つのも一苦労になり、ここへ運んでくる時もタクミの身体を使っている『アケミ』に頼んでしまったほどだった。
しかしそんなものが霞んでしまうほどにアケミの感情を惹き付けてやまない部位が一つ。
「あ、改めて見てもデカい、よな・・・」
それは胸元で重々しく揺れる二つの大きな塊――おっぱい。
下を向けば実に視界の半分を塞いでしまうほどに大きく、足はおろかつま先すら見えない。試しにその場で軽く跳んでみると、どゆんっ♡だぷんっ♡と激しく暴れ、肩へ凄まじい圧をかけてくる。
「う、うわ、重っ・・・?!」
恐る恐る両手ですくうように持ち上げてみるとずっしりとした途轍もない重量が手に伝わり戦慄してしまう。ふと脳裏に「重いし、肩は凝るし、大きすぎるお尻も合わせてちょっと屈んだだけでもバランスを崩しやすいから気を付けてね」というタクミの言葉が蘇り、その言葉が冗談でもなんでも無い事を思い知らされた。確かに、こんなものを胸にぶら下げていたら生活するだけでも一苦労だろう。
と、ふと手に乗っている胸の形が球体から楕円形に崩れている事に気が付く。年齢のせいでハリを失いつつあるが逆にそれが重量感を増しており、手のひらに吸い付くように乗っていたのだが、それを見た瞬間アケミの中で何かが火を灯した。
(えっ、えっろ・・・!おっ、おっぱいってこんなに形が崩れるものなんだ・・・!?)
まるで幼い頃遊んだスライムのように形が変わっている胸に思わず性欲が反応してしまう。
『タクミ』とて一人の健全な男子高校生。その手の話題には当然興味津々だし、十八歳の誕生日を迎えたその日にインターネットでアダルトビデオを購入した。人生初の生々しいエロを食い入るように鑑賞して何度も何度も見返したが、それですら今のこの興奮には及ばない。破裂しそうなほどの勢いで鼓動する心臓を手のひらで感じながらも、目の前のおっぱいに思考全てを奪われているためどこか他人事にすら思えた。
さらにアケミの身体は元々強い性欲を秘めていた上に元夫の徹底的な開発によって少しの興奮でも全身が火照ってしまうほどの淫乱な身体に仕上がっている。
男子高校生の旺盛な性欲を持つ魂に、元人妻の秘めた性欲と開発済みの熟れた身体。それらが上手く混ざり合ってしまった結果、理性や罪悪感などは簡単に吹き飛んでしまった。
「んっ・・・?!♡♡」
たった一揉み。ほんの少し指を沈み込ませただけだというのに背筋にゾクッと言い様もない衝撃が走り、脳を伝って全身へと伝播していった。一度味わってしまった異性の快感の味はアケミを深く魅了し、引き返すという選択肢を一瞬にして排除してしまう。
「んっ♡♡やぁ、んっ?!♡♡はっ♡♡はあっ♡♡」
開いた口の端から銀色の光が零れている事すら自覚せず、一心不乱に揉む、揉む、揉む。手のひらに伝わる極上の柔らかさは元より、乱暴な手つきで揉まれる胸からも全てを蕩けさせるような快感が生み出される。野球部の練習でボロボロになった手とは正反対の細くしなやかで美しい指が肉鞠を揉み、潰し、こね、掴み、弄ぶ。その光景だけでも十二分に淫靡な上に揉んだ分だけ快感が走るとなると、手が、指が、身体が止まってくれるはずもなかった。
「はっ♡♡はひっ♡♡はっ♡♡はあっ♡♡」
もはや獣のような呼吸になりながら飽きもせずただひたすらに揉み続ける。男では決して味わえなかったはずの快楽を味わっている優越感と背徳感が脳内麻薬をこれ以上なく分泌し、興奮を極限まで引き上げていった。
「はぁっ♡♡はぁっ♡♡はぁっ・・・♡♡・・・ん?」
意識にぼんやりと霞がかかり全身から噴き出すように汗が流れ出てきた頃、ふと股間に気持ち悪い感触を覚える。ずっと昔はよく味わっていたはずなのに、いつしか忘れてしまったその感触。無意識で内腿を擦り合わせると太もも同士が押し潰されながら擦れる感触に驚いたが、それ以上にヌチャッ、というベトベトの感覚が返ってきて、まさかこの年で――しかも他人の身体でお漏らしをしてしまったのかと慌ててロングスカートをたくし上げた。
「うわっ・・・♡♡」
幸いと言うべきか尿特有のキツいアンモニア臭は一切感じられなかったので漏らしてはいなかったものの、当初の目的が一瞬で吹っ飛んでしまうほどの光景が目の前に広がった。股間の気持ち悪い感触はどうやら尿以外の水分が分泌されていたようで、そのせいでスケスケのレース地で編まれた黒いセクシーショーツがぴったりと股間に張り付いて女性器の形をはっきりと写し取っている。よくよく見るとその側面からは黒々とした毛がはみ出しており、その中では未処理の陰毛が密林を形成しているであろう事は手に取るように分かってしまった。
先ほどベトベトの感触を返してきた太ももは股間から現在進行形で垂れている粘度の高い液体で汚れており、床まで到達するのも時間の問題だろう。さらにそこからはむせ返るような淫臭が漂っていて、それがロングスカートに留まっていたのを一気にたくし上げて解放してしまったせいで鼻から侵入して脳髄まで犯し、クラクラと思考を惑わせていた。
何より、そんな極上の肢体を持つ熟れた身体の美女がみっともないほどのガニ股を開いて己のスカートをたくし上げているという凄まじい光景のせいで、あらゆる要素がより淫乱さを強調されていた。
(もう股間が・・・おまんこがビショビショだ・・・確か女の人って興奮すると愛液っていうのが出るんだっけ・・・?じゃあ、アケミさんの身体もここまで興奮してるって事だよな・・・)
上気した頬に火照った全身、愛液がトロトロと溢れて止まらない秘部。自分も含め、『興奮している』という事を認識した瞬間、まるで導かれるように股間へ手を添えていた。
「ひゃっ?!♡♡」
ショーツ越しに秘部へ触れ、くちゅっ♡と水音が鳴るよりも早く身体が勝手に跳ねる。たった一瞬の接触でさえも開発済みの女体は男とは比べ物にならない快感を生み出し、一瞬にして理性を蒸発させてしまった。
「お゛っ♡♡ん゛おっ?!♡♡」
まるでそうする事が当たり前かのように指を二本、秘部へと突き入れる。何年にも渡って男のモノや自身の指、時には無機物を受け入れてきたアケミの膣はあっさりと指を根本まで飲み込み、膨大な快楽を生み出して思考を甘く蕩けさせていった。
ただ入れるだけでも潰れたカエルのように下品な声が喉から漏れ、視界にパチパチと白い火花が散る。これ以上進むと戻れなくなる、とどこか遠いところで誰かが警告してきたような気もしたが、それすら飲み込まんとする『もっと欲しい』という本能の声が全てを押し流していった。
「お゛ほぉっ!?♡♡♡んお゛っ♡♡♡お゛っ♡♡♡」
ぐちゅぐちゅぐちゅぐちゅ、と狂ったように指を突き入れては抜き、突き入れては抜き、膣内を本能の赴くままに掻き回す。洪水のように溢れ出た愛液は意思を持っているかのように指へと絡み付き、その動きをさらに早く滑らかなものにしていった。
(たり、ないっ・・・♡♡♡もっと、もっとぉっ・・・!♡♡♡)
たった数十秒後には二本の指では物足りなくなり、三本目の指を入れてさらに動きを激しくしていく。
快楽で潤んだ視界では誰もが目を惹かれるような妖艶な美女が蕩けた顔と下品なガニ股で必死に股間を掻き回している姿が映り、そこから溢れ出る愛液と全身の汗の臭いは嗅覚を麻痺させてしまうほどに濃くキツい。部屋中に響くような湿っぽい肉音はそれよりも大きい下品極まる喘ぎ声にかき消されて微かに響くだけだった。
何より股間から脳へ、脳から全身へと走り続ける快感は思考も理性も押し流し、ただただ肉体の求めるまま身体を動かすよう命令しているかの如く強い。このまま快楽漬けになってしまえば二度と元には戻れないだろうと確信するほどだった。
顔も、声も、身体も、快感も、全て他人の――女性のものになってしまった背徳感と倒錯感。本来ならば一生味わえないはずのそれを今自分はこれ以上なく堪能しているのだ、と自覚した瞬間、急激に快感のボルテージが上がり――
「イ゛ぐっ!♡♡♡イ゛ぐイ゛ぐイ゛ぐっ♡♡♡イ゛っちゃうぅっ?!♡♡♡♡♡♡」
身体に教え込まれた反射か、汚い喘ぎ混じりの声で絶頂を宣言する。折れてしまうのではないかというほど深く背を反らし、ガクガクと足を震わせ、ショーツ越しにも関わらず愛液をブシャアッ!と撒き散らす。清楚な見た目からは想像もつかないほどの下品な絶頂だったが、アケミ本人には気にする余裕など一切なかった。
盛大な絶頂の後、まるで糸が切れてしまったかのように仰向けで倒れ、強かに背中をぶつける。その顔は全力疾走した後のように多大な疲労で歪み、呼吸も危ういほどに乱れていた。
「ひゅーっ・・・♡♡ひゅーっ・・・♡♡」
(これ、が・・・女の人のオナニー・・・♡♡こ、こんなの知ったら戻れなくなるっ・・・♡♡もっと、もっとシたい・・・!♡♡)
もっと、という身体の声にしたがって腕を股間に這わせようとするが、ぷるぷるぷる、と快楽の余韻か、はたまた極度の疲労か、手が震えて上手く動かせない。それどころか持ち上げる事さえも億劫でとうとう諦めてしまった。
「はぁ、はぁ、はぁっ・・・♡♡」
(あ、アケミさんの身体、全然体力無いんだな・・・身体が重い・・・元の俺の身体だとまだまだいけそうなのに・・・!)
キツい練習でクタクタになった事を思い出しながら、ゆっくりと呼吸をしつつ全身を巡るふわふわとした余韻に浸る。改めて体力の有り余っている『野球部の男子高校生』からすぐに息が切れてしまう『運動不足の元人妻』になってしまった事を痛感した。
たっぷり十分以上かけて息を整え、億劫さを投げ飛ばすように勢いよく身体を起こす。すると当然のように胸元ではおっぱいがどゆんっ♡と跳ね回り、全身から汗臭さとメスの臭いがミックスされた事後のような淫靡な香りが辺りに広がった。
「っ・・・!♡♡」
その感覚と臭いに収まったはずのアケミの性欲が再び刺激され、冷えたはずの身体と心を熱く滾らせていく。その衝動に抗う事など当然出来るはずもなく、蕩けた股間へと手を伸ばしたのはそのすぐあとだった。
***
時は少し戻り、アケミと別れて『帰路についている』タクミ。その胸中はアケミと同じく不安で覆われていた。
(ふぅ・・・まさか本当に若い男の子に・・・タクミくんになっちゃうだなんて。私、元に戻るまでちゃんと『北島タクミ』をやれるのかしら・・・?)
先ほど話していた交友関係だけでも本人の信頼を損なわないよう上手く立ち回る必要があるというのに、野球部の活動まである。『アケミ』自身、運動音痴と自覚するほど身体を動かすのが苦手だったせいでこれまでの人生でも体育の授業以外ではほとんど運動した事がなかった。それをいきなり甲子園にまで出場した野球部のエースピッチャーをやれというのだから不安に思わないはずもない。考えれば考えるほど心が暗く曇っていくようだ。
「っ、あんまり考えすぎてもダメよね!どんくさい私の身体じゃなくて鍛えられているタクミくんの身体だし、いけるはず!・・・多分」
不安を払拭するようにあえて声に出して気合を入れ直す。そうこうしているうちに、あっという間に『自宅』へと辿り着いた。初めて見る他人の家の鍵を無遠慮に開けるという行為にドキドキしながら扉をくぐる。
「お、おじゃましま・・・じゃない、ただいま」
つい出そうになった言葉を慌てて修正しながら口にする。すると奥からパタパタとスリッパを履いた足音特有の音が響き、一人の女性が姿を現した。
「おかえり。あんた、ちょっと遅かったじゃない。部活はお昼過ぎで終わるって言ってなかった?」
出てきたのはタクミの母親である北島キョウコ。
『タクミ』の話からしてアケミよりも年上、既に四十歳を超えているはずだが、それを全く感じさせない若々しさと美貌を兼ね備えている。気の強い印象を抱かせるツリ目は活気で漲り、肌もツヤとハリに満ちていると一目で分かるほど。
ちょうど運動でもしていたのか、腰まで伸びる黒髪を動きやすいポニーテールに纏め、動きやすい黒のスポーツウェアを着用している。ぴったりと身体のラインが出るような服装のおかげでその引き締まった体形が惜しげもなく晒され、思わずタクミは見惚れてしまった。そういえば身体を動かすのが趣味といっていたな、と思い出しつつ抱いた尊敬の念を表に出さないようにしながら『タクミ』の口調で返す。
「う、うん。実は帰り道に重そうな荷物を抱えてフラフラしてた女の人がいてさ。心配だったから家まで送って、ちょっとお茶をご馳走になってたんだ」
「そ。・・・良い事したわね」
口調こそややそっけないものの、ふわりと慈愛を感じさせる柔らかな微笑みに自分の事ではないのにも関わらず胸が温かくなる。もし自分に子供がいたらこんな風に出来ただろうか、と思わずにはいられない。
と、キョウコの微笑みが訝しげに歪む。何か失礼な事をしたのだろうか、まさか中身が違う事がバレたのか――と胃がせり上がるような感覚を覚えるとキョウコはくるりと背を向けた。
「それはそれとして・・・あんた、汗臭いわよ?早くシャワー浴びなさい」
「わ、分かった」
ここに帰ってくるまでに多少慣れてしまっていたが、確かに運動後という事もあってタクミの身体は少し臭う。確かにこれでは室内を歩けないだろう。
(確か洗面所は玄関を入って右、だったわね)
「って、お風呂・・・!?」
***
「ほ、本当にいいのかしら・・・」
洗面所でどうしたものかと立ち尽くす。風呂に入るという事は全裸にならなければいけないし、さらには身体を洗うために全身をまさぐらなければいけないだろう。他人の――ましてや年下の男の子の身体をそんな無遠慮に扱ってもいいのだろうか、としばらく逡巡していたものの、ふと鼻を汗特有の酸っぱい臭いが刺した事で覚悟が決まった。
(そう、よね・・・いつ戻れるか分からないし、その時までずっとお風呂とかトイレとか我慢するわけにもいかないし・・・それなら今のうちに慣れておいた方が良いわよね)
まさか何日も風呂に入らない不潔な状態で過ごすわけにも身体を返すわけにもいくまい、と意を決して服を脱ぎ始める。特に迷う事もなくスムーズに脱いでいくが、途中で鏡に半裸の姿が映ってしまったので慌てて目を瞑った。
「ご、ごめんなさい!あんまり見ないようにするから・・・!」
事故的にとはいえ半裸を見てしまった罪悪感で思わず口から謝罪が零れる。そのまま下も全て脱ぎ、股の間でプラプラと揺れるナニかをなるべく意識から外しつつ薄目で壁をつたい風呂場へと何とか入る事に成功した。
ここまで来ればもう大丈夫だろう、と目を開けたものの、タクミは動揺のあまりある事をすっかり失念していた。風呂場にも当然、鏡がある事を。
「きゃっ・・・?!」
反射的に出てしまったか細い悲鳴。目の前に突然現れた『男』にタクミは慌てて内股になって胸と股間を隠すが、虚しく空を切る胸元側の腕と妙な感触が返ってきた股間側の腕、さらに『彼』が全く同じポーズになったせいでその男が自分自身なのだと自覚させられた。
風呂場に設置されている鏡は少し離れているせいでタクミの全裸をばっちりと余すところなく映し出し、野球部エースらしい鍛え上げられた鋼の肉体を惜しげもなく晒し上げる。服の上からでは細く見えていたがその下はがっしりとした筋肉で覆われ、特に投手の命である腕や肩回りは一番に目に付くほどだ。もちろんそこだけに留まるはずもなく、腹筋や足回りといった部位も非常に良く鍛えられ、男の肉体としてこれ以上ない魅力を放っていた。元の自分とは真逆の若く健康的で研ぎ澄まされた身体にタクミは思わず見惚れてしまう。
(す、すごい・・・さすが男の子っていうか、こんなにがっしりとしてるのね・・・)
そのまま無意識のうちにペタペタと全身を触り始める。グッ、と腕に少し力を入れるだけで元の身体の何倍も力が籠り、二の腕には山のような力こぶが盛り上がる。力を入れて押してみてもビクともせず、どれほどの練習を積めばここまで仕上がるのかと純粋な尊敬の念が湧き上がった。腹筋は当然のように六つに割れ、それぞれの境界もはっきりと目に見える。指でなぞると心地の良い段差とその奥の硬さが伝わり、何度も往復したくなってしまう。そんな身体に、自分が今なっているのだと思うとドキドキと興奮が湧き上がってきた。さらに男になっているという事はその興奮を敏感に反映する器官があるわけで。
「きっ、きゃあっ?!」
夢中で腹筋をなぞっていたせいで鏡越しではなく肉眼で勃起した逸物が目に飛び込んでくる。男子高校生としては平均的なサイズではあるものの、包皮はしっかりと剝けていて成人男性のそれと遜色はない。元夫のモノで散々見慣れているはずの『アケミ』だったが、唐突に視界に入った事、何より自分に付いているという本来ならば一生経験するはずがなかった視点で見てしまったおかげで再び甲高い悲鳴を上げてしまった。
(みっ、見ちゃった・・・!タクミくんのおちんちん・・・)
顔を真っ赤にして慌てて目を逸らす。だが興奮状態で異性の性器を見てしまえば気にならないはずもない。内心では申し訳なさを感じつつも、ゆっくりと首を動かして再び逸物を視界に収める。
「す、すごい・・・男の人のおちんちんってこんな感じなのね・・・♡」
己の身体から斜め上に突き出した肉棒。その下には大事な種を生産する二つの玉がふるふると揺れる。どちらも女性ののっぺりとした股間では味わえない異物感だが、それを今こうしてはっきりと感じている背徳感で得体の知れない興奮がゾワゾワと背筋を駆け巡っていった。
さらに逸物をじっくりと観察してみると記憶の中にある凶悪なそれとは違いが多く見受けられる。元夫の男性器はいわゆる巨根と呼ばれるほどに太く大きく、カリ首や全体に浮き出る血管が嫌な迫力を放っていた。加えて持続力も異様に長く、それの相手を延々とさせられた苦い記憶が脳裏を掠める。『アケミ』にとって男性器は恐怖と嫌悪の対象であり、それを模したディルドでさえ避けてしまうほどに嫌な思い出としてこびりついていた。
しかし今目の前にあるタクミのものはガチガチに勃起してもなお威圧感というものは存在せず、むしろ本能的に惹き付けられるような不思議な魅力を放っている。それを目の当たりにし、タクミは我知らず呟いていた。
「か、格好いい・・・♡♡」
高鳴る鼓動のまま、うっとりと呟く。さらに『アケミ』自身、徹底的な開発をされて欲求不満に疼く身体を何年も一人で鎮めてきた、いわば男日照りの魂。そんな人間が『興奮している若い男の身体』を目の当たりにしたのならば取る行動は一つだろう。
「っ・・・!♡」
ドキドキドキドキ、と腹筋に触れていた腕をゆっくりと下ろしていく。ゴワゴワの陰毛を越え、硬くそそり勃った逸物を優しく握るとそれだけで微かな快感が返ってきた。
欲求不満な元人妻の秘めた性欲を持つ魂に、男子高校生の性欲旺盛な身体。それらが上手く混ざり合ってしまった結果、握った手は勝手に動き出していた。
「ひゃうっ・・・!♡♡」
シュッ、と一度扱いただけでゾワリと全身へ走る快感。女性のそれとはまた違った感覚に一瞬で病みつきになってしまった。元夫に仕込まれたテクニックでスムーズに扱き上げていく。
「んっ♡♡ふあっ♡♡んんっ♡♡」
シコシコシコシコ、と握った手が上下するたびに先端から先走りの汁が垂れ、指へと絡み付いて滑りをさらに加速させていく。
か細い喘ぎ声と肉棒を扱く声が風呂場に響き、いやらしい事をしている罪悪感と背徳感を掻き立てる。鏡を見れば蕩けた顔で内股になり必死で己の逸物を扱き上げる顔立ちの整った若い男の子。ツンと鼻を刺す汗の臭いに混じってイカのような臭いも広がり、その興奮は際限なく高まっていく。全身を駆け巡る快感はこれまで惰性で行っていた自慰とは比べ物にならない程に気持ち良く、久しぶりの『性行為』をしている満足感で飢えていた魂が急速に満たされていった。
だがそんな極度の興奮に性欲旺盛な男子高校生の身体が――ましてや甲子園を控え、自慰をする余裕もないほど毎日練習していたせいで色々と溜まっていた『タクミ』の身体が長く耐えられるはずもなく。
「ッッッ~~~~~!!!!!♡♡♡♡♡」
ドピュッ!と股間から勢いよく飛び出していく白濁液。まるで身体中の力がそこから出ていっていると錯覚するほどの強烈な快感に意識が揺らいでいった。
びゅくっ、びゅるっ、と何度かの痙攣の後、尿道に残った分も全て吐き出し終えてようやく一息をつく。荒くなってしまった呼吸を整えながらぼんやりと射精後特有の脱力感と余韻に浸る。
「はぁ、はぁ、はぁっ・・・♡♡これが、男の子の射精なのね・・・♡♡」
ほんの少しの虚脱感と、それを遥かに上回る幸福感と満足感。初めて経験する男の快楽にタクミはすっかり虜になっていた。
ふと股間を見ると一度射精したばかりだというのにまだまだ熱く滾っており、物足りないと言わんばかりにビクビクと震えている。一度刻まれた異性の強烈な快感はタクミの心を離してはくれず、導かれるように再び肉棒を握りしめたのだった。
***
翌日の朝。ちょうど今日は部活も休みだという事で、改めて今後の方針や戻り方を模索するためにタクミはアケミの自宅へと赴いていた。時間通りにインターホンを鳴らしてみるが何故か返事はなく、再度鳴らしてもまた返事が無い。
先ほど連絡した際にはきちんと返事があったので何かあったのかと仕方なく受け取っていた合鍵で部屋へと入った。
「タクミくん?入るわよ?」
慣れ親しんだ自宅の玄関をくぐってリビングへ。だがそこで目に入ってきた光景に思考がフリーズしてしまった。
「お゛っ♡♡んぁ、ひぎっ♡♡♡」
インターホンが鳴ったどころかタクミが入ってきた事すら気づいていない様子で必死に股間を弄り回しているアケミ。身に付けている簡素なシャツは既に汗でぐしょぐしょになり、ズボンは邪魔になったのか適当に放り投げられている。何より部屋中に充満するメスの臭いはこの自慰がどのくらい続けられているかを何よりも雄弁に物語っていた。
と、そこでようやく部屋に入ってきたタクミに気づく。
「あっ、アケミさんっ・・・!♡♡い、いつからそこっ、にぃ?!♡♡♡」
「つ、ついさっきよ。・・・その、勝手に入ってごめんなさい。インターホンを鳴らしても返事が無かったから何かあったのかと思って・・・」
会話中だというのにぐちゅぐちゅと股間を弄る手を止めないアケミにやや呆気に取られるタクミだが、その気持ちは『自分の事のように』よく分かる。あの身体は一度初めてしまうと自分の意思ではもはやどうこうする事も出来ないほど性欲が強いのだ、と。
「すっ、すみませっ・・・♡♡♡こんな、こんないやらしい事っ・・・!♡♡♡でもずっとムラムラが治まらなくてっ♡♡♡何回もイって全身クタクタなのにまだ全然足りないんですぅっ!♡♡♡」
理性ではもうやめたいと思っているが、それ以上に身体が求め続けてどうしようもないのだろう。元々は夫の開発が原因だが、それをあそこまで育ててしまったのは自分自身の責任だ、とタクミは意を決してアケミにある提案をする。
「ね、ねぇ・・・もし良かったら性欲解消のお手伝いをさせてくれないかしら?」
「・・・へっ?」
あまりに想定外の言葉に流石のアケミの手も止まる。提案した本人も恥ずかしいのか顔を赤らめながらもさらに続けた。
「そのっ、そもそもそんなえっちな身体に育てちゃったのも、タクミくんをその身体にしちゃったのも、私の責任だから・・・せめて性欲には振り回されないよう『処理』してあげなくちゃ、って思って・・・」
だんだん声が尻すぼみになりながらも最後まで言い切った。永遠にも思える数秒の沈黙の後、おずおずとアケミが口を開く。
「お、お願いします・・・実はさっきからアケミさんの・・・男の身体を見てるだけで心臓がすっごくドキドキしてて・・・こ、このままだとおかしくなりそうなんですっ・・・!」
元夫の一件から意識的に男を避けるようになって数年。その間に身体はこれ以上なく性欲を溜め込み、一人の女性として『男』の存在を求め続けていた。そんな強い衝動を抱えた身体にいきなり放り込まれ、制御できない性欲に呑まれそうになっている最中に求め続けていた男を見てしまえばそうなってしまうのはもはや当然の事だろう。もし自慰続きのせいで疲労状態でなかったらどうなっていたか分からない。そんな切実な思いを声色から悟ったタクミは優しく寄り添うようにアケミの傍に座り、指をしゃぶってたっぷりと唾液を絡ませた。
「分かったわ。その身体は誰よりもよく知ってるから任せて。・・・出来るだけ早く終わらせるから」
そのまま濃い陰毛が張り付いた股間に手を這わせ、既にぐちょぐちょに蕩けている秘部にゆっくりと指を突き入れる。何年も続けた性交や自慰のせいであっという間に指の根本まで飲み込まれてしまったほどにユルユルだったものの、ナカに侵入してきた異物を認識するやいなや膣は敏感に指を締め付けてきた。
「大丈夫?苦しくない?」
「だい、じょうぶですっ・・・♡♡ふっ♡♡ふうっ♡♡」
ただ指を挿入れただけなのに既に快感を生み出している自身の身体の貪欲さにやや呆れつつ、指の腹をアケミのお腹の裏側――いわゆるGスポットと呼ばれる部位に当てる。何度も何度も感じてきた特有のザラザラとした感触に手ごたえを感じるとそのままほんの少しだけ力を込めて擦り上げた。
「ん゛お゛っ?!♡♡♡」
その瞬間、まるで電流を流されたかのようにアケミの身体が跳ねる。背筋は反り首も真上を向いてしまったため表情こそ見えないが、聞き慣れた濁った喘ぎ声だけでどれほど感じているかは容易に分かった。
「あっ、アケミさんっ・・・今のって・・・?!♡♡」
「女の人のナカで一番気持ち良いところよ。大丈夫、力を抜いて・・・」
「ひぎぃっ!!♡♡」
ゴツゴツとした何かを刺激してやると再びアケミはビクビクと痙攣し、快楽の波に呑まれる。何年も自分を苛み続けた強烈な快楽を他人に、しかも年下の男の子に感じさせる事を心苦しく思いながらも慣れた手つきでひたすら掻き回していった。
指が一往復するたびにアケミの喘ぎ声が強くなり、みっともなくガニ股になった腰が浮いてくる。それを見ていると『自分が感じさせている』という支配感にも似た感情と興奮がゾワゾワと心の奥から湧き上がり、タクミも徐々に気持ちが昂っていった。
だがそんな容赦のない手つきについ昨日身体を交換させられたばかりで女体の何もかもを分かっていないアケミが耐えられるはずもなく。
「ん゛お゛ほぉ゛っ?!?♡♡♡お゛ひっ!?♡♡♡♡」
ブシャアッ!と汚らしい音と共に秘部から勢いよく愛液が飛び出す。浮き上がった腰をつま先だけで必死に支えていたが、ガクガクと小鹿のように震える脚ではそれも難しくあっという間にべしゃりと地面に倒れてしまった。今まで自分でシていたのとは文字通り桁が違う快感にしばらく呼吸を整えるのもやっと、という様子でぐったりと余韻に浸っていたものの、ふと熱っぽい視線を感じて何とか身体を起こす。そこで目に入ったのは股間をギンギンに膨らませ目を見開いてアケミを凝視しているタクミの姿だった。
「ふっ♡♡ふっ♡♡ふぅっ♡♡」
「あ、アケミさん・・・?」
呼びかける声も聞こえていないのか、返事もせずひたすらにアケミを――アケミのトロトロになった秘部を凝視している。そのまま熱に浮かされたようにぎこちない手つきでベルトを外すと、ぶるんっ!と硬くそそり勃った逸物を露出させた。各所にうっすらと青筋が透けて見え、先走りの汁も漏れ出している辺りどれほど興奮しているかは一目で分かってしまう。あまりの衝撃にアケミが言葉を失っていると、まるで逃がさないとばかりに太ももをがっちりと掴まれて大きく股を開けさせられた。
ここまで来ると流石にこれから何をさせられるのかは否が応でも分かってしまう。一刻も早く振り払わなければ数秒後には自分の逸物が自分のナカに入ってきてしまうだろう。
早く振り払わなければいけない、のに。
(な、なんで期待してるんだ俺・・・?!嫌なのに、止めなきゃいけないのに・・・アソコもお腹の下が疼いて・・・早く挿入れて欲しいって思っちゃってる・・・・!♡♡)
それはある意味当然の帰結。数年間男の味を我慢し続けた熟れたメスの身体が、自分の身体に興奮してくれる若い男の逸物を前にして悦ばないはずがない。そこにはただ純粋な欲望と本能だけが存在し、それを前にした理性など吹けば飛ぶような脆さでしかなかった。
つぷ、と既に受け入れ態勢が整っている秘部にあてがわれる逸物。そこまでいってもなお、アケミはこれから起こる事へは恐怖ではなく期待を抱いていた。
「ごめんなさい、タクミくんっ・・・でも私っ、私もう我慢出来ないのおっ・・・!!♡♡♡」
「ッッッ~~~!?!♡♡♡」
ズンッ、といきなり最奥まで突き上げてくる逸物。ヒクヒクとナニかを求めて止まなかった秘部は何の抵抗もなく肉棒を根本まで全て呑み込み、きゅんきゅんと嬉しそうに締め付ける。指でも無機物でもない、本物の男性器の感触に身体はこれ以上なく悦び、最大級の多幸感と快楽を生み出して全身へと送り出した。もはや津波のような奔流と化したそれをアケミが――『タクミ』が受け止めきれるはずもなく、一瞬で意識が彼方へと飛びそうになる。しかしそれすら膨大な快楽が許さず、そのせいで意識が引き戻されるというループに陥っていた。
一方、異性の身体と快感に溺れていたのはアケミだけではなく。
(これが私のナカ・・・♡♡♡あったかくて、ふわふわで、おちんちんが溶けちゃいそう・・・!♡♡♡)
熟成されたアケミの秘部は蕩けるような柔らかさと温度を持っており、ただ挿入れるだけでもゾワゾワと逸物から全身へオスの快楽が走る。だがずっと求め続けていたモノをようやく受け入れられたアケミの膣がそれだけで許してくれるはずもなく、まるで別の意思を持った生物のようにウネウネと逸物に絡み付いて逃がすまいと締め付けてきた。ただでさえ極上の感触を味わっていたところに緩やかな圧まで加わり、危うく即座に射精してしまいそうになるのを必死で堪える。しばらく挿入れたままの体勢でいると何とかやり過ごす事が出来た。
(あ、危なかった・・・私のナカってこんなにすごかったのね・・・♡♡♡)
と、挿入の余韻に浸っているとふとアケミの顔が目に入る。汗で前髪が張り付いているせいで目は良く見えないものの隙間から涙に反射した光が見え、頬は真っ赤に染まり、口はだらしなく開かれている。どこからどう見ても快感に振り回されている女性の――メスの顔。それを見た瞬間タクミの獣性が刺激され、気が付けば腰を大きく引いて再び突き出していた。
「お゛っ??!♡♡♡ん゛お゛っ!??♡♡♡お゛ほぉっ!!?♡♡♡」
パンッ!パンッ!と肉同士が激しくぶつかり合い、部屋の外まで響きそうなほど大きな音を立てる。あまりに容赦のないピストンにアケミは呼吸すらままならず、ただひたすら快楽に押し流されて濁った喘ぎ声を上げる事しか出来ない。
(こんなっ・・・こんなの嫌なはずなのにっ♡♡♡女の人の身体にされてっ♡♡♡えっちな事で頭がいっぱいになって♡♡♡『自分』に犯されてるなんて嫌なはずなのにぃっ♡♡♡気持ち良すぎてっ♡♡♡全部どうでもよくなるっ♡♡♡)
全身を駆け巡る快感と幸福にとうとう脳まで犯され、思考がドロドロに蕩けていく。気が付けば自分から女体の快楽を貪るように腰を振り、甲高い喘ぎ声を上げていた。それだけでは物足りないと訴える身体に合わせるようにキスをせがんだ。もっと、もっと気持ち良くなりたいと心の底から願っていた。
甘えるように突き出された舌にタクミも応え、唇を塞ぐとにゅるにゅると己の舌を絡ませる。同じ唾液のはずなのに妙に甘く感じるそれを存分に味わい、縋るように絡まってくる舌をあしらい、口内全体を蹂躙して犯していく。互いの唾液がぐちゃぐちゃに混じり合い、相手の吐いた息で呼吸をし、お互いの境界線が曖昧になった頃にようやく口を離した。二人の本音を表すように銀色のアーチが名残惜しそうに繋がり、より一層淫靡な雰囲気を醸し出している。とろん、と蕩けた瞳でお互いに見つめ合いながらしばらく呼吸を整えていたが、ふとタクミが囁いた。
「・・・好き♡」
「・・・へっ?!」
たった二文字。その二文字がアケミの鼓膜を震わせ脳に届いた瞬間、これまで以上の幸福が全身を満たした。己の性感が生み出した幻聴か、と疑う暇もなく、今度は聞き間違いのないような音量ではっきりとタクミが告白してきた。
「うん・・・やっぱり好きよ、タクミくん♡そんなオバサンの身体にしちゃったのは申し訳ないけれど・・・その身体で気持ち良くなってるのも、喘いでる声も、甘えた顔でキスをせがんできたのも、かわいくて・・・全部全部愛おしくてたまらないの!♡」
真剣そのものの顔で次々にまくし立てる。冷静な状態であればそれらはアケミにとって恥だったかもしれない。ただ性交の熱に浮かされて勘違いしてしまっただけかもしれない。それでも『好き』の二文字はこれ以上なくアケミの心を揺さぶり、全身に最大級の幸福感が満ち満ちる。
『アケミ』の身体はこれまで異性からの愛情というものを注がれた事がほとんどなく、あったのはただ恐怖と苦痛だけだ。それを知ってか知らずかタクミはこれ以上ない愛を宣言した事で身体は満たされ、それを『タクミ』にも伝えた。そのおかげでアケミもまた目の前の『男』に精一杯の愛を伝える。
「俺も・・・俺も好きですっ♡♡だからもっと・・・もっとくださいっ♡♡♡」
「っ、えぇ、えぇ!♡もちろんよ♡」
アケミの愛は『アケミ』の心も満たし、いつしか二人はお互いの指をしっかりと絡ませていた。ただの性欲処理から最上級の愛情表現へと変化した性交は至上の快楽を二人にもたらし、幸福感で満たしていく。
「タクミくんっ・・・!♡♡♡俺、もうっ・・・!♡♡♡」
「えぇっ♡♡♡いいわよアケミさんっ、いっぱい出して♡♡♡アケミさんの赤ちゃん欲しいのっ♡♡♡」
夢中で交わり続けるうちに自分が『タクミ』なのか『アケミ』なのかも曖昧になり、口調や記憶が入り混じってどんどん溶けていく。だが夢中で己の快感を、相手の身体を貪り続ける二人は全く気付かず、むしろ勢いを増していった。
初めて味わう異性の身体。ましてやお互いに極限まで興奮が高まっている状態では長く続けられるはずもなく、ほどなくして同時に絶頂を迎えた。
「「ッッッ~~~~!!?!?♡♡♡♡♡」」
ナカに注ぎ込む感覚と注ぎこまれる感覚。一生味わうはずのなかった至上の快感と多幸感で全身が満ち足りた瞬間、がっちりと『何か』が収まるべきところに収まるような感覚がした。身体が入れ替わってからというもの、ずっと全身に感じていた違和感。『これは他人の身体なのだ』という不自然さは綺麗になくなっており、まるでこの身体でずっと生きて来たかのような自覚が生まれる。後に残ったのは性交の疲労と、それを上回って余りある絶頂の余韻と満ち足りた感覚。ふわふわとしたそれらに抱かれるようにして意識を手放した。
***
一週間後。
日差しの降り注ぐアスファルトをアケミは汗だくになりながら歩いていた。
「ふぅ・・・相変わらず暑いわね。またこんなに買っちゃったし・・・ちょっと控えるべきだったかしら?」
肩にかかっているのはまたしても満載になったエコバッグ。少しは控えようと思ったが、どうにも自分は安売りという言葉に弱いらしい。そんな小さな自己嫌悪に浸っていると前から見慣れた顔の男性が歩いてきた。
「こんにちは、アケミさん。今から帰りですか?良かったら荷物持ちますよ」
そこにいたのは部活が休みだったのか私服姿のタクミ。どうやらアケミに会いに来たらしく、少し気取ったような恰好だ。
言葉に甘えて荷物を持ってもらい、雑談としてお互いの近況を話し合う。中でもやはり一番の盛り上がりを見せたのはタクミの甲子園だった。
「そうそう。俺、甲子園の一回戦勝ちましたよ!」
「うん、中継見てたわ!本当におめでとう。すごいわ」
目をキラキラとさせ、心の底から祝福するアケミ。わざわざテレビで見る辺り、熱心に応援していたらしい。
だが、ふとアケミの顔が少し曇る。その瞳に映るのは悔しさや羨ましさといった感情だ。
「・・・でも、やっぱりちょっと羨ましい。私も甲子園のマウンドに立ってみたかったわ」
そうアケミは――元タクミは呟く。結局あの後も身体は元に戻らずお互いの身体で過ごしているのだが、未練というものは中々断ち切れないらしい。
その言葉を聞いてタクミは――元アケミは申し訳なさそうに謝った。
「すみません、本当はアケミさんがあの場所に立つはずだったのに・・・」
「あ、謝らないで!お互い相手の身体で生きていこう、って決めたのは私なんだし!」
身体は元に戻らず、それどころか口調や記憶まで相手のものに染まって元自分のものは曖昧になってしまったのでそのまま生きていこう、と提案したのはアケミの方だった。不安も未練もあったが、こうするしか他に方法はない、と諦めにも似た感情があったのが理由の『半分』だ。
「そう、ですね・・・それなら俺、一生をかけてアケミさんを守ります。アケミさんの・・・『北島タクミ』の身体と人生を貰った人間として、ずっと支えていきます」
あまりにまっすぐな誓いに一瞬でアケミの顔が真っ赤に染まる。プロポーズそのものの言葉で告白されぐわんぐわんと思考が揺さぶられるが、何とか言葉を返した。
「い、良いのよこんなオバサンに気を遣わなくて!タクミくんだってもっと若い子の方が良いでしょう?そ、そうだ!確か後輩の女の子にタオル貰ってたわよね?あの子なら好みにも合うと思うし、お似合いだと思うんだけど・・・!」
恥ずかしさのあまり声を大にしてまくし立てるアケミ。しかしタクミはそれを涼しい顔で聞き流すとしっかりとアケミの手を取り、まっすぐ視線を合わせて宣言した。
「いえ、俺が好きなのはアケミさんだけです。身体と人生を貰ってしまった責任感はもちろんありますが・・・そんなのどうでもよくなるくらい、アケミさんの事が好きなんです。じゃなきゃ、『一生支える』なんて言えません」
「ひぁ・・・あ・・・」
純粋そのものの言葉にアケミの顔は日差しよりも熱くなり、言葉もまともに話せないほどに動揺してしまう。しばらくそのまま固まってしまったが、ようやく落ち着いたのか呼吸を整えてアケミも笑顔で応じた。
「うん・・・私もタクミくんが好き・・・♡タクミくんのお願いなら、出来る限り叶えてあげたいって思ってるわ」
タクミの真剣さに応じるようにアケミも真剣な顔で返す。この人が愛してくれる限り、自分も精一杯の愛を捧げたいのだ、と。
と、その言葉にタクミは少しだけ顔を赤らめて『お願い』をする。
「その、いきなりで悪いんですが、アケミさんにお願いがあって・・・」
「えぇ、大丈夫よ。何でも言って?」
「実は・・・」
***
その夜、アケミの家。
綺麗に整理された寝室のベッドの横でアケミは顔を真っ赤にしてプルプルと小刻みに震えていた。
「た、タクミくん?確かに何でも言ってとは言ったけど、これは流石に・・・!」
アケミが着せられているのはメイド服。しかも雑貨屋に売っているような安っぽい作りで、サイズも全く合っていない。ギチッ、ミチッ、と胸元の生地が嫌な音を立て、ギリギリまで丈を詰められたスカートはアケミのデカ尻も相まってほんの少し動いただけでも中の下着が見えてしまいそうだ。その中の下着にしても紐だけで構成されており、まさしく性交専用で大事な部分を隠すつもりなど微塵もないようなものだった。
「こ、こんなオバサンにこのえっちな服は似合わないんじゃないかなーって思うんだけど・・・」
「いえ、似合ってますよ。かわいいですし、正直めちゃくちゃ興奮します・・・!」
その言葉通りタクミの股間は見事に硬くそそり勃っており、彼がどれほど興奮しているか一目で分かってしまう。
「も、もうっ・・・!♡」
口では怒ったような素振りを見せながらも好きな人に褒められて内心まんざらでもなく、本能的に下腹部が疼いてしまう。既に股間は愛液でじっとりと濡れそぼり、受け止めるショーツはほとんどあってないようなものなので太ももにトロトロと流れっぱなしだ。
「ね、ねぇ、タクミくん・・・私、そろそろ・・・♡」
「・・・いいですよ。じゃあベッドに行きましょうか♡」
もじもじと恥ずかしそうにタクミの袖を引くアケミを優しく撫でながらベッドへ押し倒すタクミ。
アケミが元の身体に戻る事を諦めた理由のもう半分は結局のところ単純で、女として抱かれる快感が忘れられなかったせいだ。身体も若さも人生もがらりと変わってしまったが、それでもいいと思えるほどに今の身体に満足している。タクミの方も口に出しこそしないがその気持ちは同じだろう。
文字通り、お互いの『全て』を交換した二人の間には生半可な事では切れない強いつながりが生まれている。それはきっと、最期まで失われる事はない。