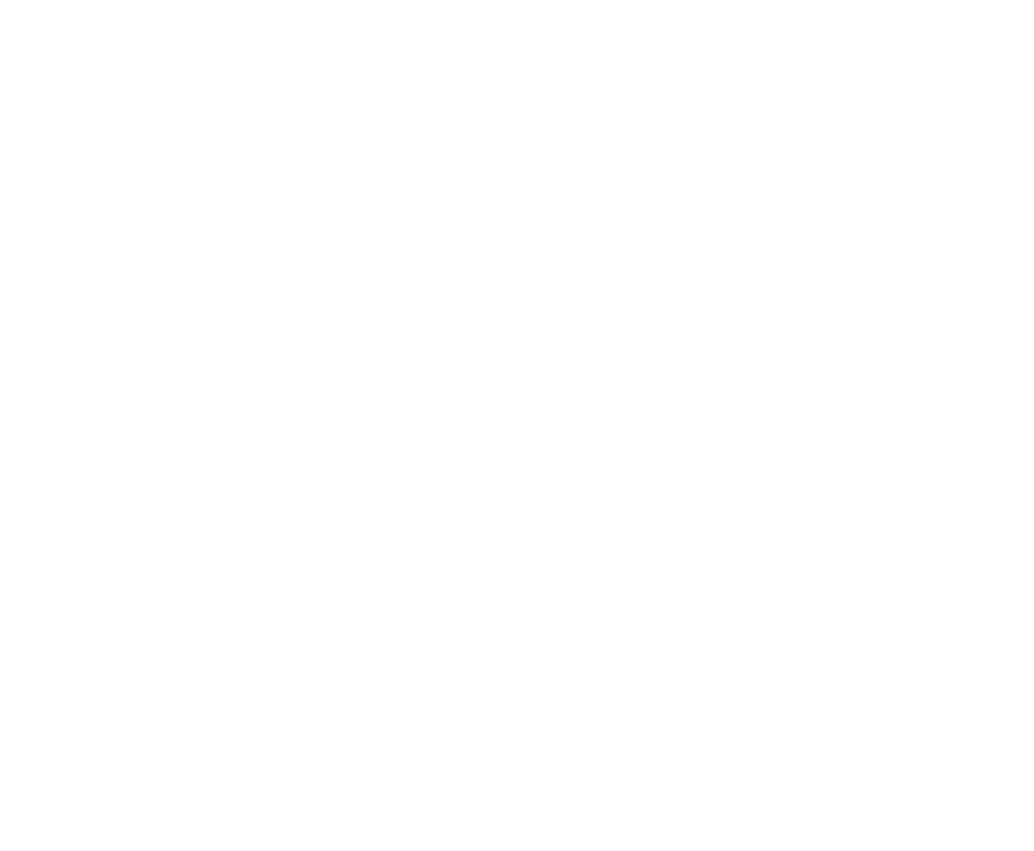「右藤君、ちょっといいか?」
「はい、何でしょうか?」
俺、右藤は商社に勤めるサラリーマンだ。担当は営業統括。そんな風にいうと物々しいが、各地にある営業所の管理をしている。営業所からの報告を受けたり、別の担当から預かった商材を営業所へ下ろしたり、営業所関係の何でも屋のような仕事だ。

「明日の午前中、商材説明会議に出てくれないか?」
俺に声をかけたのは営業統括課長だ。
「明日は昼から須州営業所の会議なんですが...」
俺がいる本社のある美府から須州までは電車で2時間はかかる。本社で商材説明会議に出ていたら、須州の会議には間に合わない。
「それなんだが、須州営業所の会議はリモートでやってくれないか?」
リモートか...。須州営業所の会議に出てから直帰するつもりだったのでがっかりしてしまった。それに、うちの会社のリモート会議システムが俺は苦手だった。しかし、そんなことは言っていられない。
「わかりました。リモートで用意します」
そう答えた。
午前中の会議が終わり、昼食の後にリモート用の部屋へ行く。パーテーションで区切られた部屋には机が一つだけあり、パソコンとヘルメットのようなものが置いてあった。俺はパソコンを立ち上げてヘルメットを被る。パソコンに表示された会議に「参加する」のボタンをクリックすると、ヘルメットからキュルキュルという電子音が鳴り始め、俺の意識は途切れた。
しばらくして目を覚ますとやはりパーテーションに区切られた部屋にいた。ただ、パーテーションの色が本社とは違うし、パソコンの型も古い。ヘルメットを脱ぐと、髪がパサっと揺れてほんのりと甘い香りがした。自分の身体を見下ろすと、さっきまでのスーツ姿ではなく、ピンク色のベストに同じくピンク色のスカートが目に入った。胸には豊かな膨らみがある。触ってみると弾むような弾力があり、同時に触られているという感触があった。パーテーションの中に備え付けられている鏡を見ると、20代半ばだろうか、どこか幼さの残る顔つきのかわいらしい女性の姿が写っていた。そう、俺の身体は頭からつま先まで女になっていたのだ。これがうちの会社のリモート会議システムだ。ネットワーク経由で会議参加者の精神を会議の開催場所にいる別の社員の精神と交換して会議を行なうのだ。回りくどいようだが、パソコンの画面越しよりも会議がスムーズだと一部の社員には好評で、特に本社に所属する社員は積極的にこのシステムを利用するように言われている。システムで使われる交換相手は様々で、会議開催のタイミングで本社に用事がある人がいればその人が選ばれるのだが、大抵は役職のない女性の事務員が選ばれる。今回、俺の相手に選ばれたのも若い女性の事務員で、膨らんだ胸には「左野」と書かれた名札が付けられている。俺がリモート会議を好まないのは、こんな風に他人の身体になるのが苦手だからだ。
パーテーションを出ると、
「あ、左野さん...じゃなくて、本社の右藤主任ですよね。私、その身体の左野と同じ総務課の前沢です。お疲れさまです」
今の俺と同じ制服を身につけた若い女性が話しかけてきた。歳はこの左野さんと同じくらいだろうか。
「お疲れさまです。右藤と申します。今日はよろしくお願いします」
「お困りのことがあれば遠慮なくおっしゃってくださいね」
そう言って前沢さんはクスクスと笑い始めた。
「どうかしました?」
「いつもの左野はもっとポヤポヤした雰囲気なので、そんなキリッとした顔をされるとまるで別人みたいで、つい...」
まるでというか、身体はともかく、別人そのものなのだが。
「そうだ、すみません、ちょっとお手洗いに行きたいのですが...」
「あ、はい、あちらの角を曲がった先ですよ。もう、リモートするときは先にお手洗いも済ましておくようにって言っているのに、左野のやつ忘れていたな...」
「いえいえ、結構ですよ」
俺はトイレへ向かい、用を足そうとするが、
「しまったな...」
男性用の小便器に向かって股を開いたところで気づいた。今の俺は女性の身体だから立ちションができないではないか。ガニ股になった脚を閉じて、何だか情けない気分になりながら個室へ入り、用を足すことにした。ストッキングを破らないようにずらし、下着をおろして便器に座ると、膀胱から直接尿が出るような感覚が伝わってくる。何度かリモート会議を経験して、女性の身体になることも慣れてきたが、やはりこの放尿の感覚には違和感がある。早く終わって元の体に戻りたいものだ。

会議は順調に終わった。今頃、本社では俺の身体になった左野さんが事務作業をしているのだろう。俺の顔でポヤポヤしながら仕事しているのだろうか...。身体を戻すためにシステム室へ入ると、この身体が名残惜しいような気もしてきた。小さくて非力だが、柔らかい肌と良い匂いのする髪のこの身体は「居心地」がよかった。そんな名残惜しさを抑えてパソコンを立ち上げると、
「通信障害」
そんな文字が表示された。
「あ、右藤さん!リモート会議システムなんですが、今は通信障害で使えなくて...」
前沢さんが慌てた様子で駆けつけた。
「通信障害って、復旧の見込みは?」
「本社の情報システム課に依頼しているのですが、まだ目処がわからなくて...」
そんな、俺はまだこの身体で過ごさなくてはならないのか?
どっと疲れたような気がして、さっきまでの名残惜しいような気持ちは消え去ってしまった。
「もし良ければ、復旧まで応接で休んでいてください...」
そう言われて応接に通されたが、仕事はできないし、暇つぶしにゲームをしようとしてもスマホは本社だし、正直、手持ち無沙汰だ。履き慣れないパンプスで足が痛いので、行儀は悪いがパンプスを脱いでソファにあぐらをかいて座った。タイトスカートがめくりあがって、ストッキングに包まれたのっぺりと平な股間が目に入る。何だろう、下着が少し濡れているような気がした。パンプスを脱いだ足からは匂いが漂ってきた。うっすら感じていたことだが、この左野さんの体は汗かきなのだろうか。そういえば、会議中もパンプスや下着が汗で蒸れるのを感じていた。髪から漂う良い匂いも、汗の匂いを隠すためのものなのかもしれない。そんなケアまでしなくてはならないのだから、女も大変なんだなと思う。
結局、夜になってもシステムは復旧することなく、俺は女の体のまま営業所を出ることになった。本当ならこの体の持ち主の左野さんはここ須州のどこかにある自宅に帰るのだろうが、流石にそれは問題があるということで、俺は須州駅前に会社が手配したホテルに泊まることとなった。
「ふぅ...」
チェーンホテルの簡素な部屋だが、やっと1人だけになれて一息ついた俺は営業所から着てきた制服のままベッドに腰掛ける。左野さんからは服を脱いで着替えてもいいと了承を得ている。いや、きちんとシャワーを浴びて欲しいとむしろお願いをされていた。裸を見られるよりもシャワーを優先するとはよっぽど気になるのかと思ったが、パンプスを脱いだストッキングの足はじっとり湿っていて昼間よりも臭いを感じた。背中にも汗をかいているようで下着が張り付く不快な感覚があった。確かにシャワーを浴びずにこれを放置するのは女性としては耐え難いものだろう。ただ、何となく抵抗を感じた俺は裸になるのを後回しにして夕食にすることにした。せっかく須州に来たのだからどこか飲みにでも行きたいところだが、女の体で夜遅くまで出歩くのはどうかと思うし、左野さんの体がどこまで酒を飲めるのかもわからなかった。前沢さんは「左野は結構飲みますよ」と言っていたが。夕食にしたのはホテルへの道すがらのコンビニで買った缶ビールと弁当だ。缶ビールをあおると、いつも飲んでいるビールのはずなのに苦く感じる。ただ、まるで体が酒を欲しているのかのようにゴクゴクと喉が止まらなかった。気づいたら缶ビール一本を一気に飲み干していた。
「マジかよこの体...」
そんなとき、フロントから内線があった。お連れ様が到着したという。お連れ様?
「あ、早速やっていますね!その身体、よく飲むでしょう?」
ホテルに現れたのは前沢さんだった。慣れない女の身体で過ごす俺の世話をしてくれるのだという。手配された部屋がなぜツインなのかと訝しんでいたが、そういうことになっていたのか。
「そんな、悪いですから良いですよ...」
俺は断ろうとしたのだが、前沢さんは構わないと言って居座る。
「もちろん、この分の手当はいただいていますからただの好意というわけではありません。それに...」
前沢さんがモジモジしながら口籠る。
「それに...、左野と私は女同士ですが実は付き合っているんです。恋人の身体を見ず知らずの男性に取られたような気がしてちょっと悔しくて」
どうも前沢さんの距離感が近いと思ったらそういうことだったのか。
「さ、早く食べてシャワー浴びてください!でないと、その汗臭い身体のまま私が襲っちゃいますよ!」
前沢さんがそんなことを言い始める。
俺はそそくさと弁当を片付けて、ユニットバスへと向かった。まずはピンク色のベストを脱ぎ、ブラウスのボタンに手をかける男性用と合わせが逆なのでぎこちない手つきでボタンを外していると外から前沢さんの声がした。
「右藤さ〜ん、開けていいですか〜?着替え忘れていますよ〜」
俺の返事を待たずに容赦なくユニットバスの戸が開かれた。
「あ、もしかして脱ぐの手間取っていました?」
「まあ、そうですけど...」
「それじゃあ、私が手伝いますよ!それが今日の仕事ですから!」
「いやいや!遠慮しておきます!」
「そんなこと言わないで...!」
前沢さんは聞く耳なく俺のブラウスとキャミソールを脱がせてタイトスカートを剥ぎ取った。顕になったのは下着姿の女の身体だ。
「これが...俺?」
「そうですよ...このかわいい顔、柔らかいおっぱい、ちょっと太い太もも...全部今は右藤さんの身体なんですよ...」
前澤さんの手が俺の身体を優しい手つきで撫でた。そんなふうに撫でられていると、頭の奥が熱を帯びてきたような気がしてトロンとしてくる。
「さあ、お風呂に入りましょう」
ブラのホックが外されて、ふっと胸の支えがなくなったような気がした。薄々感じていたが、ブラを外してみるとこの左野さんの身体の胸は結構大きい方ではないのか。俺の身体が動くと、胸がプルプルと揺れた。さらにパンツを脱がされると、薄ら毛の生えた股間が顕になる。勿論、男の身体にあるものは無く、なだらかな丘が股間の向こうへと続いていた。俺は本当に女の身体になってしまったのか...。アルコールと女としての快感が混ざり合い、俺の視界はぐちゃぐちゃになってしまった。シャワーを浴びた後、俺は前沢さんが用意していた寝巻きに着替えたのだが、ヤる気満々の前沢さんにすぐに襲われた。ふわぁと蕩けるような、男のものとは違う柔らかい興奮に頭の中が埋め尽くされ、俺は前沢さんの言うがままとなった。
「いつもは左野が攻めなんですよ。今日は特別ね」
そう言う前沢さんの股間にはそそり立つ男性器...ではなく、ペニバンが装着されていた。流石にそれを突き立てられるのには抵抗がある。俺の男の心は必死で拒否していた。
「そんなに嫌がっていても、ここはちゃんと濡れているじゃないです」
前沢さんがそう言って俺の股間に手をやると、ぬちゃっとした感触があった。俺の股間が濡れている...。今は俺が使っている左野さんの身体にとって、前沢さんは恋人だ。そんな恋人の身体を受け入れるために、この身体はすっかり用意ができていたのだ。そう思った時、急に抵抗する力がなくなった。そんな俺の股間に、前沢さんのペニバンが暴力的に差し込まれた。押し寄せる快感で視界がぼやけ、俺の意識はそこで途切れた。
翌朝、目を覚ますと俺は前沢さんとまるで抱き合うような格好でツインベッドの上で布団に包まっていた。
「おはようございます右藤主任、昨日はとってもよかったですね」
目を覚ました前沢さんがまだ眠そうな目つきでニヤニヤ笑いながら言った。
「サイズはどうですか?」
前沢さんに襲われた翌朝、ホテルから出勤するにあたって、前沢さんが用意してくれた服に着替えた。女性用の制服のままでは嫌だろうと会社の経費で用意してくれたのはマニッシュなパンツスーツだった。
「私と左野はサイズが大体一緒だからいったん私の身体に合わせて選んだんですが...。大丈夫でしょうか?」
ということは、もしかしてこのパンツスーツは前沢さんが一度着たものなのだろうか。昨夜の一件があったせいか、妙に意識してしまう。
オフィスカジュアルスタイルの前沢さんと2人でホテルを出ると、まるで本当のカップルのような気がした。いや、身体という視点では本当にカップルなのだから間違いではないが。
「え?まだ復旧していない?」
須州営業所に出勤して話を聞いた俺は思わず声を上げた。
「そうなんです...。ただ、本社の情報システム課によると異常は通信システムのみで、美府本社でローカル環境を使えば身体は戻せるそうで...」
須州営業所のシステム担当が申し訳なさそうに言う。そうならば仕方がない。本社の許可を得て、俺は左野さんの身体で美府へ向かうことにした。それにしても、昨日からの俺にかかる費用は結構な額になっているのではないか。大人しく俺が自分の身体で美府から須州へ出張していればこんなに費用はかからなかったのではないか。元はと言えば課長が会議の予定を詰めたからこんなことになったのではないかと腹立たしくも感じる。流石に前沢さんは美府までは来ないようだが、営業所の玄関まで見送ってくれた。どこか寂しそうな顔で手を振る前沢さんの姿を見ていると、またこの身体と須州という街に名残惜しさを感じてしまった。
須州から美府までは特急列車で2時間ほど。美府駅から近い本社に着くと、たった一日空けただけだというのに久しぶりに帰ってきたような気がした。
「あっ!私だぁ!」
本社で通されたのは情報システム課の会議室だった。会議室のドアを開けると、呑気な男の声がした。部屋の奥にちょこんと座っていたのはスーツ姿の若い男...まさに俺自身だった。ただ、なんとも締まりのない顔でニコニコしている。見た目は俺でも、中身は左野さんなのだろう。前沢さんが言っていたポヤポヤしていると言うのが見た目からもよくわかる。ただ...、この雰囲気でいて夜は前沢さんを攻め立てているんだろうな...。
「キリッとした顔しているし服も格好いいし、なんだか私じゃないみたい...」
俺の身体で左野さんが呑気な感想を言っている。俺の顔でそんな風に見つめられるとどうも気味が悪く感じてしまう。

「あ、あの左野さん、感想はともかく早く戻りましょう」
「はーい、あっ、そうそう最後に一言だけ、右藤主任の身体、とっても力あるし良かったですよ!」
「それは良かった。またご入用でしたら貸し出しますよ」
そう言葉を交わして、俺たちはシステムのヘルメットを身につけた。ローカルネットワークでもリモート会議システムの内容はあまり変わらない。ヘルメットのような機器を被るとキュルキュルという電子音が鳴り始め、俺の意識は途切れた。
「右藤主任!起きてください!」
女の声で気づき、ヘルメットを脱ぐとそこにはさっきまでの俺...パンツスーツ姿の左野さんの姿があった。ということは...、会議室の隅にある鏡を見ると写っていたのはスーツ姿の若い男。懐かしい俺の姿だった。
「戻ったのか...」
安心したおかげか、どっと疲労が押し寄せてくるようだった。
「私の身体、戻れて良かった〜」
声の方を見ると左野さんが嬉しそうに自分の胸を揉んでいたので、俺はさっと視線を逸らした。
「ん?あれ?右藤主任、もしかして昨日の夜に前沢と何かしました?」
身体に違和感があったのか、左野さんがそんなことを言い、俺は思わずギクっと身体がこわばった。後ろめたいことがありすぎる。
「いや、それは前沢さんが...」
「そうですか...。それは仕方ないですけど、キチンと埋め合わせしてもらいますよ」
左野さんはそう言ってニヤリと笑った。
俺たちが戻ってから、リモート会議システムの使用は休止された。俺たちの事故があったからということもあるが、システムで身体を使われることが多い女性事務員から不満の声が上がりはじめたことが大きかったようだ。せっかく開発したシステムが使われなくなり、情報システム課の連中はがっかりしていたが、その代わりがあった。
「お久しぶりです」
あの一件からしばらく経って、俺は商材説明のために再び須州営業所を訪ねた。説明会議の後に俺を迎えたのは左野さんと前沢さんの2人の女性事務員。俺にとっては忘れられない顔ぶれだ。


「お久しぶりです。待っていましたよ」
そう言う左野さんを見て驚いた。顔はあの日の別れ際に見たフワフワした幼さの残る顔のままなのに、ピンクのベストの制服では無くパリッとしたマニッシュなスーツを着こなしていて、どこか自信ありげに見える。
「随分と印象が変わりましたね...」
「あ、これ?なんか最近服の趣味が変わっちゃって...。右藤主任と入れ替わった後遺症なのかな?」
そんな軽く言うことではないだろうに、左野さんはあっけらかんとして言う。
「それに右藤主任だって、その爪、こっそりネイルしているでしょう?」
思わず俺は手を隠した。確かに、あの日から俺も色々と気になるようになってしまい、脱毛したり、スキンケアをするようになり、ついには爪を手入れするようにもなっていたのだ。これも入れ替わりの後遺症というものだろうか。
「まあ、そんな話はおいおいにしましょうよ」
前沢さんがそう言ってからイタズラっぽくきく。
「例のものはちゃんと持ってきましたか?」
前沢さんの言葉に、俺は段ボール箱を持ち上げてみせる。
「こちらにありますよ」
「じゃあ、定時後に場所を変えて試してみましょうね。楽しみだな〜」
左野さんが例によってニコニコ笑いながら呑気に言う。俺が持って来たのは「人体交換機」、例のリモート会議システムを改良して人間の身体を入れ替えることに特化した商品だ。まだ試作品で商品にはならないが、社員が試すことはむしろ推奨されていた。そもそもこれが商品化されることになったのは入れ替わり体験者として情報システム課からヒアリングを受けた左野さんの提案だった。
「だって、私は右藤主任の身体でムラムラ悶々と過ごしていたのに、右藤主任は楽しいことしていたなんてズルいでしょう?だから、身体を入れ替える機械を作ったらどう?って思ったんです」
そんなことを言っていた。社内でも正直なところ異性の身体になりたくてこのシステムをつかっていた人間は少なくなかったようで、提案はあっさりと通り、今は情報システム課で改良が続けられている。販売できるようになるのもそう遠い話ではないだろう。俺が左野さんの身体で前沢さんと交わったことを知った左野さんが埋め合わせとして求めたのはサンプルで再度、俺たちの身体を入れ替えることだった。元の身体に戻った時、もう二度と入れ替わりたくないと思っていたのだが、こうして左野さんに求められると不思議と断ることができなかった。いや、むしろ、心のどこかにあったまた女になりたいと言う気持ちが断るのを遮っていたような気さえする。そうして、俺はまた女の身体になった。
「って、あれ?」
ビジネスホテルの一室で左野さんと前沢さんとで「人体交換機」を試した俺だが、ヘルメットを外して見下ろしてみた身体は左野さんのものではなかった。
「これは...前沢さん...!?」
俺は左野さんの恋人で、俺があの夜に交わった前沢さんの身体になっていたのだ。
「私も2人が羨ましくて、身体借りちゃいました!」
前沢さんの精神が宿った俺の身体がイタズラっぽく笑った。
それから俺たち3人は身体を何度も入れ替えながら交わり合った。男の快感と女の快感が幾度となく入れ替わり、自分が誰の身体になって何を感じているのかも分からなくなる。そういえば、俺と入れ替わった左野さんは後遺症で男っぽくなった。一方で俺は女っぽくなった。きっと前沢さんも同じように変わってしまうのだろう。俺たち3人は身体を何度も入れ替えながら混ざり合い、1人の人間になってしまうのかもしれない。
でも、それはそれでいいじゃあないか。蕩けたようなぼんやりとした意識の中でそう思った。