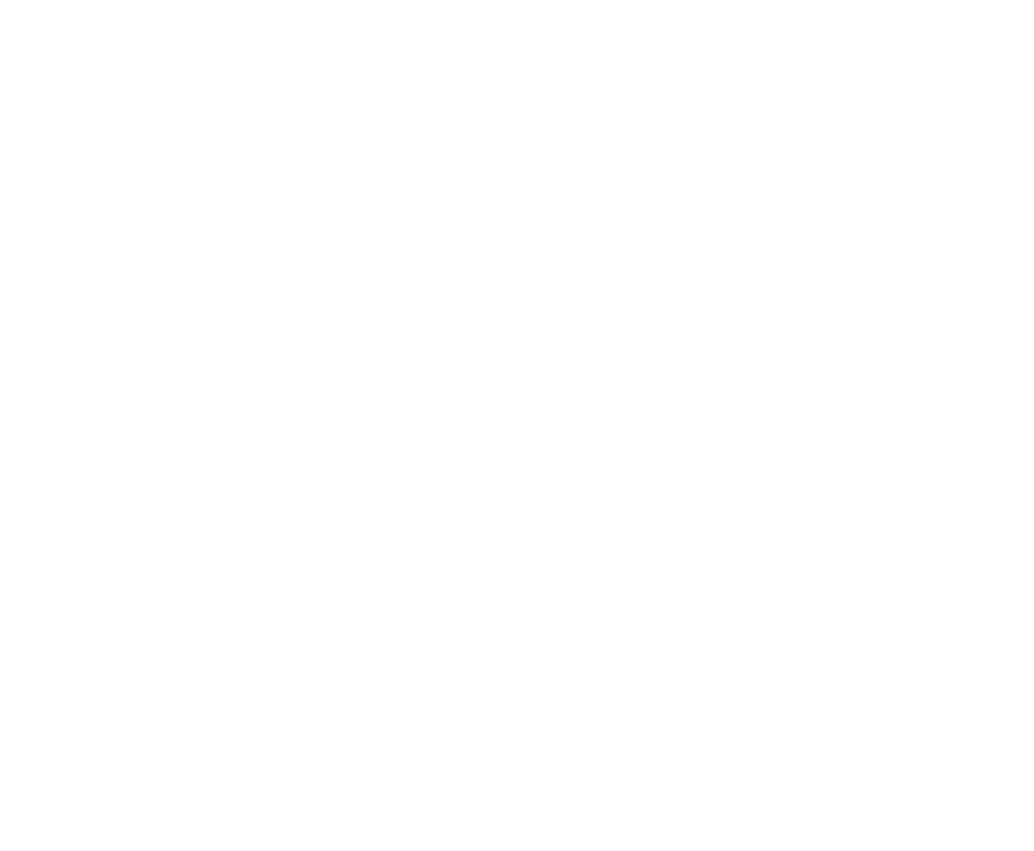「あのさあヒナ、おまえケッコンってしってるか?」
「ケッコン……?なあに、それ?」
「おとうさんとおかあさんっていつもいっしょにいるじゃん? なんでなのかきいてみたんだけど、ケッコンっていうのをしたからいっしょなんだってよ」
「そうなんだ。……いいなぁ」
「だからさ、オレたちもケッコンしねえ?」
「えっ?あたしと……そーちゃんが?」
「おう! オレさ、らいねんからしょうがっこうだから、そしたらヒナとはべつべつになるだろ?でもケッコンすればいっしょにいられるとおもうんだよなー」
「す……するっ!あたし、そーちゃんとケッコンしたい!」
「へへっ、それじゃあやくそくしようぜ! ゆーびきーりげーんまーん————」
***
俺は祭りというものが好きだ。普段は何も無い公園に屋台が立ち並んで、大勢の人で溢れかえる非日常的な空間。見慣れた場所でもその日だけは何もかもが違って見えて、まるで違う世界に来たように感じられるその場所が、そのイベントが幼い頃から大好きだった。
そして……そんな「日常」とかけ離れた状況下ならば、好きな子に告白するという一世一代の大勝負にも踏み切れるのではないかと、そう思ったのだ。
(そう、俺は今日この場所で、綾乃に告白するんだ……!)
考えただけで心臓がバクバクと音を立てはじめるが、既に2人きりで花火大会に行こうと彼女を誘ってしまっていて、しかもOKまでされたのだからもう後戻りはできない。後は綾乃と会って上手くエスコートして、タイミングを見て告白するだけ……と、言葉にしてみればなんて事のないことでもいざ当日になってみると話は変わってくるもので、朝起きてからずっと緊張しっぱなしで気が休まらないでいた。
中学時代からずっと片思いをしていた綾乃と知り合いになって、こうして花火大会に誘えるような関係にまでなることができたのは去年の文化祭がきっかけだった。
あの時のことは今でも鮮明に覚えている。軽音楽部のライブが始まるまでの時間潰しにその辺をフラフラとしている最中、吹奏楽部に入っている綾乃が何かバカでかい太鼓のようなものを重たそうに担いでいるのを偶然見かけた。そして「よかったら手伝おうか?」なんて声を掛けて俺への好感度を稼ごうかなんて思っていた矢先に、なんと彼女は段差につまづいてそのまま大きな楽器の下敷きになってしまったのだ。
そんな場面に遭遇しておきながら素通りできるはずもなく、こちらも若干パニックになりながら綾乃を助けてそのまま保健室まで運んでいったのだが……それをきっかけにして彼女と話す機会が増えたり、共通の友人を通して遊ぶことなんかもあったりして、やがて個人的な連絡を頻繁に取り合うまでの仲になることができたというわけだ。
(多分いける……よな? 2人きりだってのは事前に伝えてて、それでも断られなかったんだから……いや、でも……)
待ち合わせ場所についてからというものの、いけるかいけないか、そんな不安ばかりが頭を駆け巡っているせいで一向に気が休まらない。もし告白が失敗して、今まで築き上げてきた関係すらも崩れてしまったら……そんなこと考えるだけで胃がねじ切れそうだ。
(……待ち合わせの時間までまだかなりあることだし、気分転換にその辺でもぶらついてみるか)
適当に散策していれば気も紛れるだろうし、綾乃と屋台を回る際の下見にもなるだろう。そう思った俺は、待ち合わせ場所の広場から屋台が立ち並ぶ通りへと歩を進めていった。
***
「——あの、ちょっといいですか?」
考えるより先に、そんな言葉を発していた。
目の前には浴衣を着た怯えた様子の女性と、その女性の腕を掴んでいる中年の男が1人。その男は声を掛けた俺のことをギロっと睨みつけていて……やっぱやめときゃよかった、なんて言葉が頭をよぎる。
事の経緯はいたって単純。綾乃との待ち合わせ時間まで屋台を見て回っていた矢先、この男に絡まれていた女性が強引に腕を引っ張られてどこかへ連れていかれそうになっているのを見て、反射的に声を上げてしまったのだ。
見るからに話が通じなさそうな泥酔した様子の男を前にして足がすくむが、今さら引き下がることもできなかった俺は半ばヤケクソ気味に、相手の方を精一杯睨み返す。
「あぁ?なんだてめぇ」
「この人嫌がってるじゃないですか。 手、離してあげてくださいよ」
「へぇ?随分と威勢がいいじゃねえか」
「っ……!?」
なるべく刺激しないように言葉を選んでいるつもりだったのだが、むしろ相手の神経を逆なでしてしまったらしい。男は不快そうに表情を歪めると女性から手を離し、いきなり俺の胸ぐらを掴み上げてきた。
「女の前だからってカッコつけてんじゃねえぞクソガキ!」
ドスの効いた声で怒鳴られて身体が固まってしまうが、もう後には引けないと思いじっと視線を合わせ続ける。こうなったら何発か殴られるのは覚悟しておこう。暴力沙汰になれば流石に誰かが止めに入ってきてくれるはず……なんてことを考えていると、予想外なことに男の方が手を離した。
「……クソッ、どいつもこいつも……」
そんな捨て台詞を残して去っていく男の背中を見つめながら、安堵のため息をつく。
正直ビビりまくっていたのだが、男の俺でさえここまでビビっていたのだから、絡まれていた女性はさぞ怖い思いをしたことだろう。とりあえずはトラブルを無事に乗り切れたことを安心しつつ、彼女に向き直った。
「あ、あの、大丈夫でしたか?」
「うん、私は大丈夫だよ。 ……蒼汰くん、助けてくれて本当にありがとね」
「……えっ?」
知らないはずの女性の口から自分の名前が出たことに一瞬戸惑うが、よく見ると彼女の顔に見覚えがあることに気づく。
「蒼汰くんって……も、もしかして、綾乃なのか?」
「え?そうだけど……まさか、私だって分かってなかったの?」
「いや、まあ、その……浴衣だし、普段とその、色々違ったからさ……」
そう、目の前にいたのは他でもない綾乃だったのだ。
普段見慣れている制服姿とまるで違う綺麗な浴衣を着ているということもそうなのだが、普段は化粧をしていないようなのに今はうっすらとメイクが施されているところとか、ロングヘアの黒髪を後ろにまとめた大人っぽさを感じる髪型だとか、そういう部分も含めて完全に別人に見えてしまっていた。一方の俺はというと、Tシャツにデニムというあまりにもラフな装いで気後れしてしまう。
しばらくはそうして、何も言えずに綾乃のことをじっと見ていることしかできなかったのだが、不意に彼女は俺と目を合わせたかと思うと「ふふっ」と息を漏らした。
「な、なんだよ。どうかしたのか?」
「蒼汰くん、足震えてるよ?さっきまでカッコよかったのに、これじゃ台無しだなーって思って」
「い、いやっ、これは……!」
指摘されて初めて気づいたのだが、どうやら先程の恐怖がまだ残っていたらしく未だに膝がプルプルと震えていて……ピンチの綾乃を偶然助けることができてラッキーなんて思っていたが、確かにこれじゃあカッコがつくものもつかない。
あまりの恥ずかしさに顔が赤くなりそうになるが、それを誤魔化すようにして口を開いた。
「……そりゃまあ、あんな輩に絡まれたらビビるに決まってるだろ。 ていうか、綾乃は本当に大丈夫なのか?あんなことがあった後じゃ祭りどころの気分じゃないだろうし——」
「私はいいの!せっかくのお祭りなんだし、気持ちを切り替えて楽しまなきゃ! それに……もしまた何かあっても、蒼汰くんが守ってくれるでしょ?」
「!?」
そんな風に言いながら、俺の手を優しく包み込むようにギュッと握りしめてくる綾乃。手に伝わる柔らかさと温かさに意識が持っていかれてしまって、心臓がバクバクと激しく脈打ち始める。
「ほら、行こっ!」
満面の笑みを浮かべて俺の手を引く綾乃の姿は、今まで見た何よりも一番綺麗だった。
今日、俺はこの子に告白をする。その結果がどうなるのかは分からないが……彼女と回るこの花火大会のことを俺は一生忘れることができないのだろうと、心の底から思うのだった。
***
「……うわっ、結構人多いなぁ。 この辺は穴場のはずなんだけど……」
あれから屋台をあちこち回り尽くした俺たちは、もうそろそろ花火が打ちあがる時間だということもあり、屋台が立ち並ぶ通りから少し離れた高台まで足を運んでいた。
毎年大勢の人で溢れかえるメイン会場の広場とは違い、この辺は少し遠いせいか毎年ほぼ人が寄ってこないにも関わらず、花火がよく見える隠れた穴場……の、はずだったのだが、今年は例年と比べて人の数が明らかに多かった。
人が少ない静かな雰囲気のある場所で花火を見ながら告白するというプランが早々に瓦解してしまい、焦りと緊張で額に汗が滲む。
「大丈夫じゃない?広場の方よりは全然人も少ないし……ほら、あそこの芝生とか座れそうだよ」
「お、おう……」
うろたえている俺とは対照的に落ち着いた様子でそんなことを言う綾乃に手を引かれ、木陰になっている芝生の上に並んで腰かける。そして、お互いに一言も言葉を発することなくしばらく沈黙が続いた。
(……やばい、いざとなるとめっちゃ緊張してきた……)
声が出ない。今まで何百回とシミュレーションしてきた状況だというのに、こんな時のために用意していた気の利いた話題も、やろうとしていたことも、何もかもが頭から飛んでしまっている。
チラリと横目で綾乃の方を見やる。改めて見ても、今日の綾乃は本当に可愛かった。母親のおさがりだという花柄の浴衣に髪をまとめた姿は、いつも以上に大人っぽく感じられて、いつもは見えないうなじだとか、普段は絶対に見られない浴衣の隙間から覗く胸元だとかに目が吸い寄せられてしまう。
どう考えても俺なんかとは釣り合うはずもないというのに、どうして俺は告白なんて大それたことをしようだなんて考えてしまっていたのだろうか。いっそこのまま何も伝えずに、ずっと友達として——
「そ、蒼汰くん」
俺の思考を遮るようにして綾乃が口を開く。その表情からは先程までの落ち着きが失われており、代わりに頬にはほんのりと朱色が差しているように見えた。
「あのさ……」
「あっ、やっぱりそーちゃんだ!」
「うおっ!?」
綾乃が何かを言いかけた瞬間、突如として背後から聞こえてきた聞き覚えのある声に思わず身体が跳ね上がる。慌てて振り返ると、そこには見知った顔があった。
「なんだ、ヒナか。 たく、びっくりさせるなよな」
「えへへっ、ごめんごめん」
そこに立っていたのは俺の幼馴染であるツインテールの少女、松川ひなただった。歳は俺より2つ下だが、家が隣同士ということもあって小さい頃からよく遊んでいた仲でもある。
せっかくの祭りだというのに、こいつはいつも通りのフリフリとした少女趣味な感じの洋服に身を包んでいて、そんな普段通りのヒナの姿を見たおかげか緊張が一気に緩んでいった。
「綾乃先輩も一緒だったんですね、お久しぶりでーす」
「うん。ひなたちゃん、久しぶり」
俺に続いて綾乃の存在にも気づいたらしく、ペコリとお辞儀をするヒナ。
そういえば、ヒナとは中学の時に同じ部活に所属していたのだと、以前綾乃から聞いたことがあった気がする。普段は俺に対してタメ口で接しているヒナが敬語を使ってる姿を見て少し新鮮な感じがした。
(……というか、この状況まずくないか?こいつ、このまま居座る気なんじゃ……)
ヒナは幼馴染ながら俺の妹のような存在で、小学校の低学年くらいまではどこへ行くのにもずっと一緒に行動していたのだが……そのせいか、中学に上がってからも友人らといる俺に出くわした時なんかは、当たり前のようにそこに混ざってくることがしょちゅうだった。
普段の遊びとかなら断る理由もないし、そういう時は大抵受け入れていたのだが……流石に今日はそういうわけにもいかない。
「悪い、少しだけ待っててもらっていいか?ちょっとこいつと話してくるから」
「え?う、うん、もちろん」
戸惑いながらも了承してくれた綾乃をその場に残し、俺はヒナを連れて少し離れた場所へと移動する。
「もー、そーちゃんってば強引なんだから。それで、話ってなに?」
そう言いながら、ヒナはどこか落ち着かない様子で顎のあたりを親指でスリスリと触っている。幼い頃に指をしゃぶってしまう癖を直そうとしてできた、本人も気づいていないヒナの手癖。昔から変わらないそんな仕草に少し安心感を覚えつつ、俺は本題を切り出した。
「ああ、それなんだけどさ……悪いんだけど、今日のところは帰ってくれないか?」
「…………えっ?」
「その……お前にだから言うけど、これから綾乃に告ろうと思っててさ。流石に今日だけはお前と一緒ってわけにもいかないんだよ、分かるだろ?」
ヒナを納得させるためとはいえ、改めて口に出すとかなり恥ずかしいものがある。再び顔が赤くなってしまいそうになるのを堪えつつ、言葉を続けた。
「一緒に花火を見ようって来てくれたんだろうけど、ごめんな」
「……そつき」
「え?」
「……えへへっ、それなら仕方ないね。 そっか、そーちゃんって綾乃先輩のことが好きだったんだぁ」
少しだけ間が空くも、すぐに明るい口調で返してくるヒナ。一瞬泣きそうな顔を見せたような気がしたのだが……気のせいだったのだろうか。
「それじゃあ、あたしもう行くね。 告白頑張って。そーちゃんならきっと上手くいくよ」
「おう、ありがとうな。 ていうか、なんなら家まで送って行こうか?変な奴もうろついてるし、お前一人で帰らせるのも……」
「っ……!だ、大丈夫!じ、実はさぁ、広場の方に友達待たせてるんだよねー! じゃあね!」
「あっ、おい!?」
ヒナは俺が呼び止める間もなく走り去っていき、そのまま人混みの中へと消えていった。
思わぬ邪魔が入ってしまったが、おかげで先程までの緊張は大分ほぐれたような気がする。告白が上手くいくようにと背中も押されてしまったことだし……今度、何か埋め合わせでもしてやらないとな。
「悪い、遅くなった。まだ花火始まってないよな」
そうして綾乃の元へ戻り声を掛けたのだが……しかし彼女から返事はなく、どこか上の空な様子だった。
「どうしたんだ?」
「う、ううん、ちょっとぼーっとしてただけ。 それより、ひなたちゃんは一緒じゃないの?」
「ああ、あいつは他の友達と来てるらしくてさ、広場の方で見るんだと。受験生だってのに呑気なモンだよなぁ」
「そ、そっか、そうなんだ」
心ここに在らずといった感じの綾乃に首を傾げつつも、俺たちは再び沈黙の時間を過ごす。
正直に言って、俺はこうして綾乃の隣にいられるだけで幸せなくらいだった。以前はただ遠くから見ていただけの綾乃と友達になって、一緒に時間を過ごしていくうちに外見からだけじゃ分からないようなしょうもない部分も知ることができて、それでも彼女のことが愛おしく思えて……ここで何も言わなくても、俺はこれからもそんな綾乃と『友達』として居続けることができるのだろう。
だけど、だからこそ、ここで気持ちを伝えずに終わってしまうなんて絶対に嫌だ。例えフラれるとしても、せめて自分の想いだけはしっかりと伝えておきたい。
そして、意を決して口を開こうとした瞬間——ぎゅっと、綾乃の小さな手が俺の手を握りしめていた。
「あ、綾乃……!?」
「あのね……こんなこといきなり言われたら困るかもしれないけど、その……」
俺の手を握る綾乃の手に力が込められていき、少し震えているのが伝わってくる。頬を染めたままの彼女の瞳にはうっすらと涙が浮かんでいて何も言えなくなってしまう。
ごくりと生唾を飲み込みながら、俺は綾乃の言葉をじっと待ち続けた。
「私、蒼汰くんのことが——」
その瞬間、白く眩い光が俺の視界を覆った。
***
「ぐすっ……ひっ、ひぐっ、ぐすっ……あ、あれ…………?」
次の瞬間、何故か俺は泣きじゃくっていた。
——何が起きたんだ?ついさっきまで綾乃と芝生の上に座っていて、あいつが俺に何かを言おうとしていたはず……それなのに何故か少し離れた場所に立っていて、目からは俺の意思に反して涙がぽろぽろとこぼれ落ちていく。
「ぐすっ、ど、どうなって……は? なっ……カッター!?なんでこんなモンが……」
いつの間にか手に握られていたカッターナイフを、驚きのあまり落としてしまう。いつの間にか移動していていたことも、いつの間にか刃物を手にしていたことにももちろん驚いていたのだが……それ以上に信じがたい異変を前にして、しばらく動くことができなかった。
「なんだ、この女みたいな手……」
カッターを握っていた自分の手を目の前に掲げてまじまじと見つめる。そこに見慣れたはずの自分の手は無く、代わりに白くか細い、爪に装飾が施された小さな手がそこにはあった。
そして着ている服も。手と同じように縮んでしまったような腕はフリルやリボンで彩られたピンクのブラウスの袖に覆われていて、どこか涼しげに感じる足元はヒラヒラとした黒い布地に包まれている。
それらは当然、俺が着たこともない服ではあるが、同時にひどく見覚えのあるものでもあった。そして、その有り得るはずもない推測を確かめるべく同じく見覚えのあるポーチからスマホを取り出し、自撮りモードのカメラに自分自身の姿を映した。
「ヒナ…………」
そこには紛れもなく俺の幼馴染である少女、松川ひなたの姿が映し出されていた。涙によって化粧が少し崩れてしまっているが、見間違うはずもない、今まで何度も見てきたヒナの顔が呆然とした様子でこちらを見つめている。
軽く表情を変えても、確かめるように頬をつねってもカメラの中のヒナは俺と全く同じ行動をしていて、そしてこの状況が現実であるということを突きつけてくるかのように鋭い痛みが頬から伝わってくる。
「えっ!?ぼ、ぼくにおっぱいがある、どうなってるの!?あっ……あうぅっ♡♡」
「ふぎっ……!あ゛ぁぁぁぁっ!!う゛あ゛あぁぁぁぁんっ!!」
「い、いやぁぁぁっ!!?な、何この身体、声っ!!?アタシ、どうなっちゃったの!?」
「はぁ?こ、これが俺なのか!?……ひひっ、これなら警察にもバレやしねえな……!」
自らの現状を理解する暇もなく、周囲が一斉に騒がしくなり始めた。
まるで男児のような幼い口調を使いながら、周りに人がいることもお構いなしに自らの乳房を揉みしだき始める若い女性。そんな彼女の奇行を気にも留めないどころか、いきなりその場に寝転んで泣き出してしまった彼氏らしき青年。手に持っていた缶ビールを落とし、自分の身体をペタペタと触りながらオカマのような言葉遣いで絶望する中年の男。俺と同じようにスマホに自らの姿を映したかと思えばニタニタと下卑た笑みを浮かべ始める浴衣姿の少女……彼女は確か中学で同級生だった女子生徒だろうか。
辺りを軽く見回しただけでもそんな有様だったのだが、同じような喧騒が公園中から聞こえてくるようだった。
しかし、そんな混乱の最中であっても、俺は自分が置かれた状況を理解し始めていた。いや、理解させられたと言うべきか。
(多分、花火大会に来てた人たちの身体がぐちゃぐちゃに交換されてるんだ。それで俺はヒナの身体に……)
一体どうしてそんなことになってしまったのかは分からないが、この惨状を、そして俺がヒナになってしまっているという状況を見るにそう考えるしかなさそうだった。
なんで、どうしてこんなことになったんだ。本当なら今頃、綾乃と一緒に花火を見て——
(そ、そうだ、綾乃っ!!綾乃は……綾乃と俺の身体はどうなってるんだ!?)
俺がヒナの身体になったのと同じように、恐らく俺や綾乃の身体にも他の人間が入っているのだろう。徐々に騒ぎの声が大きくなりパニックが起き始めている周りの様子を見て、焦燥感が募っていく。
(頼むから、何も起きないでいてくれ……!)
慣れない女物の服と身体に戸惑いながらも、必死で人混みを掻き分けてさっきまで俺がいた場所へと向かっていく。
既に辺りは地獄絵図と化していた。身体を返せと怒りながら男に詰め寄っているギャルが逆に男に組み伏せられて服を脱がされていたり、おっさんのような口調の幼い少女が全裸になり、ぐすぐすとすすり泣いているおっさんの股間に跨って喘いでいたりとか。別人、それも異なる性別の身体になっている人が多いせいなのか、そういった行為がそこら中で繰り広げられている始末だ。
もしも綾乃や俺の身体で勝手にそんなことをされていたら……考えただけでぞっとする。
そうしてなんとか元の場所まで辿り着くと、そこには今まで飽きるほど見てきた男の姿があった。小柄なヒナの身体になっているせいかやたらとデカく見えるが、間違えるはずも無い、俺自身の身体が目の前に立っている。
どういうわけか綾乃の姿はなかったのだが……『俺』はこちらに気づいたかと思うと、驚いたように目を丸くした。自分の身体が勝手に動いているという事実に少し気味の悪さを感じつつ、もう一人の『俺』に声を掛ける。
「あ、あの……。すみません、実はそれ、俺の身体なんです……。あ、あなたも多分、別の誰かなんですよね?」
「"俺"って、もしかしてそー…………蒼汰くん、なの?」
「えっ?なんで俺のこと知って……」
「私、綾乃だよ。気が付いたら蒼汰くんの身体になってて……。そっか、蒼汰くんはひなたちゃんの身体になってたんだね」
「そうか、綾乃が俺の身体に……」
事態は何も解決していないにも関わらず、俺は少しだけ安心感を覚えていた。他でもない綾乃なら、俺の身体で何か勝手なことをされてしまうことはないだろう。……俺なんかの身体にさせてしまったことに、少し罪悪感は感じるが。
「そうだ、綾乃の身体はどこなんだ?ここにはいないみたいだけど……」
「……それなんだけどね、気づいた時にはもう私だけだったんだ。どこかに行っちゃったんじゃないかな」
「なっ……!?そ、それまずくないか!?早く探しに行かないと!」
「うーん、やめた方がいいんじゃないかな。どこにいるのかも分からないし、それにほら。きっと会場中がこんな感じでしょ?探すどころじゃないと思うよ」
「いや、でも……」
落ち着いた様子で淡々と言ってのける綾乃に、少したじろいでしまう。確かに、今のこの状況ではどうすることもできないかもしれないが……綾乃は自分の身体に誰かが入っていて、今も勝手なことをされてるかもしれないという状況が怖くないのだろうか。
「大丈夫、きっと後のことは警察とかがなんとかしてくれるよ。 ……ねえ、落ち着くまでは蒼汰くんの家に避難させてくれないかな。ここから近いし、両親も旅行中で他に誰もいないんだから丁度いいんじゃない?」
「えっ?いや、もちろん構わないけど……俺の親が今いないって、綾乃に言ってたっけ?」
「……やだなあ、さっきのデート中に蒼汰くんが話してたでしょ。それよりほら、早く行こ。こんなとこにいたらトラブルに巻き込まれちゃうよ」
「お、おう」
綾乃の……俺の身体に手を掴まれ、そのまま強引に引っ張られるようにして歩き出す。
(っ……!?な、なんだこれ、顔が熱いし、心臓も……)
今まで自分の物として当たり前のように存在していた、骨ばった大きく無骨な手。そんな俺自身の手で握られているだけだというのに、俺の胸は異様なほど高鳴っていた。
大勢の人の身体が入れ替わってしまっていて、しかも相手は俺の身体だというのに……そんな異様な状況でありながら、俺は綾乃と手をつないでることに興奮してしまっているのだろうか。
未だ騒ぎの収まらない祭り会場の中を、綾乃に手を引かれながら進み続けていった。
***
「ふぅ……。やっと一息つけそうだね」
「そ、そうだな……」
祭り会場である公園を後にした俺たちは、すぐ近くにある俺の家へと辿り着いていた。公園を出る時にパトカーが何台も止まってるのが見えたので、綾乃が言った通り何とか事態は収集してくれるのかもしれない。
(まだ変な感じが……俺、一体どうしたんだ……?)
俺の自室に入り、ようやく気分も落ち着くかと思っていたのだが……公園にいた時から感じていた胸の高鳴りは一向に収まらず、むしろ激しくなる一方だった。
「蒼汰くん大丈夫?なんだか顔が赤いけど……」
そんな俺を心配したのか、綾乃がぐっと顔を近づけてくる。俺のものだった顔が至近距離まで迫ってきて、そんな状況に何故だか先程以上にドキドキと胸が高鳴ってしまい、慌てて目を逸らす。
「お、俺は大丈夫だよ。 ……それより、これからどうしようか」
「どうしようって?」
「結局公園から離れちまったけど、綾乃の身体はまだあそこにいるわけだろ?俺がヒナになってるってことはきっと本来のヒナも。 それに……いや、なんでもない」
もし綾乃の身体が見つかったとしても、果たして俺たちは元の身体に戻れるのだろうか。口から出そうになったそんな言葉をぐっと飲み込んだ。こんな風に誰かと身体が入れ替わるだなんて、それこそフィクションでしか見たことがないようなあり得るはずも無いことだ。
どうやったら元の身体に戻るのかなんて分からないし、そもそもその方法があるのかすら分からない。もしずっとこのままになってしまったら……そんなことを考えると、どうしても声に出せなかった。
「……とにかく、俺は一度祭り会場まで戻るよ。綾乃の身体がまともな奴に使われてる保証はないし、それにヒナのことも心配だからな」
「待って」
そう言い残して部屋を出ていこうとする俺の腕を、綾乃の手がガシッと掴んでくる。驚いて振り返ると、彼女は俺の顔でこちらをじっと見つめていて……もしかして女の、ヒナの身体になっているせいなのだろうか。さっきからこうして俺の身体に触れて俺の顔に見られているだけでドキドキと胸が高鳴ってしまう。
「あ、綾乃……?」
「さっきも言ったでしょ?後のことは全部警察に任せちゃえばいいんだよ。 それに……今の蒼汰くんはひなたちゃんの、女の子のカラダなんだよ?あんなところを一人でうろついてたらきっと誰かに襲われちゃうってば」
「だけど……んぅっ!?」
ぐいっと引き寄せられ、気が付いた時には綾乃に、俺だった男の身体の胸元にぎゅっと抱き寄せられてしまっていた。綾乃の胸からバクバクという心臓の音がうるさいくらいに聞こえてきて……いや違う。これ、俺の胸の音だ。先ほどとは比べ物にならないくらいに鼓動が高鳴り、頭がどうにかなってしまいそうだ。
「そんなどうでもいいことよりさぁ……ねえ蒼汰くん。私とえっちしてみたくない?」
「……は?お、お前、何言って……」
「言葉通りだよ。こんな風に身体が入れ替わっちゃうなんて普通は体験できないことなんだから、せっかくだしお互いに異性の身体でしか味わえない感覚を味わってみようよ。 ……いつ元に戻っちゃうのかも分からないんだから、ね?」
「そ、そんなことしてる場合じゃ……あうぅっ!?♡」
言い返す間もなく、身体を抱きかかえられてそのままベッドの上に下ろされてしまう。
綾乃が何を考えているのかまったく分からない。普段の綾乃からは想像もつかないような強引さで、抵抗する暇もなく押し倒されてしまっていた。
「ふふっ、そんなに心配そうな顔しないでいいんだよ? 女の子のカラダの気持ちよさ、蒼汰くんにたっぷり教え込んであげるからね……♡」
綾乃も興奮している様子で、俺の顔をすっかり紅潮させながら顎に指先を這わせていて——
「…………ヒナ?」
ふと、眼前の俺の顔と幼馴染の顔が重なったように見えた。なんとなしに顎を触ってしまう、少し愛らしさも覚えていたヒナの手癖。綾乃がしたことのないそんな仕草を、綾乃が入っているはずの『俺』はやってみせたのだ。
「……蒼汰くん?ひなたちゃんがどうかしたの?」
「なあ、お前がヒナなんだろ?その癖もそうだし、それにさっきも……!」
浮かび上がった疑念をきっかけにして、今まで感じていた些細な違和感が次々と頭の中で繋がっていく。
『綾乃』の身体の行方を気にも留めていないことも、俺の家に親がいないことを知っていたことも、招いたことがない俺の家の場所を当然のように知っていて、俺の部屋まで迷うことなく来れていたことも。よく考えればおかしな話なのに、どうして今まで気づかなかったのだろうか。
俺の中に警戒心が生まれたおかげか身体に力が入るようになり、『俺』から……俺になったヒナから離れるようにして後ずさる。ヒナは驚いたように俺の顔でポカンと口を開けていたが、やがてクスッと、無邪気な子供の様に笑ってみせた。
「そっか、バレちゃったかぁ。結構上手く真似できてたと思ったんだけどなぁ。 それにしても……癖、ね。そーちゃん、そんなにあたしのこと見てくれてたんだ、嬉しいなぁ……」
「な、何言ってんだよお前!どういうつもりで綾乃のフリなんか——」
「決まってるでしょ?そーちゃんと結婚するためだよ」
「……は?」
あまりに予想外すぎる答えに思わず間の抜けた声を出してしまう。どうして今結婚なんて言葉が出てくるのか、意味が分からない。
困惑で頭が一杯になっている俺をよそに、ヒナは嬉しそうに話し続ける。
「だってそーちゃん、あの女の身体も中身もどこに行ったのか分からないってなったら、きっとすぐに探しに行ってたでしょ? だからあの女のフリをしてればどこにも行かないで、2人きりになれると思ったんだけど……ふふっ♡上手くいってほんとによかったぁ」
「ふ、2人きりって、一体何のために……」
「だから言ってるじゃん、結婚するためだって。 そーちゃんと……あたしの身体になったそーちゃんとえっちして、あたしたちの赤ちゃんを作るためだよ」
「ひゃうっ!?♡」
近づいてきたヒナにそっと頬を撫でられ、甲高い悲鳴をあげてしまう。落ち着き始めていた心臓の鼓動がまた激しくなり、全身が熱くなっていく。
「あははっ、やっぱりそうなんだ。 そーちゃん、今すごくドキドキしてるでしょ?」
「そ、そんなこと……」
「隠さなくたって分かるよ。だって今のそーちゃんはあたしなんだから。 大好きなそーちゃんと2人きりで、こんなに近くに居られるんだもん、ドキドキしないわけないよね。……いいなあ、あたしのカラダ。こんな風にそーちゃんから愛してもらえるなんて、ちょっと羨ましいかも」
「あ、あぅぅ……♡」
ヒナに頭を撫でられた俺は、何も言えなくなってしまっていた。
俺の身体で勝手なことをしているこいつを咎めるべきなのに、一刻も早く綾乃のことを探しに行きたいはずなのに。それなのに、こうしてヒナに触れられているだけで頭の中がふわふわしてきて、全身から力が抜けていってしまう。
「……あたしね、死んじゃおうって思ってたんだよ?あたしとの約束を忘れてあの女のことを好きだなんて言うから……だから、一緒になれないくらいならあの女を殺してあたしも死んで、そーちゃんの心に『あたし』をずっと刻み込んであげようって、そう思ってたんだぁ。でも……」
近づいてきた俺の身体にぎゅっと抱き着かれる。今すぐ振りほどきたいのに、身体はまるで言うことを聞いてくれない。
「ふふっ、まさか身体が入れ替わっちゃうなんてね。びっくりしたけど……でも、本当によかった。おかげで夢にまで見たそーちゃんとのえっちが現実になるんだから♡」
「っ……♡ひ、ヒナ、こんなバカなことはやめてくれ、お願いだから……ひぅっ!?♡」
軽々と持ち上げられて後ろ向きにさせられると、そのまま背後から覆いかぶさるようにヒナの、俺の身体の逞しい腕に抱擁される。ショーツの中へと手が潜り込んできて、その指が俺の股間を……あるはずの膨らみが何もないヒナの身体の女性器をつーっとなぞり上げられ、ビクッと背筋が震えてしまう。
「やめてなんて言ってる割には、そーちゃんのアソコすごいことになってるよ? ほら、ちょっと触っただけなのにこんなに濡れて……そーちゃん、あたしのカラダでたくさん感じてくれてるんだね♡」
「ち、ちがうっ、そんなわけ……」
「嘘なんかついたってすぐに分かるよ、あたしの身体なんだから。 それじゃあ、挿れる前にちょっとだけほぐしてあげよっか」
「い、挿れるって、まさかお前本気で……うあぁっ!?♡♡」
つぷりと、自分の体内に何かが入り込んでくるという初めて感じる異物感と共に、反射的に甲高い嬌声をあげてしまっていた。俺のものだった太い指でくにゅくにゅとナカを刺激されて、少しだけ膨らんだヒナの胸をごつごつとした大きな手で愛撫されて。全身から伝わってくる未知の快感でびくっびくっと痙攣してしまう。
「ずーっと前から、あたしはずっと本気だったんだよ。……そーちゃんは違ったみたいだけどさ。 でも、もういいの。あたしとの赤ちゃんさえ出来たら、優しいそーちゃんならきっとあたしのことをお嫁さんにしてくれるでしょ?」
「あっ♡♡あぅっ……♡♡な、何言ってんだよヒナ……うぅっ♡ こ、これはお前の、自分の身体なんだぞ……!?」
「ああ、言われてみれば、そっか。今はあたしがそーちゃんで、そーちゃんがあたしなんだから……お嫁さんになるのはそーちゃんの方かぁ。えへへっ、なんだか可笑しいね♡」
狂ってる。俺の声で無邪気に笑うヒナに、俺はそう言いたかった。けれど、口を開くと漏れ出るのは甘い喘ぎ声ばかりで、まるで説得力がない。抵抗しようにも身体に力は全く入らなくて……ヒナの身体で無理やり与えられ続ける女の快楽に、ただひたすら翻弄され続けることしかできなかった。
「はっ♡あっ、あぁぁっ♡♡♡ひ、ヒナっ、も、もうやめっ……ひぅっ♡♡な、なんかキそうで……っ♡♡♡♡」
「あ、肩ぎゅーってなってる。そろそろイキそうなんだ? そしたらほら、力抜いたほうがいいよ。その方がずっと気持ちよくなれるんだから♡」
「ふあぁぁっ!?♡♡♡♡あっ、なでるのやめてぇっ♡♡ おかしくなっちゃ……あぁぁぁぁっ!?♡♡♡♡♡あ、あうっ♡♡うぅぅっ……♡♡♡♡」
不意に頭を撫でられたせいで全身に入っていた力が一気に緩んでしまい、溜まりきっていた快感が破裂して全身へと広がっていく。身体の奥底から込み上げてきたもので頭の中が真っ白になって、視界に火花が散っているような感じがして——その瞬間、空っぽになった頭の中に洪水のように『何か』が流れ込んできた。
それは、『あたし』が松川ひなたとして生きてきた今までの全てだった。まだ小さい頃にそーちゃんの家族が隣に引っ越してきて、人見知りで不愛想な、今思えば可愛くなかったあたしなんかとそーちゃんはいつも一緒にいてくれて……結婚するなんて約束までしてくれて、それが死ぬほど嬉しくて——
(ち、違うっ……!これは俺の記憶じゃない、ヒナの……い、一体どうなって……!?)
狼狽える俺をよそに、頭の中にヒナとしての記憶が無遠慮に流れ込んでくる。
そーちゃんに見合う子になるために、可愛くなるために必死に努力して、いつか自慢の彼女だと言ってもらうために明るく振舞うようになったこと。ママの趣味で無理やり着せられたフリフリのワンピースをそーちゃんが可愛いと言ってくれて、それ以来そんな服ばかり着るようになったこと。そーちゃんが先に中学生になってすごく寂しかったことも、2年経ってまた同じ学校に通えるようになったのがたまらなく嬉しかったことも。全部全部、あたしの思い出の中心にはいつだってそーちゃんがいて——
「——ふふっ、蕩けた顔しちゃって可愛い♡あたしのカラダ、そんなに良かった?」
「そーちゃん…………♡ あ、あれっ?今俺、なんて……」
そう呟いた自分自身の言葉に思わずはっとする。目の前にいるのは紛れもなく俺自身の身体だ。そのはずなのに、大好きなそーちゃんが目の前にいることが堪らなく嬉しくて……?
「あははっ、すっかりあたしになり切って、なんだかんだ言ってもノリノリみたいだね? それじゃあ、シよっか。……そーちゃんの、男の人の身体になってるせいなのかな?あたしの身体を触ってただけなのに、おちんちんがもう破裂しそうで我慢できなくなってきちゃった……♡」
「うぁっ……♡あぁぁっ……♡♡♡」
ヒナの記憶に呑み込まれそうになっている間に脱がされていたのだろうか。気づけば下半身の衣服は全て取り払われていて、ベッドの上に仰向けに寝かされてしまっていた。そしてそーちゃんの……俺の身体も同じように下を脱いでいて、慣れ親しんだ自分のモノだった股間がまるで初めて見るもののように感じられた。
こんなことやめろと説得しようにも、口はそれを拒絶するように言葉を発せずに息が漏れ出ていくだけで、そして抵抗しようにも身体に力が入らず……いや、もう抵抗しようなんて意思は俺の中から消え失せてしまっていた。
(ずっと夢見てた、そーちゃんとのえっち……♡♡あたしたち、やっと一緒になれて……違う、こんなの俺の意思じゃない、ヒナの身体になってるせいでおかしくなってるだけなんだ……。だから、こんなことやめさせなきゃいけない……のにぃっ……♡♡♡♡)
俺のじゃない記憶と感情で心が覆われて思考がぼやけていく。嬉しい気持ちで身体中が満たされて、子宮のあたりが待ちわびているようにキュンキュンと疼きをあげている。
まだ中学生のヒナの身体に、俺の身体でこんなことさせていいわけがないのに……今はむしろ俺の方から抱きつきたくて仕方が無くて、身体の奥底から湧き上がるそんな衝動を必死に堪え続けることで精一杯になってしまっていた。
「それじゃあ挿れるよ?挿れちゃうからね?……あたしのハジメテ、そーちゃんにもらってもらえるんだぁ……♡」
「っ~~~~♡♡」
ぐいっと脚を持ち上げられ、蕩け切った俺のおまんこに、熱を持ったそーちゃんのおちんちんがあてがわれる。それだけでもう、堪え切れないほどの幸せが込み上げてくるようで——
「あっ♡♡♡んあぁぁぁぁぁっ♡♡♡♡♡」
その熱いモノがおまんこの中に入ってきた瞬間、それだけでまたイってしまっていた。快感で脳みその奥までびりびりと痺れて、その余韻に浸る間もなく今度はおちんちんがゆっくりと奥まで入り込んでくる。
「あははっ、またイっちゃったんだ?あたしになったそーちゃん、本当に可愛い……♡」
「や、やらっ♡俺の声で可愛いって言わないで、おかしくなっちゃう……♡♡」
「可愛いって言われただけでそんなに悦んじゃうなんて、本当にあたしみたい♡ 何度だって言ってあげるよ?だって今のそーちゃん、本当に可愛いんだもん♡」
「っ~~♡♡だ、だから、やめてってばぁ♡♡♡♡あうぅっ♡♡」
大好きなそーちゃんの声でそう囁かれるだけで、あたしが言って欲しかった言葉を言ってもらえるだけで。それだけで絶頂に達してしまう。理性なんて簡単にかき消してしまうほどの強い多幸感で脳みそが、心の中が満たされていく。
あたしの……そーちゃんの身体になったヒナの腰づかいはゆっくりとぎこちないものだったけど、そーちゃんと繋がっているという事実を実感しているだけで既に数えきれないほどの絶頂を感じて、その度に俺があたしに馴染んでいくのも感じてしまっていた。
(だ、だめっ♡♡ これ以上は、自分が自分じゃなくなっちゃいそうで……でもっ……♡♡♡♡)
それでも。自分がそーちゃんだったこととか、このままじゃあたしがヒナとして中出しされてしまうなんてこととか。そんなことがもうどうでもよくなるくらいに今のあたしは満たされてきっていた。もっと、もっと気持ちよくなりたい。あたしとして、ヒナとしての幸せを受け入れれば受け入れるほどにもっと気持ちよくなれて、だから——
「んっ……♡♡♡んむっ…………♡♡♡♡」
気づけばそーちゃんの背中を抱き寄せて、唇を同士を重ね合わせていた。ずっと夢見てきて、一人で練習なんかもしたことのある舌を絡ませての大人のキス。それをあたしの方からしたせいか、そーちゃんは一瞬驚いたような表情を見せたけど……すぐに顔を綻ばせて受け入れてくれた。
「ぷはっ……。えへへっ♡そーちゃん、やっとあたしのことを受け入れてくれる気になったんだね♡」
「……やだ、そーちゃんって呼ばないで」
「え?」
「ヒナって、ヒナって呼んで……♡♡そーちゃんの身体で、声で、あたしのことをヒナとして愛して……♡♡」
「……あたしみたい、っていうか本当にあたしになっちゃったんだね。でも……いいよ。そーちゃんが……いや、ヒナがここまでお願いしてくれてるんだからな。お望み通り『俺』として抱いてやるよ」
「っ~~~~♡♡♡♡」
全身に響くような低い声で囁かれて、今度はそーちゃんの方から唇を重ねられる。
(好き♡♡好きっ♡♡大好きっ♡♡すきぃっ♡♡♡♡)
もう自分がそーちゃんだったなんて自分でも信じられないくらいに、あたしは『あたし』に染まり切っていた。さっきまであんなに元の身体に戻らなきゃって思ってたのに、綾乃先輩のことが心配で仕方なかったはずなのに。
もう、今は全部がどうでもいい。こうしてそーちゃんと一緒にいることができて、繋がれて、愛され続けて。入れ替わって『あたし』になることができてよかったって、心の底からそう思えている。だって、そのおかげであたしはそーちゃんと一つになれたんだから……♡
「っ……!なんか来て……そ、そろそろ出ちゃいそうかも……っ!」
「いいよ♡♡キてっ♡♡だしてっ♡♡♡♡あたしをそーちゃんのお嫁さんにしてぇっ♡♡♡♡♡♡」
ぎゅっと、お互いに強く抱きしめ合って、おまんこの中に熱い何かがドクドクと注がれているのを感じる。
それが嬉しくて、幸せで、気持ちよくて。もう、何度目なのか分からないほどの絶頂に達しながら、あたしはそーちゃんの赤ちゃんを孕むためにおまんこをきつく締め付け続けていた——
***
あの日から1週間が経って、結局あたしとそーちゃんは……いや、あの事件に巻き込まれた人たちはみんな元の身体に戻れていないようだった。
今となってはあまり興味もないから詳しい話は知らないんだけど、花火大会で起きたあの出来事はどうやら大規模な集団発狂事件として世間を賑わせているらしい。警察が大勢集まるほどの騒ぎになったこともそうだけど、特に話題になっているのは事件に巻き込まれた人たちの一部が「身体が入れ替わった」と主張していることだった。
そう、"発狂"してるのは一部の人たちだけ。入れ替わった人たちは皆個人差はあれど次第に身体の記憶を読めるようになっていて、新しい身体を受け入れられなかった人たちだけがそんなことを主張して頭がおかしいと思われている、なんて噂を小耳に挟んでいた。
(まあ、誰がどうなってようと今はどうでもいいんだけどね。あたしにはそーちゃんさえいればそれでいいんだから)
一部の人たちには不幸だったのかもしれないけど、あたしにとってあの日のことは神様からの贈り物以外の何物でもなかった。
そう、あの日のことをきっかけに、念願かなってあたしはそーちゃんと付き合うことができたのだ。今日はそーちゃんの高校に学校見学に……もといデートに行くことになっていて、入れ替わる前は何度も歩いた駅までの道だというのに足取りが弾んで仕方がない。
「きゃっ!?」
そんなことを考えていた矢先、浮かれてしまっていたせいか曲がり角で人とぶつかってしまった。
ぶつかった相手は中年太りのおじさんで、対格差もあってあたしはしりもちをついてしまう。
「チッ、痛ってえな。気をつけろよクソガキ」
「……綾乃?」
無意識の内に、そんな言葉が口から零れ出ていた。
目の前にいるのは綾乃先輩とは似ても似つかない、あたしが嫌いなタイプのおじさんだった。それなのに、何故か一瞬その姿が彼女と重なって見えたのだ。
「はぁ?」
「い、いや、あの……ごめんなさい、人違いです」
あたしが言い終える前に、男は舌打ちと共にその場を後にしていった。そういえば綾乃先輩もあの花火大会にいて、結局誰と入れ替わってたのか知らないままだけど……。
(まさか、ね)
きっと、あたしの勘違いだろう。それに……もしそうだったとしても、もはやあたしには関係ないことだ。あたしにはそーちゃんさえいればそれでいいんだから。
だから、この心のモヤモヤもただの気のせいなんだと思うことにして、再び駅まで歩みを進めるのだった。