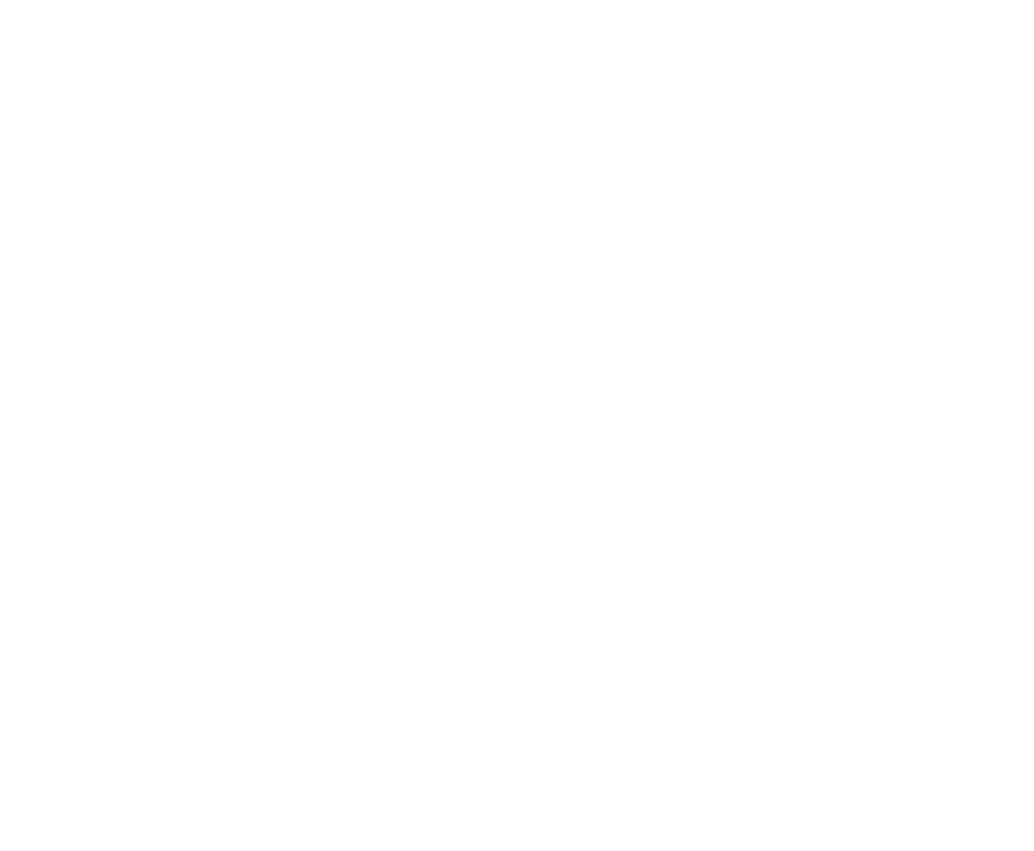俺がその人に出会ったのは、まだ高校に入学してから2週間くらいの、とある放課後のことだった。
「やあ、そこの君。突然だがサイエンス部に興味はないかい?」
制服の上から白衣を羽織る女性。肩あたりまで伸ばされた長くてすこしぼさっとした髪、知性を感じさせる眼鏡、細身でスレンダーな体型、そして周囲に漂うミステリアスな雰囲気。今まで出会った女性とは何かが違っていた。
「今まで入った新入生はみんな辞めたりいつの間にか来なくなったりしていて困っていたんだ。君のような可能性に溢れた部員が入ってくれると……って、話聞いてる?」
「あ、すみません」
俺は彼女につい見惚れてしまっていた。一目惚れ、というやつだ。付き合えるかなんてわからない、この人見るからに恋愛とか興味なさそうだし。それでもいい、俺はこの人に少しでもお近づきになりたかった。
「え、えっと、サイエンス部って、どんな、活動?してるんですか?」
「よくぞ聞いてくれた!話は理科室でゆっくりしようじゃないか。ついてきたまえ」
満面の笑みで手を引かれながら部室で歩く理科室に連れ込まれてしまった俺。初めてのボディタッチに心臓がバクバクだった俺に、部長は飲み物を出してくれた。なぜかそれはビーカーに入っていた。
「どうだい?サイエンス部っぽいだろう?遠慮せずぐいっと飲んでくれたまえよ」
「あ、はい。いただきます」
正直サイエンス部っぽいかはともかく、ビーカーに直接口をつけるのはなんとなく抵抗があったが、その時の俺は緊張してまともに考えることができず、一気にそれを飲み干してしまった。
「うわっ苦っ」
「まあ、そうだろうね」
それの味はお世辞にも美味と言えるものではなかった。
「なんか、ゴーヤに牛乳かけたみたいな味です」
「なるほど。そういう風に味覚に作用するんだね」
味に苦しむ俺の様子を興味深そうに観察しながら、彼女はメモを取る。その時俺は気づいた。
「あ、あの、もしかして俺のことを実験台にしてます?」
「ふっふっふ。バレてしまっては仕方ないね。これは私が調合した薬のひとつさ。効果についてはある程度推測はついているが、しっかり実験しないとね。さあ聞かせてくれ、君は今どんな感じだ?」
開き直ったのか全てを明かした彼女は俺に一気に近づいてきて、早口でまくしたててくる。近くで見ると顔立ちが整っていてかなり美人だ。
「顔立ちが整っていてかなり美人だ……って、何言ってるんだ俺」
心の中で押し留めていたはずの言葉が、自分の口から出ていた。
「おっと……まさか私の外見を褒められるとは思わなかったな。他に何か私について思っていることはあるかい?正直に全部言ってごらん?」
「ミステリアスな雰囲気が素敵で、一目惚れしました。怪しい薬飲まされて今それどころじゃないですけど……ま、待ってください!今のは口が勝手に!」
なぜか隠しておきたいことが全て口から漏れ出てしまうようになっていて、今さっき抱いたばかりの淡い恋心も一瞬で彼女にバレてしまう。
「ほんとはサイエンスとかよくわからないけど貴方にお近づきになりたいと思って……違う!違います!」
「ふふっ、もう遅いよ。どうやらこの薬は私の見立て通り、隠し事をできなくさせる効能が出るらしい。実験は成功だ。協力感謝するよ」
そんな薬、聞いたこともない。でも、実際にこうして体験してしまっていた俺は、きっと彼女は、何十万人に一人とかそう言うレベルの天才なんだと思った。
俺は恥ずかしさと、この人はやばいという危機感から勢いで走って逃げようと思った。でもそれは彼女に筒抜けだ。
「おっと、まあ落ち着きたまえ」
椅子から立ち上がった瞬間に手を掴まれ、そのまま椅子に戻され、しかも向き合う形にされた。恥ずかしくて目も合わせられない。
「さっきの言葉からするに、君は私に恋愛感情を抱いているんだろう?それなら都合がいい、私に協力してくれたら、君と、いわゆる恋人になってあげてもいい」
「……え?」
思わず顔を上げる。彼女の目は真剣そのもので、かつ、何か奥の方に、黒い情念のようなものを感じた。
「君の名前は?」
「もっ、森田友樹です!」
「森田君だね。君は今日から私の助手になってもらう……あ、申し遅れたね。私はサイエンス部部長、深山理胡。よろしく頼むよ」
「よ、よろしくお願いします」
この日から俺は、彼女の助手、というよりは実験台になった。これが、俺の人生の全てを変えてしまったのだ。
あれから半年ほど経った。俺は実験台としての生活にも慣れ、声が1分間だけ高くなる薬とか、体の柔軟性が上がって余裕で前屈ができるようになる薬とか、色々な薬を試され、たまに体調を崩しながらも部長のために精一杯尽くしてきた。その甲斐あってか結構親しくなれた。ただし、モルモットとして。
「さて、長らく待たせたが、今日はあの計画を遂行する日だ。これが終わったら君と恋人になるという約束も果たそう」
「……それは嬉しいんですけど、なんで俺縛られてるんですかね?」
そんな俺が、なぜか理科準備室に体を目隠しされたうえロープでぐるぐる巻きにした状態で寝かされている。まるで悪いことでもしたやつみたいになっているが、俺にはなんの罪もない。気づいたらこうなっていた。
「睡眠薬の効果が意外と短くてね、こうするしかなかったのさ、暴れて逃げ出されても困るしね」
「いやいや、今更もう俺逃げないですよ」
「今回の実験は事情が違うのさ。あとはこの薬を飲んでくれれば準備完了だ……と言ってもそのままでは飲めないか、口を開けてくれ、飲ませてあげよう」
先輩の態度からいつも通り不穏な雰囲気を感じつつも、いつも通りおとなしく従う。もう半年もモルモット生活したらこれくらい慣れてしまうものだ。
なんて思っていたら、あきらかに人間の口に入れるものではない金属製の筒みたいなものを入れられ、そこから薬品が流れ込んできた。咄嗟に俺はこぼさないようにそれを飲み干した。
「けほっ、けほっ、何なんですかいまの」
「漏斗だが?」
「漏斗だが?じゃないですよ!」
初対面の頃から薄々思っていたが、彼女は頭はいいがちょっと天然なところがあるようで、あらゆることをナチュラルに実験器具で行う癖があるようだ。頭はいいはずなのにそういうところが変なので、こうして自然にツッコミを入れられるほどまでになれたのだと思う。
「では、私は次の工程に取り掛かるからしばらく待っていてくれ。きっと意識が朦朧とするが、すぐに目覚めるさ」
「えっ、ちょっとどこ行くんですか!?」
彼女は大体いつも大切なことを説明してくれない。おそらく頭が良すぎて彼女の頭の中だけで話が進んでいて、俺に対して色々省いてしまっているものだという風に思う。というよりは、そう思わない限り本当に何を考えているのかわからない。そういうところもミステリアスで素敵だけど、でもやっぱり伝えてくれないとわからないことはいっぱいある。
「深山先輩は俺のこと、どう思って……あ……なんだ……これ……」
急に俺を襲うふわふわとした謎の感覚。先ほど言われた意識が朦朧とするという作用が出たらしい。全身から重さを感じなくなり、まるで体を捨て去って精神のみが浮いているような不思議な気分だった。しかし、すぐに何かに引っ張られ、地面に落ちるような感覚。
「うわあああっ!!……あれ?部長?」
意識がはっきりしてくると、目の前には見慣れた顔があった。
「お目覚めかな、乃々歌。いや、森田君かな?」
「……え……いや、俺は森田ですけど……」
俺が答えた途端、部長の顔がぱっと明るくなり、ガッツポーズを決めた。
「おおおお!成功だ!ついに完成したぞ!ありがとう森田君!君の協力のおかげだ!」
「は、はぁ」
部長は喜んでいるが正直俺は何が起こっているのかよくわかっていなかった。
「……ふふ、どうだい、その体は?」
「体……?」
そう言われて、自分の体を確認しようと下を見る。
「え。なにこれ?胸?それにこの服、女子の……」
見慣れない胸の膨らみがあり、そこにリボンが載っている。さらに下はスラックスではなくスカートになっている。そういえば、そもそも俺は理科準備室で縛られていたはずなのに、なんで体育館の近くにいるんだろう。
「な、何が起こってるんですか、これ」
「鏡を見ればわかるさ。ちょうど近くにあるからついてきたまえ」
部長に言われるがままついていくが、流石に不味そうなので俺だけは一時停止した。
「待ってください、そっち女子トイレですよ」
「今の君なら問題ないよ。早く来たまえ」
「え。でも……」
迷っていると手を引かれ、転びそうなのも気にせずに無理やり女子トイレに連れ込まれる。そこで洗面所の鏡を見ると、部長の隣にスポーティなポニーテールの、スタイルのいい美少女が映り込んでいた。しかし鏡の前にいるのは俺と部長のみ。ということは、まさか。
「え、俺、女の子になってる!?まさか性別を変える薬か何か飲ませましたか!?」
「うーん、当たらずとも遠からずと言ったところかな。君に、いや君たちに飲んでもらったのは、同じ薬品を飲んだもの同士の人格を交換する、というものだ」
「……え、ありえるんですか?そんなの」
「現にそうなっているだろう」
今まで色々な薬の実験台になっていたが、そんな非現実的な効果が現れたのは初めてだった。改めて深山理胡という人物の天才性を思い知らされてしまう。変だけど、本当にすごい人なんだ。
「その体は、私の幼馴染にして唯一の友人、笹原乃々歌のものだ」
「……え、幼馴染まで実験台にしたんですか?」
「それは違う。私はそもそも乃々歌を手に入れるために薬品の調合を続けていたんだ」
「……え、どういうことですか」
ずっと助手をしているのに、今まで一切教えてくれなかった、薬品作りの動機。彼女はそれを、どこか遠くの方を見つめるようにして語り始めた。
「私はずっと、笹川乃々歌が欲しかったのさ。幼馴染としてずっと一緒にいられると思っていたのに、乃々歌は別の友達を作ったり、彼氏を作ったりして、どんどん私から離れていく」
「ああ、確かにこの子、見るからに友達多そうですからね」
「……だからもう一度仲良くなるため、私は様々な策を練った。私には幸い、類稀なる薬品作りの才能があったからね。最初は効率的な疲労回復ドリンクやプロテインを研究し、スポーツに勤しむ彼女の役に立とうとしたが、その程度では仲の良い友達から抜け出せなかった。だから惚れ薬のようなものを作ったこともあったが、それを用いても彼女から私への感情は、『仲の良い幼馴染』の範疇を出ることはなかった」
途中からどんどんヒートアップしていく部長。きっと彼女は、この乃々歌という子に対して、ただの幼馴染ではない感情を抱いていたのだろう。やり方はどこかおかしい気がするが、その想いは本物だった。しかし、俺の中に一つの疑問が生まれた。
「……つまり部長はこの乃々歌さんのことが好きなんですよね?それならなんで俺と恋人になるなんて約束したんですか?」
「私は乃々歌に好きになってもらいたかった。私だけの乃々歌でいてほしかった。そのために使える方法をずっと模索し続けた。その末に私は辿り着いたんだよ。『私のことが本気で好きな乃々歌』を作り上げてしまえばいい、とね」
「……え?」
あまりの発想に、理解が追いつかなかった。天才というのは理解されないものであると、彼女が言っていたことがあるが、まさに今、俺の理解を超えてきた。
「全く予想外ではあったが、森田君という存在が大きな伴となった。君が抱いている私への恋慕。私のどんな実験にも付き合おうとする妄信的な姿勢。それを彼女にまるまる移植できないか……そうして生み出したのがこの薬品さ。『乃々歌の肉体』に『私に恋をする精神』を入れて、『私に恋をする乃々歌』を作り出す実験!それこそが私のこれまでの研究さ」
「……」
もう、言葉が出なかった。理解ができてないのか、呆れてしまったのか、自分でもよくわかっていなかった。でもひとつだけ、確信を持って言えることがあった。
「部長、やっぱり俺のこと、単なる実験台にしか思ってなかったんですね。正直、狂ってますよ」
「……まあ、それは否定しないさ」
「……でも、そんなところも好きです、部長。最初は見た目で一目惚れして、それでこの部活に入って。最初はすごい人だなってことしか思わなかったけど、時々親しみやすいところとかも見つかって……何よりさっきの、幼馴染への一途な想いを聞いて……もっと好きになりました」
彼女に何をされようとも、彼女がどんな思想を持っていようとも、俺の気持ちは一目惚れした日から変わらない。真っ直ぐな目で部長を見ると、彼女は静かに近づいてきて、その唇を俺の唇に当てた。
「君も大概、狂っているじゃないか」
その時の表情は、今まで俺に一度も見せたことのない、少女のような笑みだった。
「そうだ、君に一つ、試してもらいたいことがあったんだ」
「ひゃっ!何するんですか!?」
彼女は何かを思い出した途端、俺の胸を思いっきり揉んできた。思わず上擦った声が出てしまう。
「男性の快楽より女性の快楽は上回ると言われている。倍率については諸説あるがね。いまならそれも検証できるんじゃないかと思ってね……!」
「いやいやいや、待ってください」
「君に拒否権はないよ。それにしても全くこんなに大きく育って、バスケする時邪魔じゃないんだろうか」
俺の言葉を無視して胸を揉み続けられる。感覚としてはくすぐったさに近い。あと少し雑なので痛い。
「うーん、反応が薄いぞ……そうだ……あっちでもっと激しいことをしようか。気になるだろう、女の快感ってやつを……それに君は私が好きなら、『そういうこと』もしたいはずだ」
彼女は至近距離で、手でも言葉でも俺を責め立てる。当然、俺に逆らうという選択肢はない。
「……はい。その、やさしく、お願いします」
「ふふ、まあ、やれるだけやってみるさ」
そのままトイレの個室に詰め込まれる。当然そこは本来1人で入るスペースなのでとても狭く密着している。さらにお互いの体温や吐息でどんどん温度が上がっていく。そして彼女にされるがまま、下着を下ろされ、スカートを捲られた状態で便器に座らされる。柔らかいお尻に、冷たい便座が当たる。
「女子トイレに入るのも初な君には刺激が少々強いだろうが、実験のためだ、耐えてくれたまえ」
「いやいや、無茶言わないでくださいよ!」
冷静にツッコミを入れている俺だが、内心ではめちゃくちゃドキドキしている。こんな形とはいえ、好きな人と性的なことができる機会なのだ。……本当は男としてやりたかったが。
「覚悟はできたかい?始めるぞ」
「っ……なんか、濡れてる……?」
本来棒がついているはずの場所を触られる未知の感覚。部長の細くて長い指が、湿り気を帯びた股間に徐々に侵入してくる。
「なんか、変な感じですね、体の中に他人の指が入るって」
「ああ、男子はここには穴はないんだったね。まあ、初めては女でも慣れないよ」
さらっと部長の性事情を聞いてしまった気がするが、そこに突っ込むと怒られそうな気がするので、気づかないふりをしたまま、肉体から与えられる感覚を享受することにする。
「んっ……ふぅー、なんか、暑くなってきました」
「心拍数と体温が上がっているんだね。つまり、感じているってわけだ。わかるかい、このあたりがなんというか、収縮するような感覚があるだろう?」
「ここ……?」
部長に片手へその下あたりを触られながら、もう片方の手でその内側から触られる。確かにこの辺からきゅんとした感じがある。男性器は体の外にあったけど、女性の場合は体内にあるからこのような感覚になるのかも。
「よし、慣らしが終わったところだし、少し激しくいこうかな」
「……はぃ」
意地の悪い笑みを浮かべながら部長に言われたじろいでしまう俺。その伱を彼女は見逃さない。
「あっっっ!えっっ、なんだ!っこれっ、さっきと、ぜんぜんっ!っ!」
急に波のように何度も訪れる快感に頭の中が一瞬真っ白になる。さっきまでとは違い入ってくる指には力が入っており、俺の、乃々歌さんの体の中にある気持ち良いところを刺激されている。
「ふふふっ!どうだい、すごいだろう女性の快楽は!」
「あっ!まってっ、これぇ、こわいっ、あたまっ!へんになるっ、っ!っ!!」
さっきまでとは桁違いの速さで未知なる快感が身体中を駆け巡る。頭の中が何度も白黒している。
「あははは、頭なら元から変だろう気にするな!君は何も考えず快楽に身と委ねればいいのさ!」
「やぁぁぁ!!!まっ!はぁ、はぁん!やぁっ、んっぅっ!はぁ、なんか、あがって、きてっっ!!」
「少々早い気もするがフィニッシュといこうか。存分に気持ちよくなってもらおう!」
そう言ってさらに激しく、さらに奥まで、さっきまで一本だったはずの指は二本に増えて俺の中を掻き回す。その度に全身に電撃でも浴びせられたような衝撃と、下の方から何かが登ってくるような、ちょうど男だったら射精する寸前のような感覚がくる。
「あっあっあっ!!!ぃゃっ!くるっ!なんかきっっっっっっ!!!!!……ああっ、はぁ、はぁ…………はぁ……」
一瞬、頭の中が何もなくなって、体が何度か跳ねた。
「絶頂に達したようだね。どうだい?男性の肉体よりも気持ち良かっただろうか?」
「はぁ……はぁ……いまの、すごかった……」
「ふふっ、想像以上の反応だ……いいデータが取れたよ、ありがとう森田君」
そう言って、俺はもう一度キスをされた。全身が綿飴にでも包まれているような、甘い快感の余韻が残る。まさに夢見心地、まるで天に登るような感覚。そう、さっき薬を飲んだ時みたいな……あれ……これ……なんか、いしき……が……
「お、おい、森田君?しっか……て……い……」
気がついたら、俺は理科準備室に戻ってきていた。
「…‥身体中が痛い」
ところどころ物をぶつけたような痛みと、手首を縛られているあたりが特に痛い。周りを見ると、近くの書棚の本が落ちている。そういえば、目隠しが外れている。それにさっきと比べて場所がずれているように感じる。
でも俺は今の今まで部長と女子トイレでいちゃついていたはず。
「……え、まさか夢?ってことは……いや、あるかも。実はいい夢を見られる薬とか飲まされてたりして。あの人なら作れそうだし」
そんな噂をすればなんとやらで、理科室の扉が開き、部長も戻ってきた。
「ふぅ、危ないところだった……君は、森田君であっているね?」
「何言ってるんですか、俺が森田以外の誰に見えるんですか」
「やはりか、どうやら入れ替わり薬の効果時間はそう長くないらしい。改良が必要だね」
「……あれ、夢じゃなかったんだ」
「現実さ。まあ、夢のような時間ではあったがね」
どうやら、俺は本当に別の人と入れ替わっていたらしい。そうなるともしかしたらこの体の痛みは、俺の体になった乃々歌さんが拘束を解こうとしてついたものかもしれない。
「あ、部長、早くこれ解いてくださいよ」
「ああ、ごめん。忘れていたよ」
ロープを切ってもらい、固まっていた体をほぐしていると、どたどたと足音が聞こえてきた。そしてドアが勢いよく開くと、見覚えのある人物が現れた。
「……やっぱり、この部屋ね。どういうことか説明して、りこぴん」
「乃々歌!?」
すごい剣幕を放って部長に迫る彼女こそ、さっきまで自分と入れ替わっていた人物。笹原乃々歌その人だ。
「さっきの、夢って言われたけど、なんか見覚えある気がしたの。それできてみたら、あたしが見たのと同じ。理科準備室で、あたしが倒した本が散らばってて、しかもロープまで!」
「ま、待ってくれ乃々歌、これには事情が」
「何?あたしをこんなところに閉じ込めて、しかもあたしの体は勝手に女子トイレに行ってたし、妙にほてってたし、ねえ何したの?ちゃんと言ってよりこぴん……いや、理胡」
彼女は、少し悲しそうな顔をしていた。
「……実験だったのさ。体を入れ替える薬が完成したからね。でも森田君の他に飲んでくれる人がいなかったから、君なら協力してくれるかもと思って」
「……別に自分で飲めばいいんじゃないの?それに、私に協力してほしいなら、新しいスポーツドリンクなんて言わずに、ちゃんと隠さず実験のためって言ったら手伝ったのに。それにあんな縛って放置なんて……ほんとは私になんかするつもりだったんじゃないの?」
「いや、そんなことは」
いつも余裕綽々な態度の部長が、自身なさげに縮こまっていていたたまれない気持ちになる。幼馴染同士の話なので下手に援護射撃もできない。
「本当に?」
「……すまないことをした」
「……今までプロテインとか色々作ってくれてさ、それは実際良かったし感謝してるよ。……でも、ちょっと今回のは、ヤバいよ、理胡。前からそんな感じはあったけどさ、まああたし相手だからいいけど、程々にしておいた方がいいよ、本当」
「……ああ」
「もういいよ。じゃあね」
部長と、さらに俺のことを一瞥してから、彼女は去っていった。
重い空気が理科室の中に充満する。とりあえず何か励ましたほうがいいだろうか。
「……部長」
「すまないが森田君、1人にしてくれないか」
「……はい」
部長のこんな弱々しい姿を見たのは初めてだった。とても心配だったけど、彼女の望み通り、俺はこの場を去ることにした。
翌日、いつものように部室に行くと、そこには誰もいなかった。その翌日も、そのまた翌日も彼女は現れない。そんなある日、俺は廊下である人とすれ違った。
「……あ、理胡と一緒にいた人じゃん」
「……こんにちは」
先日入れ替わっていた乃々歌さんだ。話しかけられるとは思っていなくて、少し反応が遅れてしまった。それに、改めてその姿を見ると、あの日のことがフラッシュバックして申し訳ない気分になる。
「ねえ、あれから理胡が学校来てないみたいなんだけど、何か知らない?」
「……わかりません。連絡先も教えてもらってないですし」
「……そっか。あたし、ちょっと言いすぎちゃったかなーって思ってさ、次あったら謝ろうかなって思ってたんだけど」
「いや……こちらこそすみません、俺が止めていればこんなことには……」
「あはは、苦労してるね、君も。まあ、それはいいのよ。あれでもやっぱり幼馴染だしさ、いないと寂しいんだよね」
平時の乃々歌さんは、溌剌とした印象の人だった。それに、彼女なりに幼馴染は大事にしていることも窺えた。部長がやったことは、正直擁護しようがないとは思うけど、仲直りはしてもらったほうがよさそうだ。
その時、急に俺のスマホに一件の着信が入った。
「あ、すみません電話が」
知らない番号だが、とりあえず通話ボタンを押す。すると少し掠れた声がした。
「もりたくん……たすけてくれ……」
「部長!?」
一言だけ言って電話を切られてしまった。
そんなやりとりを横で聞いていた乃々歌さんは何かにピンと来たようだ。
「……ねえ。何か食べ物とか持ってる?」
「持ってますけど」
「じゃあそれ持って急いで一緒に理胡のうち行こう。場所はあたしが知ってるから」
「え!?でも授業は?」
「いいの。緊急事態だもん!」
どうやら深刻そうな感じだったので、俺は乃々歌さんに道案内してもらいながら部長の家にたどり着いた。
「おじゃまします!」
「お、おじゃましまーす」
乃々歌さんについていくと、様々な本や薬品が散らばった部屋の中で倒れている部長の姿があった。顔面蒼白で目にはものすごいクマができている。
「……お……来てくれたのか森田君……それに、乃々歌?」
「これ水!飲める?」
「……うん」
「森田君、だっけ?何か食べ物あげて」
「あっはい!」
まるで救急救命士のように適切な処置をする乃々歌さんの指示に従い、さっき購買で買ったメロンパンを部長に渡す。それを食べ終わるまで待つと、ようやく部長が元気を取り戻したようだ。
「いやあ、迷惑をかけたね2人とも。実験に夢中になって3日間徹夜してしまった……」
「もう、りこぴんは昔からそうなんだから!無茶しないでって言ってるのに!」
「うん、ごめん乃々歌」
「それと、この前はごめんね、ちょっと言い過ぎた。ショックで学校来てないんじゃないかって心配してたんだよ」
「いや、悪いのは私だ。あの薬についても乃々歌にはしっかり理解してもらう必要があった」
「じゃあ、仲直りってことで」
「別に喧嘩はしていない気がするが……まあいいか」
そう言って、2人は握手を交わした。一度は途切れかけたけど、長年の積み重ねが2人を結んでいるかもしれないと、感動すら覚えたその時。
「ありがとう、君がここに来てくれて手間が省けたよ。乃々歌」
「なに……これ……り……こ……」
部長が握手した状態で手をホールドし、不意打ちでもう片方の手に持っていた注射器を打ち込んだのである。
「やはり血管に直接投与した方が効きやすいね」
「……部長、なにやってるんですか?」
「喜べ森田君。改良版の薬が完成した。あとはこれを君に投与すれば、計画は完璧だ」
部長は、友人に騙し討ちのような方法で薬品を使った行為には何の悪びれることもなく、平然と俺に言い放った。
「今仲直りしようとしてたじゃないですか。嫌われたわけじゃないんだからこんな無理やりするのは流石にひどくないですか」
「だとしても、結局彼女が私を好きになることはない。それに……私は気づいたんだ」
おもむろに歩き出した彼女は、その白い手の上に、俺の顎を乗せるように置いた。
「あいにく私は男性には一才興味が湧かないが、それはそれとして君個人のことはとても気に入っている。だからもし君が、これを使ってもいいというなら、生まれ変わった君と、恋人として生きたいと思っている」
「……俺と、恋人に……」
「もし君が……そう、人道や道徳といったものを取るのならば、乃々歌のことは解放しよう。しばらく君への人体実験も中止だ、君というファクターがあまり重要でなくなるからね。別のアプローチで私は彼女を手に入れるため再びゼロから研究だ」
「……俺は……」
「どうする?私はどちらでも良い。君の選択に委ねようじゃないか。ちなみに、これは理論上、永続的に人格を交換できる代わりに、1度しか使えないつくりになっている。決断できるのは今だけだ」
まるで天使と悪魔のような選択肢。乃々歌さんの人となりがなんとなくわかってしまった以上、彼女への申し訳なさはあるし、二度とこの体には戻れなくなるのは、すなわち俺の過去全てへの決別になる。
……しかし、すでに俺の心に迷いはなかった。なんのために俺がこの部活に入ったのか、それは……。
それから、数日後。俺はいつものように理科室に来ていた。
「俺、サイエンス部やめようと思います」
「おや、それは残念だ。他にやりたい部活でもあるのかい?」
「はい、バスケ部に入ろうと思います。今までやってなかったんですけど、なんかやる気になっちゃいまして」
「そうか。これまで助手をしてくれてありがとう、バスケ部でも励んでくれたまえ」
「はい!お世話になりました!」
爽やかな顔で去っていく森田友樹を見送る俺たち。自分を見送るとは、なんとも変な感覚だが、もう、あれは自分ではないのだ。とはいえ、あの部長がこんなにあっさり退部を許すとは思わなかった。
「引き止めなくてよかったの?中身は乃々歌さんなのに」
「ああ、いいんだ。今となってはそこまで執着する理由もない。私が好きなのは体だけだったのかもしれないな。最低な女だと罵ってくれたまえよ」
「そんなこと言ったら、『あたし』は嫌いになるかもしれないけど、『俺』はそれでも好きですよ、部長」
「ぷっ……あっははは!」
俺が返した言葉に、自嘲するような顔だった部長が高笑いし出した。
「本当に君は狂っているよ!……最高だ、私は君のそういうところが好きだ!」
「俺も……いや、あたしも大好きだよっ、理胡のこと」
満足気に笑う彼女の顔を見て、俺はつくづく、彼女に出会ってよかったと思う。人生は丸ごと変わっちゃったけれど、ずっとそばにいられるのなら。
「さあ、今日の実験を始めるぞ!助手として、恋人として、私を支えてくれたまえよ!」
「言われなくても、ずーっとそうするつもりだよ、部長」
これにときめいた方はぜひ、今年の夏コミで出す予定の「先輩後輩入れ替わり合同」もよろしくお願いします!(ダイマ)