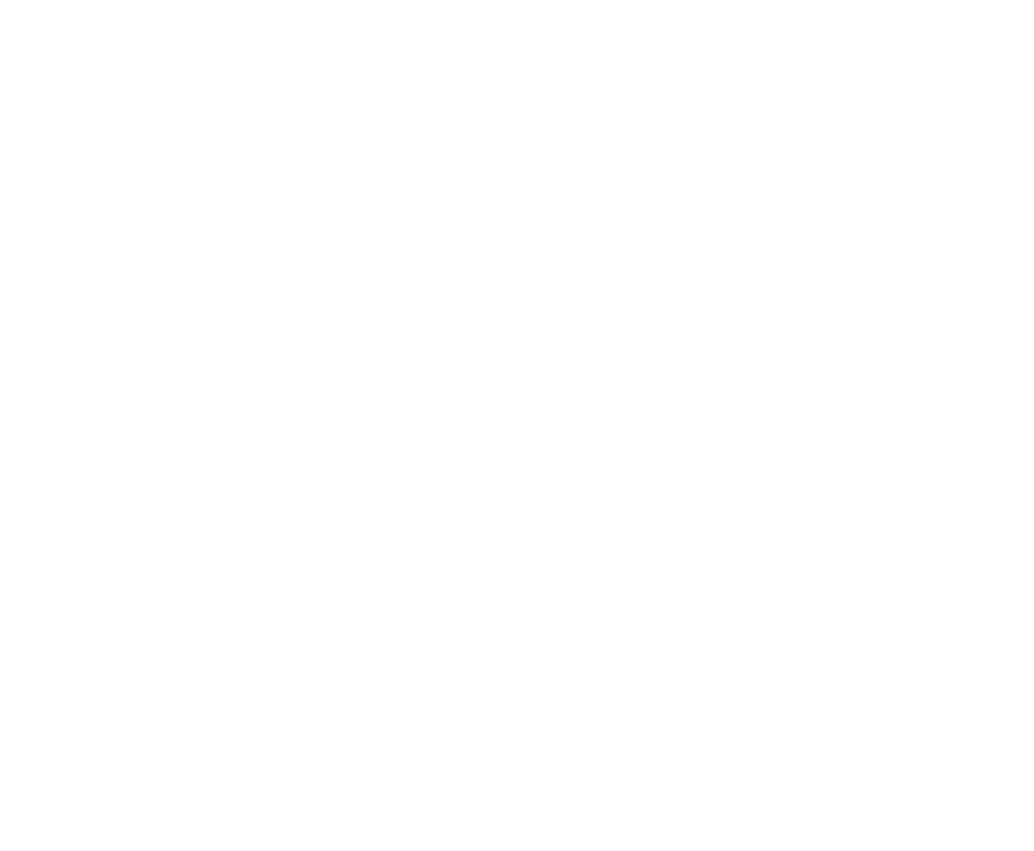「好きなひとと絶対に結ばれるおまじない?」
「うん。とっても簡単なおまじないなんだけど、これをすると好きなひとと両想いになれるんだって。けっこう効き目あるみたいだよ?」
「へえー、そんなのあるんだ」
「隣のクラスのマリちゃんとかレイちゃんとか、これで好きなひとと両想いになれたって言ってたよ」
「すごーい! あたしにも教えて教えて!」
「いいよ。とはいっても本当に簡単でね──」
※※※※※※※※※※
「ふぁ~あ……」
朝の通学路。
けだるい眠気を感じていたオレだったが、不意にとある女子から声をかけられて一気に目が覚める。
「大志、おはよーっ!」
「おっす……」
スラリと背の高い彼女の顔は見ずに、オレは気の抜けた挨拶を返す。女子はお構いなしに太陽みたいな明るい声で話しかけてくる。
「どうしたの? なんだか元気ないじゃん! もしかして具合悪い?」
「ハァ……別に、これが平常運転だよ」
「そっかあ。そういえば大志って、小っちゃい頃からずっと朝弱かったもんね」
「お前も、朝っぱらからやかましいのは相変わらずだな……」
「夏休みのラジオ体操の時なんか、いっつもボクが起こしに行ってたよね」
「…………」
オレのことを見下ろして喋るこの女子の名前は涼。オレの幼馴染だ。
同じ幼稚園に通っていて、家も近所だったオレたちは、いつの頃からか自然とお互いの家を行き来して遊ぶようになっていた。小学校に上がってからは同じミニバスチームに入っていて、一緒に汗を流した。涼がオレの家に泊まった時は、二人で風呂に入ってバカ騒ぎをして、母ちゃんにこっぴどく叱られたこともあった。
そんなオレが涼に対して強いコンプレックスを抱くようになったのは、中学に上がってからだ。思春期の訪れとともに、涼への淡い恋心を自覚した途端、自分がチンケな存在に思えてしまったのだ。
涼はとにかく華があった。背が高く顔も整っていてとてもスマートなのだけれど、どこか人懐っこくて明るくてちょっと抜けているところもあって、男子からも女子からも好かれるキャラクターをしていた。また、涼は中学時代そして高校でも一年生の時から女子バスケ部のエースとして活躍していた。小学校高学年の時以来身長が止まってしまった、万年補欠のオレと違って。
涼はすっかりクラスの、いや、学校の人気者になっていた。つい十年くらい前は一緒にパンツ一丁でバカ騒ぎをしていたボーイッシュな女の子が、随分と遠くの存在になってしまったように感じていた。
しかし涼は、オレの気持ちを知ってか知らずか、今でも気さくに声をかけてくれる。
オレの隣で彼女はため息をついた。
「あ~来週からテストかぁ。ねえ大志、一緒にテスト勉強やろうよ~」
「……なんで?」
「ボクが頭良くないって知ってるでしょ? 一般で入った大志と違ってボクはスポーツ推薦だし」
「そうじゃなくて……なんでオレなんだよ。お前ならオレより頭の良い友達とか、女バスのやつらとか、一緒に勉強する相手なんて他にもたくさん居るだろうが」
「いや、でもボクは──」
「うちのキャプテンとかどうだ?」
オレの所属する男子バスケ部の先輩──キャプテンは医学部志望で、全国模試で上位に食い込むほど頭が良い。勉強ができて、バスケが上手で、リーダーシップがあって、背も高い。そんなだから、当然のように女子からはモテる。
オレは苦笑しながら涼に問いかけた。
「涼、文化祭の時に二人で仲良さそうに話してたじゃないか?」
「……そ、それは別に関係ないじゃん!」
「…………」
涼は立ち止まり、拗ねたように口を尖らせた。
オレは彼女に冷ややかな視線を向ける。
……本当は、オレだって涼とテスト勉強をしたいし、昔みたいに素直に話がしたいし、もし叶うなら恋人になって手を繋いで歩きたい。しかし、今のオレと涼ではとても釣り合わない。少なくともオレはそう感じていた。
どうせこの想いは叶わないし、適わない。
そう、涼が付き合うのはきっと、キャプテンみたいな全てがイケてる男だろう。
そして、オレは言った。
「オレは、遠慮させてもらうよ……」
「あっ、待ってよ大志!」
オレは涼を待たず、さっさと歩き始めた。
涼の慌てた声が背後から聞こえてきた。
※※※※※※※※※※
その時までのオレたちは、昔と比べるとぎこちない間柄だった。
転機は、妹のクラスで流行っているという「おまじない」の話を聞いたことだった。
小学生の妹曰く「好きな相手と絶対に結ばれるおまじない」だそうだ。
いつものオレだったら、子供の微笑ましい噂話として片付けていただろうが、その時は違った。これまでは奇跡的に、涼に彼氏ができたという話を聞いたことはなかったし、本人から誰かと付き合い始めたという報告を受けたこともなかった。だが、あれだけの人気者──彼氏ができるのは時間の問題だろうと思っていた。そして、朝の会話での涼の反応だ。
オレは「縋れるものならば」と思って、その「おまじない」を実行することにした。
夜、オレは自分の部屋で涼の顔を思い浮かべながら名前をつぶやいた。
「涼、涼、涼、涼、涼、涼、涼……」
両想いになりたい相手の顔を思い浮かべて、きっちり七回。それより多くても少なくてもダメらしい。
残る工程は、なんと「寝るだけ」だそうだ。なんとも拍子抜けする内容だ。
オレはベッドに横になって目を閉じた。
正直なところ、オレも心の底から「おまじない」のことを信じてはいなかった。というより、どこかハズレの宝くじを買うような感覚で、気休めのつもりだった。
(こんなので涼と付き合えるのかよ。というか「結ばれる」って表現が抽象的すぎるだろ…………んっ?)
すると、突然猛烈な眠気に襲われた。
(あ……なんだこれ…………眠っ………………)
オレの意識はあっという間に朦朧としていき、まどろみの中へ落ちていった。
※※※※※※※※※※
「…………んゆ?」
オレは目覚めた。
枕元にスマホが置いてあったので、それを手に取って時刻を確認する。
どうやら横になってからまだ一時間も経っていないようだった。
「──あれ?」
そこでオレは違和感に気付いた。
スマホの待ち受け画面が、いつもと違っているのだ。
さらによく確かめてみると、手に持っているスマホはオレのものではなかった。
もっといえば、横になっているのはオレのベッドではないし、そもそもここはオレの部屋じゃない。
だが、その部屋に見覚えがあった。ある幼馴染の部屋の雰囲気に似ていたのだ。
「ここって、もしかして……」
スマホを持つ手も、オレの手ではなかった。
オレはベッドから起き上がって、部屋に置かれた姿見の前に立って、自分の姿を確認した。
鏡の中では、涼がこわばった表情でオレのことを見ていた。
「りょ、涼…………」
オレは、鏡の前で棒立ちのまま、しばらくその姿を眺めた。
少し茶色がかった黒髪のショートヘア。くりっとした目。まっすぐ通った鼻筋。ほんのりピンク色の頬。ふっくらとしていて潤いのある唇は、触らずとも柔らかさが伝わってきた。
涼は、スポーツメーカーのロゴが入ったノースリーブのTシャツにハーフパンツ姿だった。
ふと、鏡に映る涼がどこか不安そうな表情を見せた気がして、オレは思わず手を伸ばして鏡に触れた。ひんやりとした鏡の感触がして、オレと涼の手のひらが重なった。じんわりと汗をかいていた手のひらが滑って、オレたちの手はすぐに離れた。
オレは、鏡に顔を近づけた。
(涼の顔が……こんなに近くに……)
長いまつ毛や瞳の輝き、キメ細やかな肌、普段は目立たないにきびまではっきりと見て分かる。
胸の鼓動が速くなる。漏れ出た生温かい吐息で、鏡がわずかに曇る。
「涼……」
さらに顔を近づけて、姿見に映った涼とキスをした。
唇に感じたのは鏡の冷たさだったが、心では涼を何よりも近くに感じることができた気がした。
唇を離すと、透明な糸が口から伸びた。オレは慎重に手で口元を拭った。
「ん……はぁ……」
改めて目の前に居る涼の姿を見つめる。彼女は目の前の光景が信じられないといった表情だ。
オレは言い聞かせるようにつぶやいた。
「そうだ。オレ、きっとまだ夢を見てるんだな……」
オレが涼になる夢を見るなんて……「おまじない」っていうより暗示の一種だな。
そう思って、オレは自嘲気味に微笑んだ。
オレは置いていたスマホを手に取って、涼の姿を写真に収めようと思った。
※※※※※※※※※※
スマホを見たオレは声を漏らした。
「わっ!?」
着信が来ていたのだ。表示された相手の名前はなんと、オレ。
そこでオレは、涼がオレの身体に入っているという可能性に気付いた。
(そうか……オレが涼になってるってことは、涼がオレになってるってことなのか……?)
オレはその場に正座をして、呼吸を整え、恐る恐る通話に出た。
向こうからは涼の──オレの声が聞こえた。
『大志ぃ! やっと出てくれたぁ!』
「……え、えっと」
『大志だよね!? 今、ボクの身体になってるよねっ!?』
「おう……涼か?」
『そうだよ! ボクだよ! ボク、大志になっちゃったんだよぉ!』
電話口から聞こえる男の声は確かにオレのものだが、喋り方や雰囲気はどう聞いても涼のものだった。
どうやらオレの身体になった涼は、激しく動揺している様子だ。
『目が覚めたら大志の部屋に居て、鏡を見たら大志になってて、ボク、もうどうしたらいいか分かんなくて……』
「涼、大丈夫か?」
『おばさんやおじさんになんて言えばいいか分かんないし……そもそも言っていいのかも分かんなくて……自分のスマホに何回かけても返事がないから……ボク、すっごく不安だったんだよぉ~~!』
「わ、悪い……」
『大志ぃ~~!』
涼は半ベソ状態だった。
まさか涼の姿に見惚れていて気付かなかったとは言えず、オレは曖昧な返事をした。
すると彼女は不安そうに確認してきた。
『ボクたち……入れ替わっちゃったってこと?』
「そう、みたいだな……夢じゃないよなコレ?」
『たぶん……』
「…………」
『……元に戻れるかなぁ?』
「さあ…………」
オレは下唇を噛んだ。
心当たりはある。例の「おまじない」のせいで、オレと涼は入れ替わったのかもしれない。
しかし、「おまじない」の効果は「好きな相手と絶対に結ばれる」というものであるハズだ。
疑問に思ったオレは考えを巡らせる。
「…………」
『……ねえ』
「………………」
『大志ぃ……あの…………こんな時にこんなこと聞くのも、ちょっとアレなんだけど、聞いてもいいかな?』
この状況をどうしたものか考えるオレが黙ったままでいると、涼が困ったような口調で言ってきた。
「ん。どうした?」
『あのさ……男の子ってさ────あ、いや…………』
「……涼?」
『あ、違うのっ……えっとね、そのぉ……男の子の…………アレって────』
「──アレ?」
涼が何やら口ごもっていると、急に涼の声が遠くなった。
電波が悪くなったのかと思って画面を確認しようとするが、今度は視界が暗くなった。否応なしに瞼が下がってきたのだ。
(なんだ……!? また……眠気が…………)
オレはまたしても急激な睡魔に見舞われ、刈り取られるように意識を失った。
※※※※※※※※※※
※※※※※※※※※※
それから一か月が過ぎた。
「大志、おはよーっ!」
「おう。おはよう」
通学路で合流した涼の元気な顔を見ながら、オレは挨拶を返した。
もちろん、オレはオレの身体、涼は涼の身体だ。
あの夜、目を覚ましたオレたちは元の身体に戻っていた。すぐさま連絡を取って、二人とも元の身体に戻ったことと、先程の体験が夢でないことを確かめ合った。
元に戻れた原因は不明だったが、オレたちはほっと胸を撫で下ろした……のだが、数日後にオレたちはまた入れ替わってしまった。
二回目となればさすがに一回目よりも落ち着いているもので、オレと涼は速攻で連絡を取った。一時間くらいが経ち、またしても気を失ってしまった後、オレたちは元の身体に戻った。
そんなこんなで一か月経ったが、入れ替わりの現象は今も続いている。
そして、分かったことがいくつかある。
入れ替わりは数日に一回、少なくとも週に一回のペースで発生した。タイミングはランダム。家、学校、外出先でも入れ替わりは起こった。入れ替わっている時間は数十分から長くても三時間程。元に戻るタイミングも不明瞭で、いつの間にか意識を失っていて目が覚めると自分の身体に戻っているのである。
「昨日のおばさんのからあげ、とってもおいしかったよ!」
「そりゃよかったな」
そう言って涼は屈託なくはにかんだ。
当初はかなり戸惑っていたが、案外人間というものは環境に順応していくものだ。『入れ替わったか……』と気づくと、すぐにお互いに連絡やサインを送り合う。そして、他人に気付かれないように相手のフリをするという取り決めをしている。
あれだけ不安そうにしていた涼も、今では暢気だ。
「あんまりおいしくていっぱい食べちゃったんだけど、おばさんもおじさんも加奈ちゃんもなんだかびっくりしてたよ」
「おいおい大丈夫かよ。バレなかっただろうな?」
「大丈夫だって! あはははっ!」
「…………」
「……た、たぶん大丈夫だって! っていうか、大志だってちゃんとボクのフリできてるの?」
「まあ……それなりに」
「……ふーん」
なんだよその目は……!
まあ、自己評価ではあるが、長くコイツを目で追ってきただけあって、わりと違和感なく「涼」を演じることができているんじゃないかと思う。涼の家族や友達から白い目で見られるようなボロを出したこともない。
ただ……一回、電車に乗っている時に大股開きで座っていることに気付いて、慌てて脚を閉じたことは言わないでおこう。あの時の客の男どもの視線ときたら、思い出すだけでも寒気がしてくる。
きっと涼もオレに言わないだけでそれなりにやらかしているんだろうし、ここはお互い様だな。
ふと、涼がつぶやいた。
「それにしても、これっていつまで続くんだろうね?」
「うーん……そればっかりは、どうも……」
オレは歯切れ悪く答えた。
入れ替わりが起こるようになった原因は恐らくオレの「おまじない」だろう。入れ替わった状態で同じ「おまじない」をすれば、入れ替わりは起こらなくなるんじゃないかと思って何度か試してみたが、今のところ効果はない。
もしかしたら、好きな相手と結ばれたら、この現象は収まるのかもしれない。なんて思うこともある。
入れ替わりが起こるようになってからは、わりと自然に涼と話すことができるようになっていた。コンプレックスが完全に払拭されたわけではないが、涼の姿になった自分を見ると、なんだか涼と心の距離が近くなったような気がした。無邪気だった昔みたいに。
とはいえ……まさか……言えるわけないよな……
オレが頭を抱えると、涼が顔を覗き込んで尋ねてきた。
「た、大志……トイレとか、どうしてる?」
「……極力、我慢はしてる。だけど生理現象だから仕方ないだろ」
「だ、だよね」
実にもじもじしている。
ああ……まあ、小の時は男性器を手で触らなきゃいけないしな。
「まあ……頑張れ」
「あっ、あとさっ! ボ、ボクの身体で変なことしてないよね? はだっ、裸とか見てたら怒るよっ!?」
涼はすっかり顔を赤くしていた。
オレは、彼女の視線から目を逸らして答える。
「だ、誰がお前なんかで興奮するかよ……」
おいおいこの童貞が……思ってもないことを。素直になれよ。……なりてえよ。
案の定、涼は怒涛の猛抗議をしてくる。
「なんだってぇ!? ボ、ボクだって現役の女子高生なんだぞ! 女の子の身体になってるのに興奮しないって、もしかして大志って……男が好きとか、そういう感じなのっ!?」
「バーカ。オレだってかわいい女の子が好きだ。ただ、お前の凹凸の少ない身体なんかじゃ興奮しないって意味だよ」
「これから大きくなるもん……」
「というか……お前こそオレの身体で変なことするなよな!」
「そ、そんなことするわけないじゃん! 大志のヘンタイ! あっかんベ~だ!」
※※※※※※※※※※
また思ってもないことを言って彼女を傷つけてしまった。
とっとと正直に告白してしまえばいいのに。
だけど、胸の内を打ち明けられないのは、入れ替わりのせいだ……
「涼の身体……綺麗だ……胸は大きくは無いけど、形はいいし……んっ!?」
涼の部屋の中、オレは生まれたままの姿になった涼を見つめる。確かに慎ましい胸だが、男とは明らかに違う膨らみがある。
オレは指で軽く乳首をつねった。ビクッと肩が跳ね上がり、背徳感と罪悪感をデコレートした甘い疼きがじんわり広がっていく。
両の乳首を指で弄ると、鏡の中の表情がどんどんとろけていく。涼の家族も友達も、もしかしたら涼本人も見たことがないであろう、せつなくて色っぽい表情を浮かべた自分を見ると、胸がいっぱいになる。
そして、こらえきれなくなったオレは、涼の口調を真似てこんなことをささやいてしまう。
「た、大志……大好きだよ」
自分で発した言葉が鼓膜を震わせ、心を揺さぶる。オレの手は胸元から下腹部、恥丘の方へと移動していく。
溢れ出る想い──身勝手なセリフを、鏡の中に居る涼へ向けて吐き出していく。
「こ……子供の頃からずっと、ずっと大志のことだけを見てきたんだよ。もしかしたら大志は、男の子みたいなボクのことなんて好きじゃないかもしれないけど……ボクは、大志のことを想うだけで、ココがこんなに濡れちゃうんだぁ」
湿った割れ目に指で触れる。
ぬちゃ、という音を立てると、背筋が一気にゾクゾクした。
「わっ!? あははぁ……ごめんね、こんなエッチな女の子で……」
そのまま、オレは涼の秘部を指で弄っていく。本人にしか許されないであろう聖域を、オレみたいなチビでカッコ悪い男が踏み荒らしていると思うと、申し訳なさや卑屈な気持ちとともにどうしようもなく快感がこみ上げてくる。
鏡の中の涼が縋るような眼差しをオレに向けてくる。
「ひゃんっ! た、大志ぃ……!」
片手で割れ目を触りながら、オレはもう片方の手を伸ばして涼に触れる。女の蜜がとろりと鏡を伝う。女体がもたらす快楽に悶えながら、決して届かない鏡の向こうの相手へ想いを伝える。
「大好きだよ。ボク、大志のお嫁さんになりたいんだ。ずっとずっとそばに居たいよ……だからぁ……イカせてぇ!」
指の動きは速くなり、涼の身体は絶頂を迎える。
「ああ……涼、涼、涼っ! ああんっ!」
しかし、男の射精と違って、押したり引いたりするように涼の身体は何度も快感に弄ばれた。どこからどこまでが絶頂の境目なのか見当もつかなかった。
「はあ……はあ…………」
鏡の前で起き上がり、呼吸を整える。
この胸の鼓動さえも、涼の身体なんだと意識してしまって興奮してしまう。
オレは冷静な頭で、濡らしてしまった涼の身体や鏡をタオルで拭いていく。
「──ったく、涼の身体で何やってんだオレは……」
なんとも情けない気持ちで、オレはひとりごとを漏らした。
こんなことをしてる暇があったらとっとと告白してしまえ。だけど、もし告白したことで今の関係が崩れてしまったら。オレが涼の身体でこんなことをしていると知られてしまったら。付き合うどころか、絶交を言い渡されてもおかしくない。
だからせめて、この夢のようなひとときだけでも、オレへの愛の言葉をささやいてほしい。そんな歪んだ願いを捨てきれず、オレは涼の身体で女の快楽を味わってしまう。
「そろそろか……」
オレはスマホを手に取り、自分のスマホへメッセージを送るのだった。
※※※※※※※※※※
──大志が涼の身体で女体の快感に浸っている頃、涼は……
「りょ、涼……! ボクの、じゃなくてオレの彼女……いや奥さんになってくれ!
いいか、お前に拒否権とかないからな?
女の子っぽくないとか、そんなの気にするな。オレはありのままのお前が好きだ。お前の魅力なら何個でも言えるぞ。
ずっと、ずっと前からお前は、オレだけのお姫様なんだ!
だから……オレから一瞬たりとも目を離すなよ!」
部屋にある鏡に向かって壁ドンしながら、大志の身体でそんなことを言っていた。
キザな口調で澄ました表情を浮かべていた涼だったが、数秒すると、ベッドの枕に顔を埋めて叫んでいた。
「って違う違う違う~! 大志はこんなこと言わないし、言ってくれるハズないよぉ~~!」
大志の身体になった涼は、耳まで真っ赤にして恥ずかしそうにしていた。
(変なことしないでって自分で言っておきながら……ボク、大志の身体で何やってんのさ)
奇しくも、涼も幼馴染の大志に対して恋心を秘めていた。もっとも、彼女の場合は大志よりずっと前から幼馴染の男の子に対して友情以上の気持ちを持っていた。
そして彼女もまたコンプレックスを抱えていた。
(凹凸の少ない身体、かぁ……これでもほんのちょっとだけ大きくなってるんだけどね……ああ、背なんかより胸とかお尻に栄養が行ってくれればよかったのに……)
涼はため息をついて項垂れた。
入れ替わりが起こるようになってから、幼馴染との距離が少し縮まった──戻ったような気持ちでいたが、彼女もまた告白をするまでの踏ん切りはついていなかった。
女の子らしくない自分では、大志の恋人には相応しくないのではないか。今さら無理をして女の子らしく振る舞ったところで、彼は元の自分を知っているから、気持ち悪いと思われるんじゃないか。そんな葛藤が涼の中にはあった。
鏡に映る自分の姿を見つめ、涼はふと思った。
(いっそのこと……今のボクが大志のことを押し倒して既成事実を作っちゃえば……って、あーそっか、ボクの身体も結構力あるからなあ。大志の身体とどっこいどっこいかなあ。う~ん、何かいい方法ないかなあ……)
「──あっ」
すると、盛り上がった股間が嫌でも目に飛び込んで来た。まるでパンツを頭に被せられた大志が「苦しい! 苦しい!」と必死に救難信号を出しているかのように思えた。
涼は、生唾を呑んでパンツを下ろした。
「たっ、大志のおちんちん……また大きくなっちゃってる」
高らかに勃起している男性器を、涼は食い入るように見つめる。
入れ替わるようになってから、こういったことが何度かあった。
「大志って背は小っちゃいけど……こっちはすごく立派だよね」
生で見る勃起した男性器は大志のものが初めてだったので、比較対象などなかったが、涼は大志の肉棒を男性の中でも大きい部類に入るのだろうと考えていた。
涼は、指で作った輪の向こうにある肉棒を眺めながら妄想する。
「こ、これがボクのおまんこに挿入ったら、どうなっちゃうんだろう……!?」
(それにしても男の子ってすごいや。こ、これを女の子にズボって挿入れたら、とっても気持ちいいんだろうなあ……)
そんなふうに想像を膨らませると、呼応するように肉棒もさらに熱く膨れ上がっていく。
獣のような呼吸で、目を血走らせながら、涼は近くに置いてあったティッシュ箱に手を伸ばした。
「ふぅー……し、仕方ないよね……大志は男の子で、今のボクは大志なんだから……えへへっ」
涼は慎重な手つきで勃起した男性器を持った。
その時、枕元のスマホが震えた。
涼はびっくりして飛び上がって、スマホを覗き込んだ。
『いつ戻ってもいいように準備しとけ』
『あとオレの身体に変なことするなよ?』
『まあ、お前なら大丈夫か』
その文面に、涼の胸の奥がチクリと疼く。
しかし、男としての快感を覚えてしまった彼女は、射精欲に抗えなかった。
「ごめんね、大志……でも、もうビンビンになっちゃってるからぁ……!」
勃起した男性器を不器用にしごきながら、彼女は幼馴染の顔を思い浮かべて、射精の快楽に浸るのだった。
※※※※※※※※※※
『涼……』
『大志、大志ぃ……!』
──自分の身体だとどうしても想いを打ち明けられない二人が、お互いの身体を熱く交わらせるのは、まだもう少し先の話。
いかがでしたでしょうか?
お楽しみいただけたのなら幸いです。
幼馴染の男女の入れ替わりということで、じれったくてピュアな部分が強く出ている気がします。二人とも拗らせてはいますが。二人には「お前ら早よくっつけや」と言ってあげたいですねえ。
10年近くROMっていた自分がこのような企画に参加できるようになるとはあの頃は想像もしていませんでした。感無量です。
改めて、本当にありがとうございました。