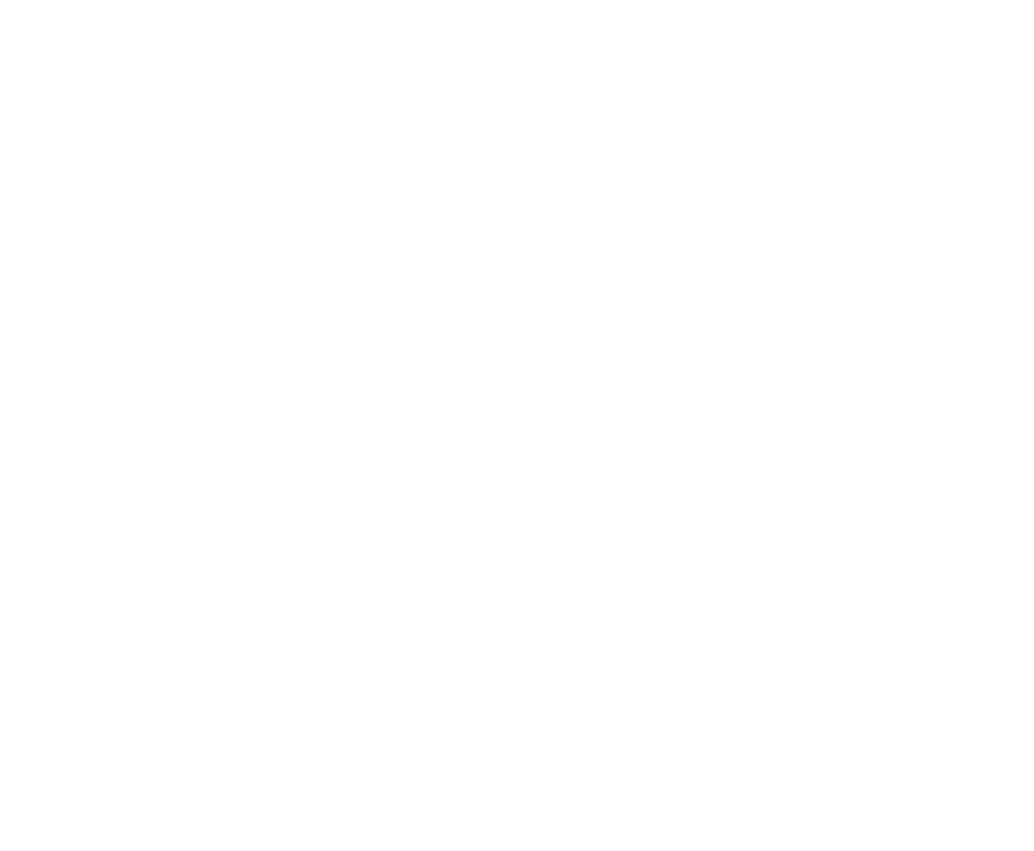口の中に徐々に広がっていく、酸味にも似た圧迫感。
空気を大きく吸い込み、それと同じリズムを意識して息を吐き出す。今できる限りの大きな深呼吸を繰り返す。
普段なら楽に走破できる道。ほんの少し軽い荷物が増えたところで問題ないとタカをくくっていたが、そう簡単にはいかなかった。
だが、投げ出すわけにはいかない。額に流れる汗も拭わず自転車のペダルを踏み続ける。
「蒼ちゃん……大丈夫……?」
後ろから俺こと
「心配すんな! ちゃんと掴まってろ!」
前を向いたまま、反射的に怒鳴るように返事をした後で少し後悔。急に大声を出してしまった。あいつをビビらせてしまったか。
だが朱音は、俺の腰に回した腕をより強く締める。
朱音の身体がより近づいたことにドキッとして、それを誤魔化すようにペダルをさらに速く回す。
「わっ! すごい! 速くなった!」
「ど、どうだ! このままぶっと飛ばすぜ!」
朱音の無邪気な声に気をよくして、さらにスピードを上げる。先ほどまで感じていた疲れもどこかに吹き飛んでいた。
ゴールまでの目印である看板がようやく目に入る。
さぁ。ラストスパートだ。
俺はフルパワーで、しかし万に一つも朱音を振り落とすことのないように注意しながら自転車を思い切り飛ばした。
「わぁ……きれい……」
「だろ? 俺のお気に入りの場所なんだ」
燃えるようなオレンジの夕日。ミニチュアのように小さくなった建物を、みんな鮮やかな色に染め上げている。
学校の裏の小さな山にある高台。そこから見下ろす景色の中でも、夕日が沈みかけるこの時間は特にお気に入りだ。
「その……体は大丈夫か?」
「うん! 全然なんともないよ! 蒼太くんが安全に走ってくれたから!」
それを聞いて、俺は胸を撫でおろす。
朱音は生まれつき病弱で、激しい運動をすればすぐ体調を崩してしまう。
自分の足で遠出なんてもってのほかだ。
だから俺は、朱音を連れ出して、自転車の後ろに乗せてここまで来た。
家と学校と病院の往復だけでは見られない、俺の自慢の景色を見せたかったのだ。
朱音がふとこちらに向き直る。そよ風に揺れる細やかな黒髪が、夕焼けを反射してキラキラと光る。
「蒼太くん。こんなきれいな景色を見せてくれて、ありがとう」
いつも控えめな朱音が見せる満面の笑み。雪のように白い肌と夕焼けのコントラストに彩られた笑顔に、思わず目を奪われる。
「お前もきれいだよ」という率直な感想がこぼれそうになり、慌てて咳払い。それじゃあ恋愛ドラマのキザなセリフそのものじゃないか。
俺は「あぁ」なんて適当に返しつつ、自転車の前カゴに入ったスポーツドリンクを取りに行った。
夕日のスポットライトを浴びて誇らしげに立つ俺の自転車。俺と朱音をここまで運んでくれた、大事な相棒だ。
俺は自転車が好きだ。自分の足で漕げば漕いだ分だけ遠くに行くことができる。遠くに行けば行くだけ知らない景色を見ることができる。
そこで、一歩引いた視点にすっと切り替わった。
そうだ。これは俺が小学六年生の頃の思い出だ。
この出来事をきっかけに俺は本格的に自転車にハマることになった。やがて親に小学校卒業と同時にプレゼントしてもらったロードバイクで自転車競技を始めた。中学三年生になった今では、アマチュア大会に出て何度か表彰されている。高校は自転車競技部のある学校に入る予定だ。
その後も俯瞰した視点から夢は続いていった。一通り景色を楽しんで日が完全に沈もうかという頃に俺と朱音の両親に発見されたこと。無事を確かめ安心された後、母さんこってり絞られたこと。翌日、父さんにそんなに自転車なのか好きかと聞かれ、いかに自転車が好きかを心のままに語ったらスポーツサイクルの存在を知らされ心が躍ったこと。
全てがキラキラした思い出だ。
俺ってこの時から自転車が好きだったんだな。今考えればあの時は相当無茶したよな。
懐かしい気持ちで思い出のムービーを眺める。
その時、突如視界が一面の闇に覆われた。
先ほどまで広がっていた景色はすべて消え失せる。明かりを求めて足を動かすが、すぐに足がもつれてその場に倒れこむ。
息が苦しい。体が重い。
思わずその場に蹲っていると、誰かのすすり泣く声が聞こえてくる。
……ごめんなさい……ごめんなさい…………
それは他でもない、朱音の声だった。
俺は重苦しい空気を力ずくで跳ねのけ、顔を上げ、手を伸ばし――
「朱音っ!」
身体にかかった布団を弾き飛ばし、飛び起きる。
寝汗で湿ったパジャマ。拘束が徐々に解れていく身体。
悪夢からの目覚め特有の感覚だ。
途中まで心地いい夢を見ていたのに、最後で台無しだ。
もやもやした感情を抱きつつ、さっさと気持ちを切り替えるために顔を洗おうとしてベッドから降りる。
「あれ……?」
か細い声が喉から漏れる。
周りを見渡すと、見知らぬ部屋。全体的に質素にまとめられているが、目を引くのは俺の数倍はあろうかという数の本が入った大きな本棚。そして何より、俺が通う中学の女子制服。
いや、よくよく見ると見覚えがある。
置かれている物は少し変わっているが、全体図は思い出の中にある部屋に一致していた。
ふと下を向くと、目に入るのは着た覚えのない薄緑のパジャマ。花柄の縁取りのされた袖から覗く手は、きめ細やかな白い肌の、傷一つない小さな手。
手を上から下へと順に這わせていく。
薄く脂肪が乗った胸。なだらかなくびれを描く腰つき。すっきりとした股座。
これはまさか……
やけに力の入らない足取りで鏡の前に立つ。
「な、なんで……?」
そこには、中学生になった朱音の顔が写っていた。
青ざめた白い肌、ふるふると震える小さな唇、長い睫毛の丸い目は大きく見開いていて。
中学に入ってからはだんだん疎遠になり、小学生の頃から育っていない小柄な体つきを遠目に見て「あいつ全然成長しないなー。ちゃんと食ってるのか?」などと心配しつつも他人事のように思っていた少女。それが他ならぬ自分の身体となっている。
頬をぺたぺた触り、さらさらのショートヘアを乱雑に掻いてみても、小さな手のひらは見た目の印象通りの柔らかくすべすべした感触を伝えてくる。
年頃のスポーツ男子相応にごつごつしたそれとは正反対の、儚く頼りない感触。
これも夢の続きなのだろうか?
「朱音……」
現実逃避するように、朱音の声で朱音の名前を呼んでみる。
スポーツ男子の泥臭さとは無縁の、清楚という言葉をそのまま形にしたような無垢な少女。全然成長しないなどと思っていたが、間近で見るとわかってしまう。こいつは俺が知る頃よりもさらに女としての色気を放っている。
鏡の中の、黒目がちな澄んだ瞳と目が合う。この顔が今は俺のものとなっているという倒錯感に眩暈がしてくる。
そのまま熱に浮かされるように、パジャマのボタンに手をかけ――
ぴりりりり! ぴりりりり!
「ひゃあっ!?」
突如、小鳥のさえずりのような電子音が鳴り響いた。
慌てて鏡の前から飛び退く。
それが電話の着信音であることに気づき、勉強机に置かれたピンクのカバーのスマホを恐る恐る手に取る。
着信音に表示された名前は「蒼ちゃん」。すなわち俺の名前。逸る気持ちを抑えつつ、受話器を上げるボタンをタップする。
「蒼ちゃん! 蒼ちゃんだよねっ!?」
「あ、あぁ……お前は朱音か?」
なよなよした仕草で半泣きになっている俺の姿を嫌でもイメージしてしまう声色に溜息をつきたくなる。やはり俺の身体には朱音の魂が入っているようだ。
俺たちは昼食後、家族が出かけている朱音の家で落ち合うことにした。
今日は日曜日。状況が把握できないまま学校に行くことにならなかったのは不幸中の幸いか。
「じゃ、じゃあこうなった原因は全然分からないのかよ……」
「うん……朝起きたらこうなってて……」
眉をハの字にし、申し訳なさそうに目を伏せる俺の姿をした朱音。見ているこっちの方が申し訳ない気分になるような情けない姿。ましてやそれが俺の顔となると、正直キツいものがある。
「とりあえず、病院とかに行った方がいいのか……?」
「そ、それはダメだよっ!」
急な大声についビクっとなり、反射的にぎゅっと目をつぶってしまう。
先ほどから背中を丸めていて気付かなかったが、朱音こと今の俺から見て、俺の身体は思った以上に大きく見えてしまう。
「ごめん……でも……身体が入れ替わったなんて言っても誰も信じてくれないと思うし、下手したらその……大変な病気だと思われて元に戻るどころじゃなくなるかも……」
再びしゅんとした猫背に戻る朱音。
でも、確かに一理あるかもしれない。ただでさえ病気がちな朱音が「身体が入れ替わって中身が男になった」なんて言い出した暁には、いよいよ精神病まで発症したかと思って大騒ぎする可能性は大いにある。
ここは騒ぎを大きくせず、俺たちだけで元に戻る方法を探していくべきか。
それにしても……
朱音が動かしている俺の身体を見ると、同時に俺が朱音の身体を動かしているという事実もはっきり意識してしまう。
着替えの際はとにかく無心で少しでも男物に近い服装をとシャツとジーンズを選んだが、ノーブラだと乳首が擦れるというのは本当だったんだと思い知る。
胡坐で座ったことなんてないであろう朱音の身体だと自然と内股の正座になってしまうのだが、そうなると股間には何も生えてないということも明確になり、頼りなさからもじもじと太腿をこすり合わせてしまう。
俺も朱音に負けず劣らず悶々とした表情をしていることだろう。
「と、とにかく! 元に戻れそうな方法を片っ端から試していくぞ!」
その後、俺たちは本やネットで見た創作や与太話に至るまで、入れ替わり現象に関する情報を片っ端から集めた。
しかし思い当たる原因はやはりなく、入れ替わりのキーになりそうな行動を命に危険のない範囲で試してみたが、成果は得られなかった。
「キスをしたら入れ替わる」なんてのも試す流れになったが、さすがにお互い抵抗があり、頬にキスで済ませたのだが……マウスtoマウスはどうしても元に戻らなかった場合の最終手段ということにしよう。
夕方5時過ぎ。朱音の家族が帰ってくる頃となり、とりあえず今日は身体に合わせた家で過ごして明日からの生活についての情報共有は夜にスマホで行うこととなった。
俺の家に帰っていく朱音を見送ると、どっと押し寄せてくる疲労感。ロードレースのトレーニングや大会の後にくる疲労も相当なものだが、それとは根本的に違った重苦しさ。
「はぁ……はぁ……っ……」
肩で息をしなければ呼吸もままならない。頭を締め付けるような頭痛まで襲ってくる。軽く痺れる手を壁につきながらどうにか辿り着いたトイレで、腹の中のものを全て戻す。
確かにこれは無理できないな……。
身近に朱音がいながらどこか自分には無縁だと思っていた「病弱少女」の生活の苦労を思い知る。
朱音から聞いていた体調不良の際の頓服薬を水道水で流し込み、薬の副作用の睡魔の赴くままにベッドに倒れこむのだった。
翌朝。俺と朱音は、昨日できなかった情報共有をするために久々に一緒に登校していた。
幸い俺も朱音も相手から見たイメージ通りの人間関係ということで、そこまで複雑に気を遣う必要はなさそうではあった。尤も、それを実際にできるかというのはまた別問題ではあるのだが……。
「……スカートってこんなに頼りないんだな……」
下に何も履いておらず、下着を晒しているような不安感。そのくせ歩くたびに脚にひらひらと纏わりついてくる。そばをいかにも「スカートめくりは悪ガキのたしなみ!」とか思ってそうなやんちゃな男子小学生が通るたびに身構えてしまう。
「あはは……そうかも。逆にズボンはやっぱり楽だね。それに……その……男の子のアレって……ちゃんと歩くときに邪魔にならないようにできてるんだ……」
朱音の口からその手の話が出たこと、しかもそれが俺の姿で股間を気にしながら顔を赤らめての発言という光景に絶句する。
俺もとやかく言えないが、朱音もまた異性の生活に戸惑っているようだ。
「よっ! 蒼太! 朝からデートとはお熱いねぇ~♪ あの鈴川もその気になれば幼馴染アドで……ってことか~? ったく羨ましいねぇ~!」
などと思っていたら、早速試練が訪れた。突如現れた、ソフトオールバックのにやけ面の男。
開口一番安っぽい冷やかし文句を飛ばすこいつは
「って、えっ……何その反応……? もしかしてガチなやつかよ!」
朱音は頬に手を当て「デート……えへへ…………」などと恋に恋する少女の表情でのたまっていた。思わず額に手を当てる俺。
仕方がない、ここは俺が誤魔化しておくか。
適当な言い訳を作り、脳内で朱音の口調に変換し、ドキドキしながら口を開く。
「そ――」
「そうなんだよ。将来デート相手ができた時のために練習したいって言ったら朱音が協力してくれたんだ。デートに見えてるなら嬉しいよ」
「なんだよそれ~! お前もまだ非モテ組なのかよ~。ってかデートの練習に付き合ってくれる相手がいるだけでも羨ましい! とっとと爆発しろ!」
しかし、その必要はなかった。朱音はデレデレした顔を「馬原蒼太の顔」にすると、俺が考えた言い訳を俺の口調で完璧に再現した。
その後も新平とのやり取りをそつなくこなしていく。俺の生き写しかと見紛う再現度に、ほっと胸を撫でおろした。
「ってことは朱音さんはまだフリーってこと? 俺にもワンチャンある!?」
「んえっ!?」
突如こちらに振り返り、無駄に爽やかな笑顔を向けてくる新平。安易に女子の身体に触れたりしないのが良くも悪くもこいつらしいが、それでも「女を見る男の目」を向けられる感覚には男としては寒気がする。
「こらぁー! このスケベナンパ野郎ー! チャラ男風情が朱音に手を出すなー!」
「げっ!? 真那! じゃあなラブラブなお二人さん!」
脱兎のごとく逃げ出す新平。後ろから通学カバンを振り上げ猛追してくる、八重歯をむき出しに鬼気迫る表情の長身の女子。
こちらは
整った容姿に男女問わず面倒見のいい勝気な性格から、女番長だの女騎士だの呼ばれてこちらはこちらで一定の人気があるようだが、本人はそういった方面には無頓着なようだ。
「まったく……朱音、大丈夫か? 変なことされてないか?」
「えーっと……うん、なんともないよ。真那……ちゃん」
「ほんとに? なんか顔赤いけど……体調悪くなったらちゃんと言いなよ?」
顔が赤いのは朱音になりきって女子と話すのが気恥ずかしいからだ、などとはとても言えなかったのだが、どうにか深く突っ込まれずに済んだ。
こうして今度は俺が朱音として振る舞う練習をする番となり、蒼太のフォローもあってどうにか乗り切りつつ、教室にたどり着く。
俺と朱音の入れ替わり生活が幕を開けた。
「お……おぉ……」
なんとか無事に朱音として振る舞い迎えた昼休みの教室。俺は茫然と立ち尽くしていた。
カーテンを閉め切ったこの空間にいるのは、全員女子。俺の存在など意に介さず、自然に制服を脱ぎ、体操服へと着替えていく。
五時間目は体育。それに備えて体操服に着替えるわけだが、今は俺もまた女子である鈴川朱音。男子禁制の場所にいてもお咎めなし、むしろ男子に混じって着替える方が問題なのだが……
右を見ても左を見ても、女子の着替え。服の上から想像するしかなかった裸体が嫌でも目に入ってしまう。健全な男子である俺には刺激が強すぎる。
「朱音~。早く着替えないと遅れるぞ~?」
「ひゃ、ひゃい!?」
真那が上半身にブラジャーだけをつけた状態で声をかける。クラスの女子の中でも特に発育のいい方だと男子の間で噂になっていたが、ついに実物を見てしまった。
「もしかして、体操服忘れたの?」
同じく朱音の仲のいい友達である
「あ、あるよ! 体操服あるよ!」
動揺のあまり片言になりながら体操服の入ったナイロン袋を取り出す。
袋を開くと、柔軟剤の香りとともに女子の体操服が現れる。
ごくりと生唾を飲み込み、覚悟を決める。
「えいっ!」
極力周りを見ないようにしながら、高速で制服を脱ぎ、超高速で体操服へと着替える。
「じゃあわたし、先に行ってるからー!」
そう言い残し、女子更衣室となっている教室から一目散に立ち去った。
今の俺なら女子の着替えも覗き放題! と思えるほど図太くはなく、しかしもう少し見てしまっても不可抗力だから許されるのでは? と思ってしまう自分もいて……
何にせよ。俺の大好きな体育だ。身体を動かして煩悩を払おう。
「そうか……そうだよな……」
日陰のベンチにちょこんと座りながら、見学レポートに鈴川朱音の名前を記入する。
朱音の身体は運動などもってのほかで、体育はいつもレポート提出となっていた。それは中身が健康体男子の俺に代わっても同様で、張り切って体育に参加しようとしたところ体育の先生に血相を変えて止られた。恐らく学校全体で「鈴川朱音は運動厳禁」が徹底しているのだろう。
仕方がない。元に戻るまでの辛抱だ。
というか、ろくに運動したことがないあいつはちゃんとやってるだろうか。
ウォーミングアップでグラウンドをランニングしている生徒を後ろから順にチェックしていく。しかし、どこを探しても俺もとい馬原蒼太の姿は見当たらない。
いや、あいつは先頭集団にいた。やけにピンと胸を張った姿勢で、ランニングにしてはやや大振りに手足を動かし、颯爽と駆け抜けていく。それはまるで、思い切り身体を動かせる喜びが顔を輝かせながら。
やがて見学者ベンチに接近するタイミングで、朱音と目が合う。すると一層顔を綻ばせ、さりげなくピースサインを送るとすぐさまスピードを上げていった。
「運動って楽しいね!」そう言わんばかりの楽しげな笑顔を見て、俺も少し嬉しくなった。レポートには「馬原君が楽しそうに走っているのがよかったです」とでも書いておいてやろう。
その後も運動初心者朱音の活躍は続いた。
サッカーのパス練習が始まればペアの新平相手に正確無比なパスを送り、試合が始まれば完璧なポジショニングからのシュートを次々と決めていく。
俺もサッカーは好きで、本職のサッカー部員には及ばないまでもそれなりに得意なつもりではあったが、ここまで活躍したことはあっただろうか。
普段以上の大活躍に、男女から賞賛の視線を集める俺の姿をした朱音は遠慮がちに、しかし喜びを隠しきれない様子だった。
体育の後、こっそり朱音を呼び出す。
「すごいじゃないか朱音! もしかして、サッカーやったことあったのか?」
「まさか。わたしは運動ダメだから……。蒼ちゃんの身体が動きを覚えててくれたおかげだよ」
ウインクとともに力こぶをつくるポーズをとる朱音。俺の身体で可愛らしい仕草を見せられてもうすら寒いだけ……かと思ったが、運動で身も心も爽やかな状態が放つ空気のおかげなのか、不思議と純粋に愛らしく見えてしまう。
「あとは……やっぱり見学レポートのおかげかな? 考えてた通りの動きができて楽しかった♪」
それを聞いて、以前体育の先生が朱音のレポートをべた褒めしていたことを思い出した。鈴川のレポートは一人一人の動きから全体の位置取りまでよく観察し、自分なりの改善案の考察までしっかり書かれている。見学レポートとはかくあるべきだ、と。
今思えば、それはまるで、自分が運動をしている光景をリアルに思い浮かべ、もし自分が運動できたらどんな風に動けばいいかを綴っているようであった。そう、こんな日のために……
「あ、早く着替えないと六時間目に遅れちゃうよ!」
時計をちらりと見た朱音は教室にダッシュ――しかけて「っとと。廊下は走らない、だね」と律儀に早歩きしていく。
「……よかったな」
俺もその後を追って、朱音の身体に負担をかけないようにゆっくりと歩いていくのだった。
その日の放課後。人通りの少ない道路にて、朱音がロードバイクに乗る練習もしてみることになった。
元に戻るまで大会には出られなくとも、もし可能なら身体は鈍らせないでいてほしい。「身体が覚えている」が通用するなら、無理のない範囲で朱音にトレーニングをしていてもらえないかと頼んでみたところ「喜んで!わたしも蒼ちゃんのかっこいい自転車に乗ってみたかったんだ」と快い返事がもらえた。
一応今は近場にママチャリで出かける程度ならできるという朱音だが、ロードバイクで落車した際の危険は通常の自転車の比ではない。まずはサドルに跨って数メートル進む練習から……と思ったのだが、あっさりとクリア。距離を伸ばしての走行も最初はぎこちなかったものの、コツを掴めばすいすい進むようになった。さらには全力スプリントも、朱音がスピード感に慣れてくれば問題なくできてしまった。
日が沈んできた頃「もっと乗りたい!」と言う朱音をなだめ、基礎体力トレーニングのリストを渡して家に帰ることになった。
それからも学校での体育で活躍し、さらにトレーニングもこなす朱音。週末のサイクルスクールでの練習にも俺に代わって復帰し、より実践的なトレーニングも順調に重ねていった。
月末には元に戻らなければ参加を見送ろうと思っていた大会に出場し、俺と遜色ない結果を残していた。
俺はというと、運動厳禁のか弱い女子としての生活が続くばかり。限られた行動範囲の中で入れ替わりに関する情報を探してみるが、一向に手掛かりは見つからない。
こんなにも運動から遠ざかったのは生まれて初めてではないだろうか。身も心も縛られるような感覚。
あぁ、早く元に戻りたい。女子の生活も男として役得ではあったが、やはり俺には自由に動く身体が必要だ。思いっきり動き回りたい。
でも朱音は運動ができる生活を心から楽しんでいる。もしかしたら、あいつの方が馬原蒼太に相応しいのかもしれない。
それは嫌だ。
もう――何もかも嫌だ。
入れ替わりから二か月ほど経った頃、俺は家に引き籠るようになった。
「じゃ。ごはん作り置きしてるから。……行ってくるわね」
出勤前の朱音の母親の声を布団越しに聞く。
「今までいろいろ我慢して真面目に頑張ってきたんだから、ちょっと無理しすぎたのよ。ゆっくり休んで、ちょっとずつ元気になりなさい」
大事な一人娘が部屋に閉じこもるようになっても温かく見守ってくれるが、俺はかえって罪悪感に苛まれることになる。
朱音や、真那を始めとした朱音の友達も心配して連絡し、直接家に来たりもした。だが、こちらが体調が悪いと言えばそれ以上は何も言うことができず、みんな作り笑顔で引き下がることしかできなかった。
病弱な朱音の身体に俺の心のストレスが重なったことによる慢性的な倦怠感。仮病じゃないといえばそうなのかもしれない。だが、朱音の身体のせいにするのは気が咎めるので、やっぱり俺の心の弱さが作り出した、朱音としての生活から逃げるための仮病なのだろう。
「んっ……くっ……」
あぁ。またやってしまった。
そう後悔しても、もうこの手は止まらない。心にもやもやしたものが広がった時は、ついこの「運動」に耽ってしまう。
内股を擦り合わせ、股間に右手を挟み入れる。未だ毛の生えない割れ目の内側に、触れるか触れないかの微弱な刺激を加え、とろ火のような淡い火照りを身体に広げていく。
「くふっ……! んぁ……っ!」
じんわり汗をかいてきたところで、指を折り、膣内に挿入する。全体をゆっくり掻き混ぜるように動かし、敏感な部分の周りを少しずつ撫でていく。
肩を寄せ、薄い胸に少しでも膨らみを盛った上で、余った左手で乳首を掻きつつ乱雑に揉む。
息が荒くなっていく。だがまだこの身体に休みは与えない。
二次性徴にも恵まれず、起伏の乏しい朱音の身体。お前も女なら雌の快楽を差し出してみろと言わんばかりに執拗に責める。
朱音の身体がこういった行為の経験があるのかはわからない。だが、そんなことはもうどうでもよかった。
俺はこの身体に閉じ込められて、生きがいを奪われた。だったらどう使おうと俺の自由だ。
黒い感情がどんどん広がっていく。穢れを知らない朱音にあるまじき後ろ暗い感情。
「んひゃあっ! くふっ……! ふぁっ!」
そのまま陰核を執拗に責める。触れるたびに身体がビクンと跳ね上がる。
そうだ。このまま女としての快楽をずっと叩き込んでいれば、この貧相な身体の発育も少しは良くなるかもしれない。
朱音は俺の身体でスポーツ少年としての青春を楽しんでいるんだ。俺も女としてこの身体を勝手に開発してやろうか。
「はぁっ。はあっ。えへへ……ごめん。わたし、えっちな悪い子になっちゃった。蒼ちゃんに毎日犯されて、もうえっちなことしか考えられないの♡」
朱音の口調を真似て、朱音が絶対に言わないことを言ってみる。すると背徳感が刺激され、身体は本能的な羞恥心からかさらに熱を帯びる。
さらに湿りだした割れ目を、くちゅくちゅと厭らしい音をわざと立ててより激しく責める。
「んはあああっ! あはぁっ!」
さらに大きな快感に、思わず上半身が前後に揺れる。枕の上で髪を振り乱して快楽を貪る。
しかし早くも酸欠状態になり始めたこの身体は、徐々に頭への圧迫感を訴える。
仕方ない。ここまでまでにしてやるか。
「はぁっ……はあっ……んあぁぁぁぁぁっ~~~~~!」
陰核を強く摘み上げ、ひときわ大きな快楽の波を引き寄せる。明滅する頭の中。ビクンビクンと跳ね、ベッドの上に投げ出される身体。
そのまま仰向けになって、虚ろな目で天井を眺めながら息を整えた。
布団をめくりあげ、染みになっていないかを確認する。カーテンを閉じたまま窓を開け、甘ったるい女の匂いを外に逃がす。
汗をかき、身体に負担を与え、快感を得る。今の俺にできる唯一の運動だ。
仄暗い充足感とともに淡々と処理を終える。
パソコンを起動し、オンラインゲームにログインする。暇つぶしに引き籠りらしくインドアな趣味でも始めてみるかと気まぐれで登録して以来、惰性で続けている。
「へぇ。今日もこんな時間からご苦労さんだな」
勝手に引き籠り仲間扱いしているログインメンバーを見て、朱音の甘い声でわざとらしく擦れたトーンでつぶやく。
「なんだよ……」
いつものようにだらだらとプレイしようかというところで、マウスが反応しなくなる。どうやら電池が切れたらしい。
確か電池は机の引き出しに入っていたはずだ。すっかり勝手知ったる朱音の机の引き出しを漁り、電池を探すがなかなか見つからない。
そこで、引き出しの一番下に隠れていたノートがふと目に留まった。白地に赤のチェック柄のそれは、まるでそのまま存在を忘れられることを望んでいるように佇んでいた。しかし、同時に誰かに見つけられることへの淡い期待も抱いていた気がして、不思議な存在感を放っている。
ごくりと生唾を飲み込み。震える手でノートを開く。
最初のページを見たとき、目頭が燃えるように熱くなった。
溢れ出す涙をごしごしと拭い、それでも流れる涙はそのままに、描かれているものを目に焼き付ける。
色鉛筆で描かれた、鮮やかなオレンジをバックにした街並み。
俺と朱音の思い出の景色。
詳しいことはわからないが、中学生でももっと情緒的というか立体的というか、ちゃんと専門的な技法に則って描ける奴はいるのだろう。
しかし、生き生きと描かれたその情景は、今まで見てきたどんな絵よりも俺の心を打った。
ページを捲るたびに現れる、様々な風景、人物、動物。
はっと思い当たり、使い慣れないタッチパッドでデスクトップの「秘密」と書かれたフォルダを開く。
そこに入っていたのは、無数の写真。ネット上で見つけたであろう遠く離れた地の景色から、自分で撮ったと思しき身近なワンシーンまで。ノートに描かれた絵の元になっている写真もこの中にあった。
好きなものを一生懸命描いたのであろうことはひしひしと伝わってくる。
鼻をすすりつつ、最初のページをもう一度見る。
あの頃の感情がふつふつと蘇ってくる。
知らない景色をたくさん見たい――
――何をやっているんだ俺は!
顔を洗い、制服に着替え、学校に向かう。
誰もいない通学路を歩いていく。
淡く上品な色合いの紫陽花。生垣の上で丸くなり眠る猫。雲間から覗く初夏の太陽。
背筋を伸ばし、目を見開いて見渡すと、見慣れたと思っていた景色も新鮮なものに思えた。
「みんな! 心配かけて――うわっ!」
「朱音~~~! 会いたかったよ~~~! ずっと待ってたよ~~~~~!」
休み時間を狙って登校した俺を迎えたのは、真那の力強いハグだった。というか普通に苦しい。華奢な朱音の身体が折れそうだ。あと、胸が顔に当たってる。
「朱音。もう身体は大丈夫なの?」
真那を引き離しつつ、海歌がそっと慎重に肩に触れる。
「うん。もう平気。やりたいことができたら元気になっちゃった」
「やりたいこと? なんだなんだ?」
真那が興味深そうに尋ねてくる。
「わたし……みんなと一緒に色んな場所に行ってみたい。遠出できるように身体もちょっとずつ強くしていきたい。それで……このノートにみんなと見た素敵な景色を描いていきたい!」
例のノートを取り出す。朱音の目で見た世界を景色を描く秘密のスケッチブック。その続きは俺が描いていく。
絵なんてろくに描いたことはない。しかし身体が覚えているのは俺も同じはずだ。そうでなくとも、一から身体に叩き込んでいく。これでも俺は元スポーツ少年。そういうのは得意なつもりだ。
だがそのためには、仲間の支えも必要だ。
「うぅぅぅぅ~~~! 朱音~~~~~! 感動した~~~~~! いいぞ! あたし達と一緒に強くなろう! まずは毎日夕日に向かって青春のフルマラソ――ぐえっ!」
「ちょっとずつって言ってるでしょ! あー、この脳筋女はさておき、私も応援するわよ。いいじゃない。今まで行けなかった色んなとこ、遊びに行っちゃおう!」
朱音と話したのは放課後だった。
「今までごめん。お前の身体で情けないことしてた」
「こっちこそごめん。運動できるのが楽しくて蒼ちゃんの気持ち考えてなかった……」
予想通り、気まずい沈黙が流れる。
俺に言わせれば、朱音は何も悪くない。今まで憧れていた運動が好きなだけできるとなれば、浮かれるのも無理はないだろう。俺が朱音でも――というか実際なってしまったから嫌でもわかるのだが――同じ状態になるに違いない。
「わたし、昔からずっと蒼ちゃんに憧れてたんだ。運動ができて、どこにでも行けて……いつからかわたし、蒼ちゃんになりたい、って思うようになってた。それが叶っちゃって、つい蒼ちゃんの生活に夢中になっちゃった」
「朱音……」
「今まで本当にごめんなさい……」
涙目になり、頭を下げる朱音。
そもそも入れ替わりなんて本当に起こる方がどうかしているんだ。むしろ俺の方こそ朱音の身体を穢してしまったのだ。
だが、どうしても断罪がお望みなら仕方がない。もう少し段階を踏もうと思っていたが予定変更だ。
「このノート、見たぞ」
「あ――」
一瞬の絶句ののち、口をぱくぱくしながら声にならない悲鳴を上げ、両手をぶんぶん振る。
だが、俺にはお前が封印していた過去など手に取るようにわかってしまう。
「お前のことだ。あの時の景色を絵に描くのを目標にこっそり絵の勉強を始めたけど、こんな完成度じゃ本物には及ばないと思って、他の絵で練習してみたけど目標にはなかなか追いつけず、実物を見に行けないこの身体じゃ……とか思って描くのを辞めたんだろ?」
両手で顔を隠し、頭から湯気を出しながら俯く朱音。どうやら図星だったらしい。
「俺は好きだぞ。お前の絵」
まっすぐに伝える。心からの俺の想い。
「だから……お前の代わりに俺が絵を描く。お前は俺の代わりに自転車に乗る。二人で互いの夢の続きを追いかけるんだ」
ノートを左手で抱き、右手を差し出す。
「――うん! 一緒に頑張ろう!」
俺の小さな手を、朱音の大きな手が包み込み、優しく、しかし力強く握った。
「じゃ。行ってくるね」
高校卒業を控えた春休み。
俺は真那と海歌に力を込めた視線を送ると、サイクルグローブのテープを締め直す。傍らには朱音の――俺の身体に合わせた、体力の消耗を抑えることを最優先に調整したロードバイクがある。
「頑張って。私の計算によれば、今の朱音の体力ならクリアできるはずよ!」
海歌が眼鏡を指先で持ち上げながら得意げに呟く。頭脳派としての自負があるらしい海歌は、俺の体力強化プログラムを様々な理論に基づいて完璧に組んでくれた。そのおかげで俺は無理なく最適なトレーニングで少しずつ、しかし着実に丈夫な身体づくりをすることができた。
「というわけで朱音~? 体調の最終調整のマッサージをするわよ~。さぁ……その最高級に仕上がったすべすべ柔らかボディを……うへへへへ……」
「そ、それはさっきやったでしょ!」
頬をだらしなく緩め、怪しい手つきで近づいてくる海歌から逃れる。どうやらこの三年間、海歌は俺の身体のチェックし続けるうちに何やら変な方向に目覚めてしまったらしい。
海歌のマッサージの腕は本物で、それはもう天にも昇る心地よさなのだがその……気持ち良すぎて人前で上げてはいけない声を上げてしまいそうになる。そして顔を赤らめ声を押し殺す俺を見て、海歌はますます興奮してしまうのである。
「ははっ! 今日も絶好調だな! さぁ朱音! 冒険同好会の初代部長として、最っ高にカッコいいところを見せてこい!」
俺と海歌の追いかけっこが終わったタイミングで真那が突き出した拳に、俺も拳を重ねる。それに慌てて続く海歌。
同じ高校に進学した俺たち三人は「色んな場所に出かけて、そこで見つけたものについて記録し紹介する」という「冒険同好会」を立ち上げた。部員は最初は俺たち三人のみで、後に高校からの友達や後輩も入ったりしたものの結局この三年間では部として正式に認可されなかったのだが、それでも、皆で興味の赴くままに色々な場所を巡る日々はとても充実していた。
何より、そこで見た景色を俺が絵に描き、そこに他のメンバーの文章を加えた会報を発行して皆と楽しさを共有するのは、これ以上ない喜びだった。
プライベートでも色々なものをひたすら描いた。朱音から引き継いだノート、そして新たに買ったスケッチブック、さらにはデジタルでも描いていった。
描くたびに新たな発見があり、時に上手くいかずに落ち込むこともあり、しかしそれでも描き続けて一段上のステップにたどり着いて行き……そんな楽しさは自転車競技に通じるものがあった。
そんな高校生活の締めくくりとして、描きたい絵は決まっている。今日はそこに自分の足で訪れて描きに行く。
「朱音ちゃーん! ファイトだ~! 今日も可愛いぞ~!」
ちゃっかり同行していた新平が、女子の呆れ半分微笑ましさ半分の視線を浴びつつ、輪の外から声を張り上げる。
こいつも同じ高校に進学し、俺こと朱音を彼女候補の筆頭としてアプローチをかけ続けていた。朱音としての新たな友達と過ごす日々は充実していたものの、それなりにいた男友達との交友が途絶えることに一抹の寂しさはあった。
冒険同好会の活動に絵に体力トレーニングにと忙しく、少なくとも高校では誰かと付き合うつもりはなかったが、結果的に新平は俺が女になってからも一番仲のいい男友達であり続けた。その存在は、やはりありがたかったと思う。
大切な仲間たちの顔を見渡し、自転車に跨る。
「うん! この町で一番のとっておきの冒険、思いっきり楽しんでくる!」
ギアを軽めに設定したペダルを小気味よく回し、ひたすら前に進んでいく。
流れていく景色は代り映えしない地元の町。しかし、自転車を漕ぎながら見るのは何年振りだろうか。
この身体になって気付けば三年が経った。その間に色々なことがあった。嬉しいことも悲しいことも、この身体に全部乗せて走っている。
高校でも「庇護欲をくすぐるお子様体型の儚げな病弱美少女」は男女を問わず一目置かれていた。俺もそういった視線を意識して、内心満更でもなかった。
でも、俺にはやりたいことがあった。守られているだけでは手に入らないものの方へとどんどん足を踏み出し、手を伸ばしていく。そんな俺と一緒に走ってくれた仲間たちには感謝しかない。
平坦な道を通り抜け、小学校の裏山を登っていく。もうひと踏ん張りだ。
先ほどから身体が疲労を訴えている。息が上がり、足も心なしか重くなってきている。
海歌特製スポーツドリンクの入ったボトルを手に取り、口全体に水分を十分行き渡らせてから嚥下する。貴重な水分も残りわずかだ。
身体が徐々に重くなり、気を抜けば俯き加減になってしまう。
やがて体力が限界に達し、一番軽いギアを回すので精一杯になる。
呼吸のリズムなんてものはとうに乱れている。頭も少しチカチカしてきた。
ここが限界なのか。
側道で足を止め、あとはゆっくり歩いていけという内なる声が聞こえてくる。
か弱い身体でよく頑張った。ひ弱な身体に無理させる必要はない。適当なところで諦めとけ。
「――舐めんな。こいつは……朱音は強いんだよ!」
気勢の声を吐き、最後の力を振り絞ってペダルを回す。
スポーツドリンクの最後の一口を放り込む。細く小さなこの身体の血を、筋肉を、骨を、脳を。全部使ってゴールを目指す。
前方から降り注ぐ、微かな光。今にも消え入りそうな、最後の輝きを熱く放っている。
タイムリミット寸前だ。だが絶対に諦めない。
ゴールまで残り数十メートル。数メートル。数歩。
「うりゃあああああああああっ!」
勾配から平坦へと切り替わるラインを踏み越える。ついにゴール。小学校の裏山の高台に辿り着いた。
だがまだ終わりじゃない。自転車を停め、フラフラの身体に鞭打ち、転落防止の柵近くのベンチまでよろよろと歩く。
そこには、かつて見た絶景が広がっていた。
地平線に沈む寸前の夕日。小さな町の全てに、鮮やかなオレンジの光を届けている。
それはまるで、自らの足で再びここに辿り着いた朱音を讃えるかのような、優しい光だった。
涙腺が緩み、一筋の涙が流れる。それを拭い、しっかりとこの目で、朱音の目で見据える。
「おっと」
自転車に取り付けたポシェットからスマホを取り出すと、この景色を何枚か撮影していく。
できればこの場で直接描き写したかったが、どうやら日没までは間に合わなさそうだ。しかし、写真さえ残しておけば、あとは帰ってから描けそうだ。
そう確信できるほど、脳裏にはっきりと焼き付いている。
「お疲れ様。やっぱりすごいね。蒼ちゃんは」
ベンチに深く腰掛け夕日を見ながら感慨に耽っていると、頭上から男の声が聞こえた。
「どうだ……やったぜ……」
朱音の澄んだ声が台無しのカラカラ声で返しつつ、とびっきりの力強い笑みをそいつに向ける。
高校トップクラスの自転車競技選手、馬原蒼太こと朱音の姿がそこにあった。
中学卒業後は自転車競技部のある県外の高校に入学。寮生活に加え三年になってからは国内外の代表大会にまで出ていたこともあり、直接会うのは三年ぶりだ。
朱音から差し出された市販のスポーツドリンクのボトルを受け取り、一気に喉を潤すと、ロードバイク専門誌の写真越しにしか知らなかった今の姿を改めてまじまじと見る。
中学時代よりも伸びた背丈。瞬発力と持久力を発揮しつつ柔軟性と軽量感を維持する絶妙なバランスで筋肉をつけた、サイクルジャージ映えする細身ながら力強い体躯。
「……かっこいいじゃん」
思わず頬が熱くなるのを誤魔化しつつ、小さな握りこぶしを作って軽くパンチをお見舞いする。
朱音も朱音で「えへへ……ありがとう」などと盛大に照れてふにゃっとした笑みを浮かべながら、スポーツ男子にしては艶のあるサラサラの黒髪を撫でる。
圧倒的な実力に加えて、その柔和な物腰にすらっとしたスタイル、さらにインタビューから垣間見える女子力の高さから「
「んっ……」
かつて俺のものだった身体を、肌触りを確かめるように抱きしめる。それでは飽き足らず、見た目に反して硬い腹筋に頬ずりする。
俺の身体。中身がそっくり変わり、外見も月日を経て変わってしまった。今や朱音の身体こそが自分の身体だと無意識のうちに思ってしまう。
だが、こちらも紛れもなく、愛着のこもった俺の身体だ。
密着したままスパッツの下にある一物を探り当て、感触を懐かしみつつ――
「わっ! ちょっ! と、とりあえず……帰ってから……ね?」
「う――わ、わかってるよ!」
中学時代の仲良し五人での同窓会を終えた後、俺と朱音は俺の家にいた。
両親は親戚一家との旅行に出ている。
帰ってくると、和室には既に二つの布団がぴったり並べて敷かれていた。
それを見て、思わず顔を見合わせ苦笑いする俺たち。
お互い風呂を済ませ、なんとなしに和室に入る俺たち。
そこで朱音は、いきなり俺を後ろから抱きしめると、そのままふわっと布団に寝転んだ。
もがく俺をよそに、髪の匂いを嗅ぐ朱音。
「いい匂い……わたしの身体って病院とか薬の匂いがしそうでちょっと嫌だったけど……蒼ちゃんのわたしは甘いお菓子みたいなとってもいい匂い……」
「お、お前もさっき俺のシャンプーとかボディソープ使っただろ……同じ匂いじゃないか……」
嘘だ。甘い匂いに混じってつんと、しかし不快ではない男の汗の香り。それを嗅いで俺の身体は早くも疼きを覚えている。
「はむっ」
「ひゃぁ!? や、やめろよ急にっ……」
「えへへ。わたしの身体、耳が弱いのも変わってないんだ」
背後から迫る朱音の手は、俺のパジャマのボタンを器用に一つ一つ外していく。
「わぁ……きれい……。わたしの身体、ちゃんと女の子のおっぱいなんだ……」
あらわになった乳房を反射的に隠すが、もっと見てほしいという本音には抗えず、ゆっくりと手をどける。小さくとも確かにおっぱいと呼べるほどに膨らんだ胸。ほんのり薄ピンクの乳首は見られていることに興奮して勃ってきている。
「それっ♪」
「きゃっ!?」
俺の胸に見とれていた朱音の隙をついて身を反転させると、お返しとばかりに朱音のスウェットのズボンとパンツを一気にずり下す。
ピンとそそり立った、かつて俺に生えていた棒。顔を赤らめ、内股になって隠そうとする朱音の手より早く顔を近づけ、間近でそれを観察する。
久々に見たそれはやはりグロテスクな形をしているが、やはり再会を懐かしむ気持ちの方が膨らんでくる。
「こちょこちょ~♪ ふ~っ♪」
子供の頃遊んだ玩具を久々に見つけたような気分が膨らみ、くすぐったり息を吹きかけたりして弄ぶ。
その度に甲高い悲鳴を上げて悶絶する朱音の反応が面白くて、無邪気な嗜虐心はさらに加速する。
それに呼応して、よりギンギンいそそり立ち、むせ返るような男の匂いも強くなる。
その匂いに、責めているはずの俺の脳までじわじわと犯され、下腹部はキュンキュンと疼き、股は既にじっとりと湿っていた。
パジャマのズボンを下ろし、股を開いてお誘いのポーズを取る。
糸を引き、とろとろになった俺の股に釘付けになりつつも、理性で必死にブレーキをかけている朱音。
「挿れてもいいぞ……今日は大丈夫だ」
「そっか……わたしの身体、病気で生理が止まったりとかしてないんだ」
「って、そういう心配するのかよ……」
「蒼ちゃん。わたしの身体を大事に強く育ててくれて……ありがとう」
「当たり前だろ。お前こそ、俺の身体をカッコよく鍛えてくれてありがとな」
「えへへ……じゃ、いくよ」
朱音がゆっくりと慎重に、男根を割れ目に挿入する。内側を小さくかき回し、入り口を広げていく。
体内に異物が入ってくる不快感。しかしそれを搔き消す快楽を与えてくれている。
「はああああぁっ! ああっ! いいっ!」
「うん! わたしも蒼ちゃんの膣内、気持ちいい!」
そのまま侵攻を進める朱音の槍。やがて、快楽に混じって、身体を引き裂かれるような痛みが襲い来る。
「ああああっーーー!」
「えっ!? ご、ごめん! 今抜くから!」
慌てて腰を引こうとする朱音を抱き寄せ、ふるふると首を横に振る。
大丈夫だ。朱音の身体なら、朱音が傍にいればこの痛みも耐えられる。
俺の意を汲んで、朱音はそのまま男根を奥へと進める。ますます強くなる痛み。
その果てに、腹の奥で何かがぷつっと切れたような感覚があった。
「ふぁああああっ!」
「ああっっ! 射精る! 射精るよ蒼ちゃん!」
俺が守り続けた処女を朱音に捧げられたという感慨に耽る暇もなく、朱音の肉棒の膨らみを感じる。
「いいぞ! 射精して! いっぱい射精してっ!」
「うん! 射精す! 受け取ってっ!」
「あああああああああっ~~~~~~~~!」
朱音の精が俺の中に大量に注がれた。腹の中を満たしていく。
快楽に頭を揺さぶられ、そのまま布団に倒れこむ二人。
「えへへへへ……」
愛する人の生命をたっぷり受け取り、笑みが零れる。
うっとりとしか気持ちで、下腹部を愛おしく撫でる。
そこで朱音と目が合う。どちらともなくよじよじと近づき、そのまま口づけを交わす。
ただ口と口を合わせるだけのキス。しかし、その時間がいつまでも続くといいのになと思ってしまうような、そんな幸せなキスだった。
スタンドに立てたスマホを凝視しつつ、後ろにいる朱音に声をかける。大学の裏庭で偶然見かけて撮影した、二匹の仲睦まじい猫。その愛らしさに見るたび癒されつつ、しかし被写体として冷静に見つめる視線も忘れない。
見えた。絵師・鈴川朱音の絵に落とし込む最高の構図が見えた。これは期待できそうだ。
ラフを描いたところで「ただいまー」というほんわかした男の声が聞こえる。
プロデビューが確実視されている大学ロードレース界のスター・馬原蒼太のお帰りだ。
同じ大学に入学した俺たちは、そのまま半同棲カップルとなった。
同じテーブルを挟んでの夕食。海歌監修のもと俺が腕によりをかけて作った、栄養と味を両立した手料理だ。
今日も最高に美味しい!と花丸評価をもらい、実に誇らしい気分だ。
「そういや次の大会、いつ出発するんだ?」
「再来週の水曜日だね。蒼ちゃんは一緒に行けそう?」
「あぁ! この前のイラストが入賞した賞金もあるからな。ネトゲ友達にも泊まりの話はつけてあるし、向こうでお前の応援にも行って、それから現地で絵も描けるぜ!」
俺と朱音、入れ替わりによって運命は大きく変わったのかもしれない。事実、スポーツサイクルのプロ選手になるという俺の未来は潰えてしまった。
だが、新しい夢や希望もたくさん見つかった。
知らない景色をたくさん見る。朱音に笑顔を届ける。そんな俺の願いは、形を変えて叶っている。
そして、その願いに終わりはない。
「じゃ、今日の練習も頑張ってこいよ!」
「うん! 蒼ちゃんの新しい絵、楽しみにしてるね!」
これからも俺は、大切な人と一緒に走り続ける。
知らない景色を二人で見に行くために。